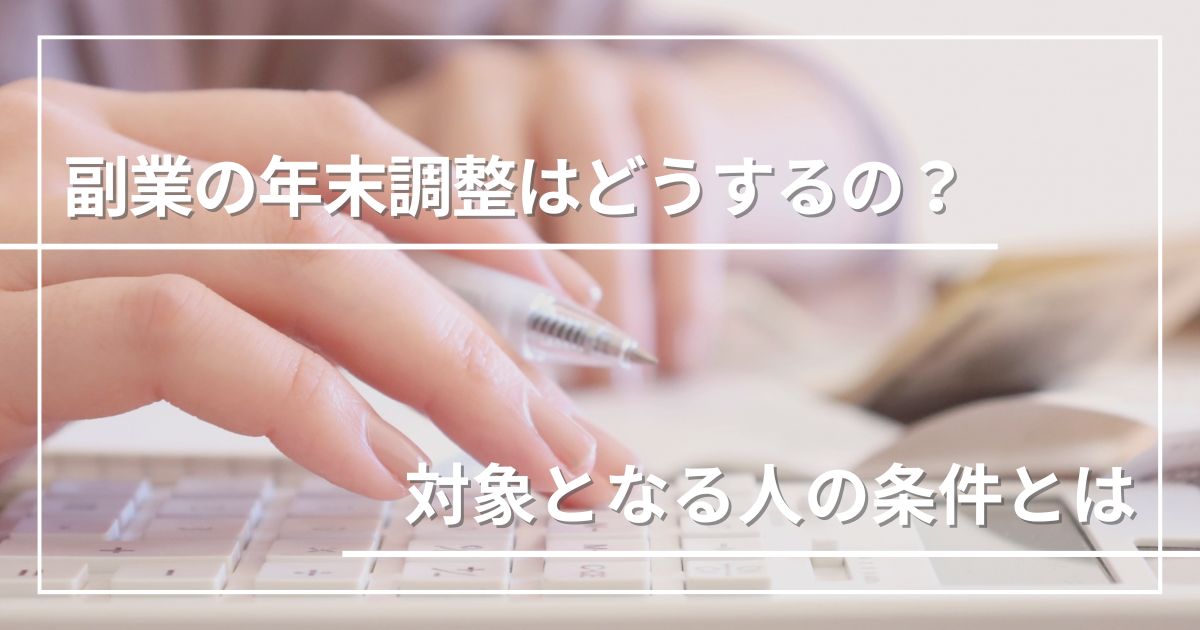働き方改革で副業を解禁する企業が増えたり、コロナ禍以降に副業を始める人が増えてきました。
これから二拠点生活をするための資金計画においても、副業で増やしたいという方は多いかもしれません。
しかし、副業をスタートした人でも意外と知らないのが年末調整の仕組みです。
1社のみからの収入であれば年末調整をするだけで所得税の納付が完了しますが、副業を行っていればそういうわけにはいきません。
今回は、副業をしている場合に年末調整の対象になる人の条件や、確定申告が必要か判断するポイントについて解説します。
年末調整とは
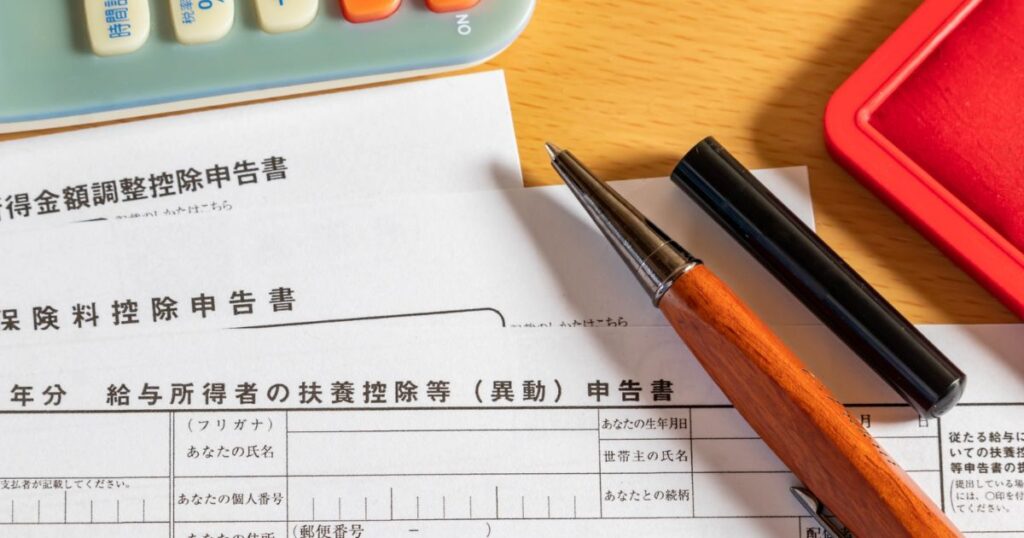
年末調整とは、会社に勤める給与所得者が1月1日から12月31日の1年間に源泉徴収された所得税額を正しく計算し、各種控除を反映して納税額を確定させる手続きのことです。
会社員やパート・アルバイトとして会社に雇用されている場合、毎月の給料や賞与などから所得税が差し引かれます。これを源泉徴収といいます。
しかし源泉徴収の金額はあくまで目安であり、確定した納税額ではありません。
その年のうちに扶養する家族が増えたり、学生だった子供が就職して扶養からはずれたりすることがあれば、毎月源泉徴収していた税額が違ってきます。
そのため、年末調整で当年の1月1日から12月31日までに支払われた給与所得や所得税、控除額を確認して、源泉徴収した所得税額との過不足を計算します。
源泉徴収により過払いがあれば還付し、不足があれば追加で徴収されることで正しい金額の税を納めます。
年末調整では、支払われた給与に対しての所得税の計算だけでなく、生命保険控除や扶養控除をはじめとした各種控除の精算もします。
ただし、副業の収入は勤務先が把握していないため、年末調整の対象とならない点に注意が必要です。
年末調整の対象になる人・ならない人

年末調整の対象となるのは、会社で働く正社員だけではありません。
パートやアルバイトなど正社員以外の雇用形態であっても、対象になる場合があります。
年末調整の対象になる人とならない人の条件は様々ありますが、1つは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しているかどうかです。
所得税法で、会社は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した従業員に対して、年末調整を実施しなければいけません。
つまり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していない人は年末調整の対象外です。
年末調整の対象になる人
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した上で、1ヵ所の給与額が年間2,000万円以下で、「災害被害者に対する租税の減免、 徴収猶予等に関する法律」によって災害による源泉所得税等の徴収猶予や還付を受けていなければ、原則として年末調整の対象となります。
年末調整の対象となる人の主な条件は、以下のとおりです。
- 1年間を通して勤務した、あるいは転職による採用後年末まで継続して勤務した従業員
- 死亡により退職した、または心身の障害により年の中途で退職し、本年中に再就職が見込めない従業員
- 12月中に給与を受け、その後退職した従業員
- パートタイムで働いていた従業員が退職し、本年の給与総額が103万円を超えない場合(ただし、退職後本年中に別の勤務先から給与を受け取る見込みがある場合を除きます)
- 海外の支社や子会社に年の中途で転勤することとなり、非居住者となった従業員(非居住者とは、国内に「住所」も1年以上の「居所」も有しない個人をいいます)
また、株式売買による譲渡所得や、家賃収入などによる不動産所得など給与収入以外の合計所得が20万円以上生じた場合は、年末調整を実施した場合であっても、自社の給与と給与所得以外の所得について確定申告をする必要があります。
年末調整の対象にならない人
年末調整の対象にならない人は以下のとおりです。
- 1年間の主たる給与の収入額が合計額が2,000万円を超える従業員
- 災害減免法によって源泉所得税・復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けている従業員
- 副業など2ヵ所以上の勤務先から給与収入を得ており、自社以外の勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員
- 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の従業員
- 年の中途で退職した従業員(年末調整の対象となるケースに該当しない場合)
- 非居住者
- 一定の条件を満たす日雇労働者
年の途中で転職した場合は、転職先の会社(12月31日時点で在籍)で年末調整を行います。
つまり、「転職前の会社は年末調整の対象外」、「転職後の会社は年末調整の対象」という関係になります。
また、給与所得のみであっても収入の金額が2,000万円を超える人は、年末調整の対象になりません。
副業の年末調整はどうなる?

副業の収入で、年末調整をされなかった所得が20万円を超える場合は自身で確定申告しなければなりません。
源泉徴収の義務は支払者が負っていますので、給与を支払った会社のそれぞれから源泉徴収票を発行してもらえば問題ないと思われるかもしれませんが、そうとは限りません。
副業の収入がどちらも所得税の課税対象額103万未満で所得税を徴収されていないときは、あわせた収入で所得税額を判断するため課税対象となることがあります。
その場合は確定申告して所得税を納めなければならないので注意が必要です。
それぞれの会社から源泉徴収されている場合は、確定申告することで所得税が還付される可能性もあります。
また、個人で副業をしてネットショップを運営している場合なども確定申告が必要なことがありますので注意しましょう。
収入と所得の違い
副業の年末調整・確定申告について考えるうえで、「収入」と「所得」の違いについて理解しておく必要があります。
「収入」とは、給与所得者なら源泉徴収される前のいわゆる額面金額、個人事業主(自営業、フリーランス)なら売上高の合計です。
そして「所得」とは、収入から必要経費の額を引いた金額を指します。給与所得者の場合は、経費の代わりに、給与収入の金額に応じた給与所得控除額が定められています。
例えば、ネットショップでの販売などの副業で20万円の売上があったとき、必要経費がまったくかかっていなければ所得は20万円になり、確定申告が必要です。
しかし、売上が25万円あっても経費が10万円かかっていれば、所得は15万円となり確定申告は不要です。
副業をしていても年末調整を行えるのは1ヵ所のみ
本業の会社で収入を得つつ他の会社で副業もしている場合でも、年末調整が受けられるのは1つの会社のみとなります。
年末調整を受けるためには、原則として雇用主に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があり、この書類は1人1枚と決められています。
もし2ヵ所以上で年末調整をすると、所得控除が重複してしまい正しい納税額が計算できなくなるためです。
また、年末調整は、一番多く給料を受け取っている会社で申請するのが基本です。
年末調整で提出する書類は以下のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
年末調整できない所得は確定申告を
年末調整を受けられない収入については、一定以上の金額になる場合、自分で確定申告を行う必要があります。
年末調整を受けずに放置すると、所得税の精算を行えないためです。
前述でも説明した通り、給与所得者は、毎月の給与からあらかじめ所得税が引かれています。
ただし税額はあくまでも概算であり、正しい税額は個々の事情に即した各種控除を適用するまでは分かりません。
そのため年末調整を受けられない収入については自分で確定申告を行って税額を確定し、正しく納税する必要があります。
確定申告の結果、払い過ぎた所得税があれば還付され、不足があれば納付が求められます。
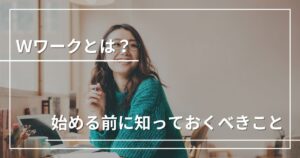
副業で確定申告をする判断ポイント

副業の収入が20万円を超える人は、年末調整の対象となる年の翌年の2月16日から3月15日までに確定申告をしなければいけません。
所得が20万円を超える副業として確定申告が必要なものには、例えば以下1~5のようなものがあります。
- 衣服・雑貨・家電などの売却による所得
- 自家用車などの貸付けによる所得
- ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
- 暗号通貨の売却等による所得
- 競馬などの公営競技の払戻金による所得
4.や5.は副業として認識していないこともあるかもしれませんが、確定申告の対象となりますので注意しましょう。
また、通常の副業は基本「雑所得」として申告しますが、事業的規模になると「事業所得」として申告することもできます。
副業の所得が事業所得と雑所得のどちらに該当するかは、原則として「その所得を得るための活動が、社会通念上、事業といえるかどうか」で判断されます。
「雑所得」か「事業所得」にするか迷っていたら、まずは帳簿付けをしておきましょう。
事業所得で申告できる場合には帳簿が必要です。
雑所得の場合には、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
2022年の国税庁による基本通達の修正案では、帳簿・書類を作成し保存していれば、本業、副業に関係なく、概ね事業所得として認められることになりました。
その所得を得るための活動が社会通念上、事業と称する程度で行っているかどうかで判定するのが原則です。
また、本業以外の所得が20万円以上あるにもかかわらず、確定申告をしないと脱税とみなされ、無申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。
申告漏れがないように自身の所得額を正確に計算しましょう。
国税庁の確定申告書等作成コーナーでは、パソコン画面で案内に沿って金額等を入力するだけで、申告書や決算書などを作成し、e-Taxによる送信ができるようになっています。
また、令和5年1月から青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成可能になり、申告が簡単・便利になっています。
副業が20万円以下でも確定申告が必要なケースも
副業の所得の合計金額が20万円以下であっても、確定申告が必要なケースがあります。
副業で給与所得や事業所得で得ている所得から所得税が源泉徴収されている場合、所得税を払いすぎていることがあるため、確定申告で還付される可能性があります。
また、副業の所得が20万円以下であっても、医療控除や初年度の住宅ローン控除など年末調整で処理できない控除を受ける人は、個人で副業所得も合わせて確定申告をしなければなりません。その場合は、20万以下でも副業で得ている分の所得も申告する必要があります。
なお確定申告をしなくてよいケースにおいても、住民税の申告は別途必要なため注意が必要です。
確定申告をしない場合、課税所得に副業所得が含まれず、住民税の正しい税額を計算できません。
住民税の申告は確定申告と同様に2月16日から3月15日までに、1月1日に住所のある市区町村の役所で行います。
2ヵ所で年末調整をしてしまった場合は?

年末調整は、1ヵ所の勤務先でしかできない決まりですが、2ヵ所以上の勤務先に年末調整の書類を提出してしまった場合のリスクや、対処法を紹介します。
控除の計算が過剰になる可能性
年末調整を複数の勤務先で行うと、各種控除が重複して適用されます。
課税所得が低く算出され、正しい所得税額を確定できません。
税額が少ないまま確定すれば、過少申告となる恐れがあります。
年末調整できるのは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先のみです。
これ以外の勤務先については、できるだけ早急に取り消しを依頼しましょう。
ただし会社が源泉徴収票の発行を完了している場合、修正はできません。
修正が間に合うかどうかの目安は、年末調整の翌年の1月31日です。会社にとって1月31日は、各種法定調書の提出期限となっています。
ほとんどの会社は、この日までに源泉徴収票の発行を終えているはずです。
間に合わなかった場合は確定申告を
年末調整の取り消しが間に合わなかった場合は、確定申告で所得税額の修正が可能です。
確定申告をせずに放置すると、課税所得額が少ないまま確定してしまう恐れがあります。
本業・副業それぞれの勤務先から受け取った源泉徴収票を用意して申告書を作成し、適切に税額の確定・納税を行うことが必要です。
なお確定申告には期限があります。
無申告のまま放置して、後に税務署から指摘を受けると、本来の所得税に加えて「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティが科される可能性があります。
年末調整の取り消しが間に合わない場合は、必ず期限内に確定申告を行いましょう。
まとめ
今回は、副業している場合に年末調整の対象になる人の条件、副業の確定申告が必要か判断するポイントについて紹介しました
- 年末調整をできるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した1ヵ所のみ
- 副業で所得20万円を超える場合は確定申告を
- 所得20万円以下でも確定申告が必要なケースもある