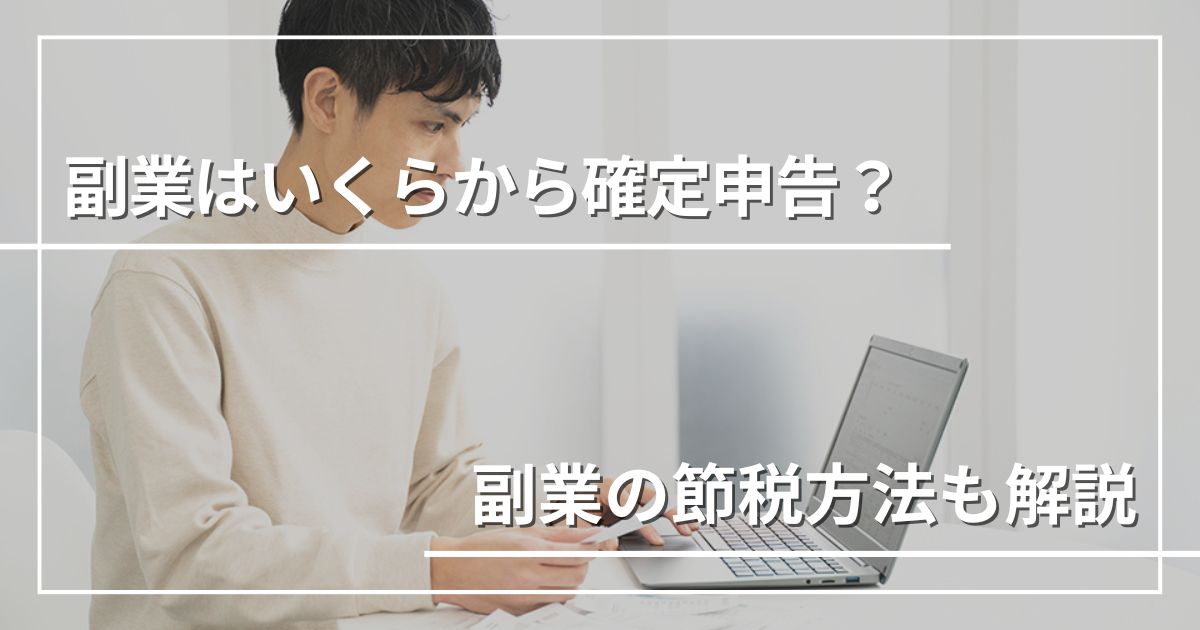現在、企業の副業解禁も進み、多くのサラリーマンが副業を検討するしていると言われています。
そこで気になるのが「いくらから確定申告が必要なのか?」という疑問や節税方法についてかと思います。
副業を始める際には、その収入が確定申告の対象になるかどうかを理解することが重要です。
今回は、副業をしている人がいくらから確定申告が必要か、サラリーマンが副業した場合の所得の種類や節税方法についてご紹介します。
副業したら確定申告が必要?

サラリーマンの副業であっても収入によって確定申告の必要性が生じるケースがあります。
副業をしている人は確定申告が必要な場合がある
確定申告は、1年間の収入から所得税の計算をし、税務署に申告する手続きです。
会社員などの給与所得者は多くの場合、勤務先で行う年末調整で所得税の納税が完了するため、確定申告をする必要がありません。
しかし、会社員で副業をしている人は、本業の勤務先で年末調整をしていても、自身で確定申告が必要になる可能性があります。
具体的には、副業所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
確定申告をする際は、まず所得の種類を知っておく必要があります。
会社員が副業した場合の主な所得の種類
所得税法上、所得は10種類に分類され、その中で副業の所得区分として多いのは以下の4つが挙げられます。
◎副業の主な所得区分
- 給与所得:アルバイトやパート雇用で得た所得
- 事業所得:事業を営んでいる人がその事業で得た所得
- 不動産所得:不動産収入で得た所得
- 雑所得:ほか9種類に分類されない所得
収入と所得の違い
副業の確定申告について考える上で、「収入」と「所得」の違いについて理解しておく必要があります。
「収入」とは、給与所得者なら源泉徴収される前のいわゆる額面金額、個人事業主(自営業、フリーランス)なら売上高の合計です。
そして「所得」とは、収入から必要経費の額を引いた金額を指します。
給与所得者の場合は、経費の代わりに給与収入の金額に応じた給与所得控除額が定められています。
副業の場合、「売上(または収入)」から「必要経費」を引いて残った額が、所得」となります。
確定申告では「所得」により所得税の計算を行います。
20万円以下でも確定申告が必要なケース

副業の収入が少額でも、確定申告が必要になる場合があります。
ここでは詳細なケースをご紹介します。
各種控除を受ける場合は必要
副業の所得が20万円以下の場合は、原則確定申告の必要はありませんが、医療費控除や住宅ローン控除を受ける際は、確定申告が必要になります。
医療費控除とは、家族の分も含めて1年間に支払った医療費が一定額を超えるとき、確定申告によって税金の一部が還付される制度です。
詳細については、国税庁のページに記載されています。
・No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁
また、住宅ローン控除とは、住宅ローン等によってマイホームの新築・取得等をした場合に、一定の要件を満たせば、一定の金額について居住を始めた年分以後の各年分の所得税額から控除するという制度です。
住宅ローン控除には多くの種類があるため、どれに該当するかは税務署等で確認されることをおすすめします。
2カ所で源泉徴収している場合は還付される可能性も
副業先が給与所得で源泉徴収されている場合は、源泉徴収票をもらったとしても「年調未済」と記載されており、通常より多くの源泉徴収がされます。
このような場合にも確定申告により還付が受けられます。
還付申告は確定申告と同じ方法で行います。
還付金は通常、申告者本人の口座に振り込まれますので、確定申告書の「還付される税金の受取場所」欄に受け取り口座を記載すると、1カ月程度で還付されます。
注意!確定申告をしなくても住民税の申告は必要
所得税の確定申告をすると、確定申告に記載された所得額をもとに、市区町村が住民税を計算して納税者に通知を行います。
そのため、所得税の申告をしないと、市区町村では納税者の住民税を正確に計算できません。
確定申告を行わない場合でも、副業で1円でも利益が出ていれば、市区町村へ毎年3月15日までに「住民税申告書」の提出が必要です。
住民税は地方税に含まれるため、自治体で納税場所が異なります。
自身の住む自治体のホームページを確認し申告漏れがないよう注意しましょう。
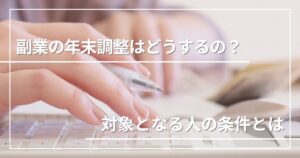
副業の雑所得と事業所得の判断
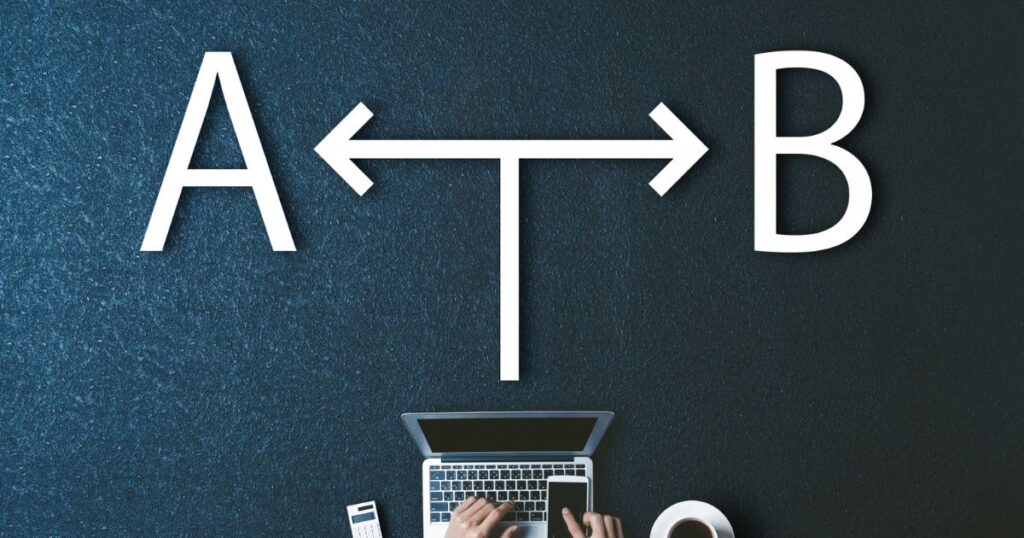
ここでは、副業の雑所得と事業所得を判断するポイントについてご説明します。
所得区分の判断
前項でも挙げたように副業での主な所得は4つあります。
例えば、副業でアルバイトやパートをして給与を得た場合は「給与所得」、アパート経営をして賃料を得た場合は「不動産所得」になります。
これら以外の、個人で行っている副業の所得は、一般的には「雑所得」または「事業所得」になります。
ただ、「雑所得と事業所得の違いがよくわからない」と悩む方もいるかもしれません。
雑所得と事業所得の判断ポイントは?
副業の所得が「雑所得」と「事業所得」のどちらに該当するかは、原則として、「その所得を得るための活動が、社会通念上、事業といえるかどうか」で判断されます。
その収入の所得区分を「雑所得」か「事業所得」にするか迷っていたら、まずは帳簿を付けておきましょう。
もし事業所得で申告できる場合には帳簿が必要となるためです。
雑所得の場合には、帳簿付けの義務はありませんが、売上や仕入・経費などの集計に帳簿がある方が便利です。
2022年の国税庁による基本通達の修正案では、帳簿・書類を作成し、保存していれば、本業、副業に関係なく、概ね事業所得として認められることになりました。
その所得を得るための活動が社会通念上、事業と称する程度で行っているかどうかで判定するのが原則です。
副業は雑所得に該当する場合が多い
前述の通り、「雑所得」か「事業所得」かは、それが事業規模であるかどうかや、独立・継続・反復して行われる仕事かどうかといった観点から総合的に判断されます。
例えば、会社員が休日に配達業務をしたり、余暇で運営しているサイトでアフィリエイト収入を得たりといったケースは、多くの場合雑所得となります。
また雑所得にあたる場合でも、事業所得と同様に必要経費を計上して申告できます。
副業で収入を得るためにかかった経費を差し引くことで所得を減らせるため、納税額を抑えられるのです。
必要経費には、オフィス(兼自宅)の光熱費、資料などに使った書籍代、打ち合わせ時の飲食代・交通費なども含まれます。
雑所得の場合でも、申告のために業務に係った必要経費の計上を忘れないようにしましょう。
確定申告から納税までの流れ
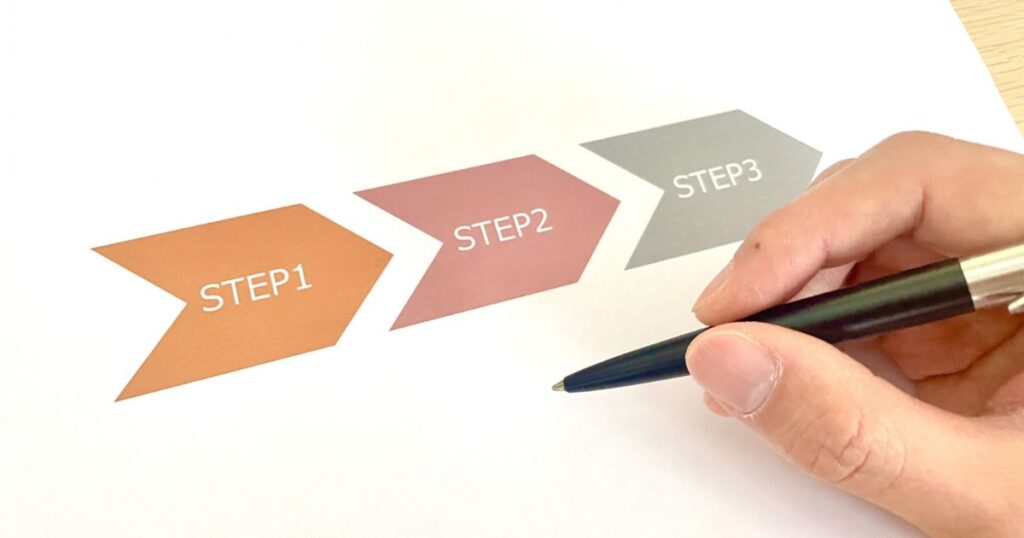
ここからは確定申告から納税までの流れを見ていきましょう。
確定申告の期間
確定申告は1月1日~12月31日までの所得を申告する手続きで、申告期間は翌年の2月~3月中旬です。
2024年は2月15日から3月15日までとなっています。
ステップ1 必要書類や帳簿の準備
まず初めに、必要書類や帳簿を揃える必要があります。
本業の収入が分かる源泉徴収票のほか、副業の収入と経費の金額が分かる書類を用意しましょう。
具体的には、下記のような書類が必要になります。
- 給与収入の分かる源泉徴収票
- 副業収入の分かる支払調書など
- 経費の領収書
- マイナンバーカード
- 金融機関の口座情報
- 保険料控除証明書、医療費控除の明細書、寄付金の受領証など
ステップ2 期間内に確定申告をする
必要な書類を揃えたら、申告書の必要書類に記載して期日内に税務署に申告します。
申告する方法には、下記のようなやり方があります。
- 税務署の窓口に提出
- 税務署へ郵送
- e-Tax(電子申告)
従来は税務署の窓口に提出する方法が一般的でしたが、最近はe-Taxが主流となっています。
青色申告をする予定の方は、電子申告することで控除額が増えるためおすすめです。
ステップ3 所得税を納める
申告が終わったら次は所得税を納めます。
支払方法は下記の中から選ぶことができます。
- 口座振替
- ダイレクト納税
- インターネットバンキング
- クレジットカード
- スマホアプリ
- コンビニ
- 金融機関窓口
口座振替は振替の手続きが必要になりますが、他の納付方法に比べると期日までに余裕があるというメリットがあります。
また、コンビニであれば24時間支払いができますし、スマホアプリであれば自宅からでも可能です。
クレジットカードは分割払いもできて便利ですが、支払い回数によっては決済手数料が必要になるため注意しましょう。
還付金を受け取れる場合もある
確定申告は所得税を納めるための手続きですが、条件によっては税金が還付される場合があります。
源泉徴収などで納めていた税金が、本来納めるべき税金よりも多かった場合は還付されます。
例えば初めて住宅ローン控除を受ける場合などが該当し、確定申告すると給与から源泉徴収されていた税金が後日還付されるでしょう。
還付される場合でも、手続きは通常の確定申告と同じになります。
意外と知らない?副業の節税方法
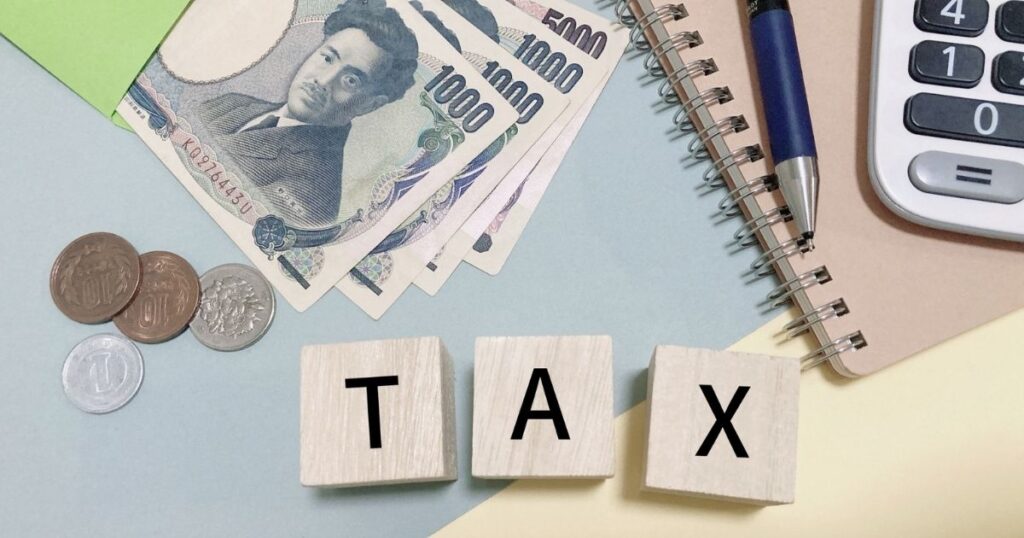
副業で節税ができる手段としては次のようなものがあります。
①経費計上をする
副業に必要な支出を経費として計上することで節税をすることができます。
副業をされている方は経費によって節税ができるため、経費について知識を深めておくことをおすすめします。
副業で経費にできるもの
①通信費
副業するために必要なスマートフォンでの電話料金やインターネット接続費などは経費として計上できる場合があります。
②交通費
副業先に通うための交通費は経費として計上できる場合があります。
例えば、電車やバスの運賃、ガソリン代、駐車料金などが該当します。
③事務用品費
副業するために使用した文房具等の事務用品の費用に関しては経費として計上できる場合があります。
④家賃・光熱費
副業を行う場所を自宅(作業場)としている場合、その作業場や事務所に相当する部分の家賃や光熱費の一部を経費にできる場合があります。
しかし、完全にプライベートな空間は経費にできません。
②青色申告を活用する
確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告を選択することで最大で65万円の控除が受けられます。
そのため、青色申告を活用することで副業をしながら節税効果を期待できます。
青色申告をするには、事前に「青色申告承認申請書」と「開業届」を提出する必要があります。
また、それぞれに提出期限があるため注意が必要です。
開業届は事業の開始等の事実があった日から1ヶ月以内に提出となっており、青色申告承認申請書は、原則として開業日から2ヶ月以内に提出することなっています。
③赤字は繰越控除や損益通算が可能
最大で3年間、今年の赤字を翌年以降の所得から差し引ける制度があります。
この制度は純損失の繰越控除といい、青色申告であれば今年の赤字を翌年の黒字から差し引き、翌年度の税金を安くすることができるというメリットがあります。
また、副業で得た所得が事業所得として扱われ赤字になると、損益通算によって本業の所得と副業の赤字分を相殺することができます。
そうすることで、本業の給与所得が減少し給与所得に対する所得税などが減額され還付を受けることができるという形です。
しかし、副業での収入が雑所得に分類されてしまう場合、損益通算を行うことができないため注意が必要です。
④少額減価償却資産の特例を利用
少額減価償却資産の特例は、青色申告をしている個人事業主や中小企業が使える制度です。
通常は10万円以上のものを購入すると、固定資産として耐用年数に応じて減価償却しなくてはなりません。
そのため、例えば20万円の固定資産を、5年の耐用年数で定額法で減価償却をすると、経費にできるのは1年間に4万円です。
一方、少額減価償却資産の特例を利用すれば、その固定資産を購入した年度に20万円全額を経費に計上できます。
つまり、少額減価償却資産の特例を使うことで早いうちに経費にでき、節税になるというわけです。
少額減価償却資産の特例を利用するために事前の申請などは必要はありません。
⑤短期前払費用の特例を利用
短期前払費用の特例を利用することで、今後事業の利益を生み出すと予測される費用を一度に経費として計上できます。
原則、前払費用は役務の提供を受けた時に経費にできます。
しかし、短期前払費用の特例では、費用を払ったときに全額経費にできるので、その年度に計上できる経費の額が大きくなり節税になります。
例えば4月~翌3月までの一年分の保険料を一括で支払った場合、原則では1月~12月までの確定申告となるため、支払った保険料の4月~12月分までが経費計上できるのに対し、特例を利用した場合は4月~翌3月までの1年分を経費計上することが可能です。
会社員の副業で、短期前払費用の特例が利用できそうな例は次の通りです。
短期前払費用の特例が利用できる例
- 保険料
- 家賃
- 駐車場代
- サーバーの利用料
- 電子版の新聞購読料
但し、短期前払費用の特例が対象となるものは限られているため、実際に利用する場合はそのサービスが短期前払費用の特例の対象となるかを確認しましょう。
確定申告や納税が遅れたら?

期日までに確定申告をしなかった場合、無申告加算税が加算されます。
無申告加算税は本来納付すべき税額の15%(納税額が50万円を超える場合は20%)と定められています。
また期日までに納税しなかった場合は、更に延滞税も課税されるでしょう。
所得税の場合は納付期限の翌日から、実際に納付した日までの利息に相当する金額が課税されます。
延滞税は納付が遅れた場合のほか、修正申告で追加納税が発生した場合や、更正または決定の処分で納付する場合にも課税されます。
また青色申告で最大65万円の控除を利用していた場合、期日に遅れると最大額の控除が受けられません。
青色申告を予定している場合は特に注意が必要です。
このようにさまざまなペナルティがあるため、期日までに納付するように気をつけましょう。
まとめ
今回は、副業をしている人がいくらから確定申告が必要か、サラリーマンが副業した場合の所得の種類や節税方法についてご紹介しました。
- 副業でも所得や控除の条件により確定申告が必要
- 副業の際は雑所得でも帳簿をつけておくと◎
- 節税を活用して副業のメリットを活かそう