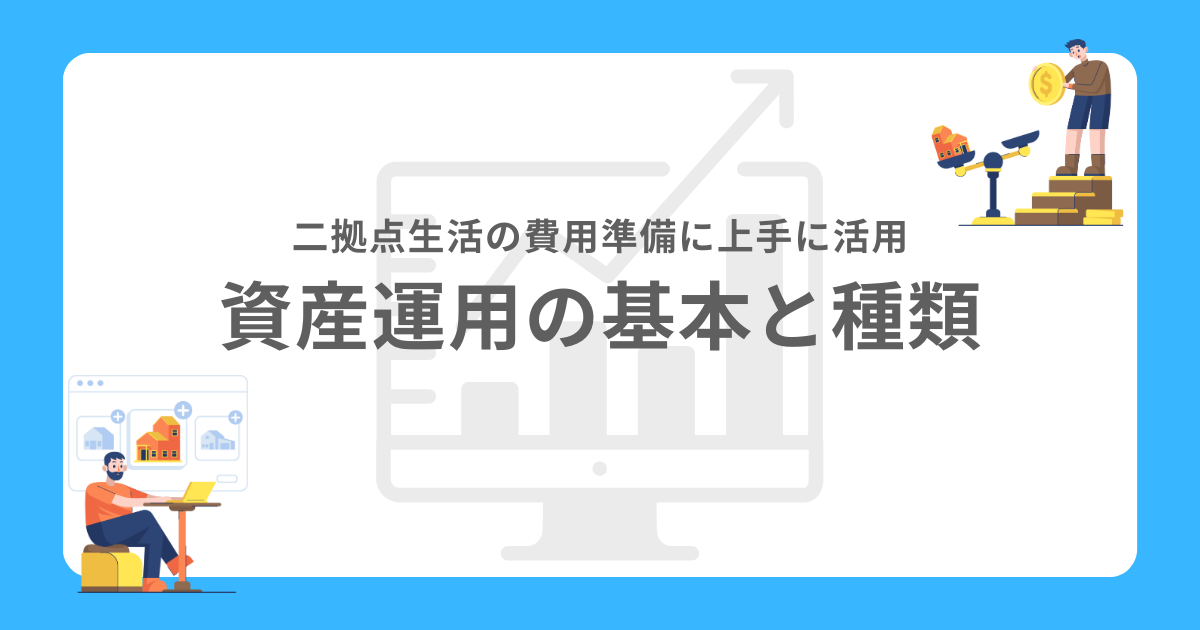「田舎と都会で二拠点生活をしたい、でも今の家計でやりくりできるか不安」
このような悩みは、二拠点生活を始めようと思っている人の誰もが持っていると思います。
結論から言いますと、二拠点生活をした場合、現在の生活費の1.5~2倍になると言われています。
そうなると富裕層しかできない贅沢のように感じられますが、二拠点生活をしている人の大半は上手にやりくりをしているという実態が見えてきます。
また、二拠点生活の費用を捻出するために上手く「資産運用」をしているという方も多いようです。
今回は二拠点生活の費用準備のために、活用している人が多いという資産運用の基本や種類について解説します。
二拠点生活をしたいと思ったら

二拠点生活者のメイン層は30代~40代となっています。
子育ても仕事も現役世代の私たちが二拠点生活をしたいと考えた時、資金よりも前に整理しておきたい項目があります。
①目的を明確にする
なんとなく「自然の中で、のんびりとリラックスできそう」というイメージで二拠点生活を始めてしまうと失敗に繋がりかねません。
二拠点生活は二つの拠点を行き来するライフスタイルですから、移動も発生しますし、生活費もかかります。
たまにのんびりしたいというだけなら旅行でもいいわけです。
例えば「夏の間は趣味のサーフィンができる場所に住みたい」、「週末は広い庭でガーデニングや家庭菜園をしたい」、「子育ては人や自然の触れ合いと大事にしたい」と、目的を明確にすることが二拠点生活において重要です。
週末のみ田舎暮らしや、本宅を田舎において平日の半分をテレワーク、もう半分を都会のアパートから出社するなど、人によってライフスタイルが変わってきます。
セカンドハウスや別荘を購入したけど最初の1~2年しか利用しなかったといったこともよく聞かれる話です。
自身の二拠点生活で実現したい生活を具体的に思い描いてみましょう。
②仕事や家族の理解を得る
二拠点生活をする上で、仕事をどうするかというのは現役世代の私たちにとって重要です。
たとえばテレワークがメインで出社の必要がないのであれば、都市部から離れた地方でも問題ありません。
しかし月に数回でも出社が必要であれば、二拠点生活の場所をある程度行き来しやすい距離にしておくのがおすすめです。
また同居する家族がいる場合、二拠点生活について理解を得ておきましょう。
たとえば旦那さん側が自分の趣味のために二拠点生活をしたいと思っていても、家族が反対するというケースもあります。
また、お子さんがいる場合は特にライフイベントや学校の行事、部活などが影響してきます。
お子さんの受験期間などとかぶってしまうと、環境の変化への対応で受験に集中できず、二拠点生活もお子さんの受験もどちらも上手くいかなかった・・・という事態に陥りかねません。
そのためお子さんのライフイベントにも考慮する必要があります。
③住みたい場所を決める
二拠点生活の目的が明確になったら、住みたい場所を決めていきます。
目的により、都会と田舎、どちらが本拠点になるかといったことも見えてくるでしょう。
住居も、購入・賃貸・シェアハウスなどさまざまな選択肢があるので、どんな生活がしたいのか、予算はどのくらいかを念頭に地域を絞りましょう。
とくに、これまで田舎で暮らしたことがないという方は注意が必要です。
住環境が整っている都会と違い、田舎など自然が豊かな環境では、家のメンテナンスや庭の手入れなどが思った以上に大変な場合があります。
また、地域によっては地元の祭りの手伝いや清掃活動、消防団の業務など地域活動への参加が必要な所もあることを覚えておきましょう。
地域の人たちとの交流は楽しいものですが、二拠点生活の場合、定住と違いなかなか参加できないこともあるでしょう。
あまり交流がない地域が希望であれば、移住者の多い地域や、定住者が少ない別荘地もおすすめです。
④資金計画
住みたい場所を決める段階とほぼ同時期にはなりますが、資金の計画や準備もしましょう。
二拠点生活で一番かかるのは住宅に関する初期費用となります。
更に、実際に住み始めてからも生活費がかかるため、ある程度の資金準備や先々の収支について計画しておく必要があります。
二拠点生活をするにはどの程度の費用がかかるのか試算しておいた方が、生活のイメージをつかみやすくなるでしょう。
現在の住まいをセカンドとして、二拠点先を本宅にする場合はお子さんの保育費や教育費用についても算出しなおしましょう。
地域によって教育にかかる費用が大きく違う場合があるためです。
二拠点生活にかかる費用は?

それでは二拠点生活にかかる費用を見ていきましょう。
生活費はほぼ2倍
①初期費用
家を建てるなら土地・建物の取得費用、借りる場合は賃貸の契約費用がかかります。
その他、荷物を運ぶ「運搬費」や生活を始めるの「家具・家電」が必要となってきます。
家族構成により金額の幅はありますが、引越し1回分の費用を見積もっておくと良いでしょう。
②移動交通費
それぞれの拠点を移動するためには、移動交通費がかかります。
現在の住まいから距離のある地域で二拠点生活を始めたいと思った場合、移動のたびに新幹線代や飛行機代がかかってきます。
毎週のように長い距離を移動するなら、交通費やガソリン代だけでかなりの金額になりますので、こちらも考慮しておく必要があります。
③光熱費・生活費
それぞれの拠点での光熱費、食費、日用品費などの生活費もかかります。
都会と田舎の違いとして、インフラの差による光熱費の違いがあります。
都会には都市ガスがありますが、地方はほとんどの場合プロパンガスになるため費用は倍になることも。
また汚水処理についても、都会のほとんどは下水道が設置されていますが、田舎は汲み取りや浄化槽であることからランニングコストが高くなる場合があります。
食費・日用品なども1.5倍ほどになると考えられますから、生活コストが増えることも考慮しながら二拠点生活を始める必要があります。
富裕層にしかできないもの、ではない
ここまで二拠点生活にかかる費用をお伝えしました。
想像よりもかかりそう、、、と思われたかもしれませんが、実際に二拠点生活をしている人の世帯年収についての調査がありますので、ご紹介します。
国土交通省の2024年発表によると、二拠点生活をしている人の世帯年収は400万円~600万円が20.5%とボリュームゾーンであり、そこを含めた200万円~800万円が全体の半数を占めています。
以前の二拠点生活イメージは、富裕層が別荘を購入し、定年退職後に悠々自適な生活を送るというものでしたが、現在では二拠点生活のメイン層は20~40代・世帯年収は400万円~600万円となっています。
意外と皆さん費用をかけずに生活されていると思いませんか?
[参考]国土交通省「移住・二地域居住等促進専門委員会中間とりまとめ(令和6年)」
資金準備をするには資産運用、の前に

とは言え、二拠点生活を始めるとなると、やはりお金が必要になってきます。
特に住まいを購入しようと考えている場合は初期費用がかかってくるため、ある程度資金を用意しておきたいという人がほとんどかと思います。
そこで上手く資産運用を活用して資金準備を行う前に、まずは知っておきたい基本についてお伝えしたいと思います。
まずは家計管理
資産運用と聞くと「まずは投資」と思われる方が多いのですが、最初のステップは家計管理です。
家計管理をきちんとすることは、入ってくるお金と出ていくお金をきちんと把握し、収支を黒字にすることで貯蓄や投資に回すことができるということになります。
「毎月の生活がギリギリ・・・」、「お金に余裕があるとつい使ってしまって貯蓄に回せない」という人はまず家計管理から始めましょう。
例えば、毎月の給料日に一定の金額を自動で貯蓄用の口座に移しておくなど、先に貯蓄に回し、残りのお金の範囲内で家計をやりくりできるようにしましょう。
家計を見直すことで現在、貯蓄できている人も更に増額できる可能性があります。
もちろん本業での評価を上げる、副業をするなどで収入を増やすという手もあります。
資産運用の基本は「分散」
資産形成をするには資産を分散して運用するのが基本です。
①リスクを分散
資産運用方法は様々ありますが、その種類を1つだけに絞って運用するのはおすすめできません。
例えば、銀行の普通預金では現在の金利はかなり低いため、収益性がなく目標額に到達するまでかなり時間がかかってしまいます。
そのため、目標額や時期にあわせて株式や投資信託などの金融商品を上手に活用しながら、運用すると良いでしょう。
しかし、金融商品は元本割れのリスクがあり、資産運用の全てをリスクの高い金融商品にしてしまうと、大きな損失につながることもあるため注意が必要です。
そのため、資産運用方法は複数組み合わせてリスクを分散することが重要です。
株式相場の世界では、「卵は一つのカゴに盛るな」という言葉があります。
卵を一つのカゴに盛ると、そのカゴを落とした場合に全ての卵が割れてしまう可能性があるが、複数のカゴに分けておけば、そのうちの一つのカゴを落として卵が割れてしまったとしても、他のカゴの卵は影響を受けずにすむ、ということを指しています。
つまり、特定の商品だけに投資をするのではなく、複数の商品に投資を行い、リスクを分散させた方がよいという教えです。
②時間を分散
投資は安値で買って、高値で売ることで利益を得るものと思われがちです。
しかし、将来の値動きを見極めて売買するのは投資のプロでも難しく、会社勤めの方がデイトレーダーのように日々の値動きを追い続けるのははっきり言って無理があります。
そうした場合に有効なのが「ドル・コスト平均法」です。
ドル・コスト平均法とは、価格が変動する商品に対して「一定金額を、定期的に」購入する方法を指します。
投資する金額を一定にすることで、価格が低いときは購入口数を多く購入し、価格が高いときには購入口数を少なく購入することで、平均購入単価を抑えることが期待できます。
この方法は定期的に購入するため手間がかからず、日々の相場を気にする必要がありません。
短期的に大きなリターンを目指すには不向きですが、大幅な価格変動に影響されにくいというメリットがあります。
資産運用の種類

前項では、資産形成の基本としてリスクや時間の分散についてご説明しました。
ここでは資産の分散先である金融商品の種類についてご説明します。
元本割れなどの危険が少ない「安全性」、必要なときに現金化しやすい「流動性」、運用することで得られる「収益性」の観点から、自分の目標額やいつまでに実現したいか、に応じて組みあわせると良いでしょう。
預貯金
資金を作ろうと考えた時、一番最初に思い浮かぶのが預貯金です。
預貯金は銀行や信用金庫に預け、利息を受け取る方法で、資産運用を行っている人でも、まずは元本割れのしない預貯金である程度、余剰資金を作ってから運用を始める人がほとんどです。
メリットとしては、必要な時に引き出すことができるため、資金の流動性が高いこと。
そして1金融機関、1人の預金者につき元本1,000万円とその利息が保証されることが挙げられます。
しかし、以前は資産運用のメインだった「定期預金」や「積立預金」も現在では利息が低く、普通預金とほぼ変わらないため、収益性としての効果は低いと言えます。
外貨預金
外貨預金は米ドルやユーロなど外国の通貨で預金する方法です。
外貨預金と国内の預金との大きな違いは、利息だけでなく、預入時と払戻時の「為替レート」=「円と外貨の両替の価格」によって為替差益を得ることができるという点です。
更にメリットとして、外貨預金は日本円での預金に比べ金利が高い傾向があり、収益性が期待できます。
しかし、通貨を交換する際に為替手数料がかかることや、為替レートの変動による元本割れの発生リスク、そして預金保険制度の対象外のため、銀行の倒産リスクがあるということに注意が必要です。
株式投資
株式投資とは、企業が資金調達のためなどに発行する株式を買い、購入価格と売却価格の差額により利益を得る方法です。
他の金融商品と大きく異なる点は、株式の購入者は株主となり、保有する株式の数に応じた優待や配当金、株主総会における議決権などのさまざまな権利が得られることです。
メリットとしては、保有する企業の株式によっては大きなリターンを得られる可能性があります。
その反面、企業の業績悪化や社会情勢、市場動向等の要因により株価が下がるリスクがあります。
更に保有する株式の企業が倒産した場合には、株式の価値がなくなるリスクもあります。
大きなリターンを狙いたいという人の他に、企業の優待を受けたい、応援したい企業があるという人に向いている商品と言えます。
投資信託
銀行や証券会社などの運用会社に運用を任せてさまざまな対象に投資し、収益を得る方法です。
分散投資の代名詞と言える金融商品です。
メリットとしては、少額から投資が始められることと、運用自体は運用のプロに任せられるという安心があります。
対してデメリットは、購入手数料や運用管理費用(信託報酬)など、各種手数料がかかる場合があることと、投資対象は国内外の株式の他、債券など多岐に渡るため、市場の値動きにより元本割れのリスクがあることです。
自身で投資する株式などの商品を選ぶのが難しいという場合は、投資信託の商品から選択するという方法も良いかと思います。
債券投資
債券とは、国や地方公共団体、民間企業などが発行している借用証書のようなもので、保有期間中の利子と、満期日を迎えれば額面金額を受け取るという投資です。
利子を受け取る他に、額面金額より債券価格が安い時に購入し「差益を受け取る」、反対に額面金額より債券価格が高い時に売却し「売却益を受け取る」という方法もあります。
メリットとしては、他の金融商品より比較的にリスクが低いということと、定期的な利子や満期に額面金額が受け取れるため、スケジュールが立てやすいという点があります。
しかし、デメリットが全くないわけではなく、発行元が破綻した場合、利息や償還金の支払いが滞るリスクがあるということも覚えておきましょう。
FX(外国為替証拠金取引)
FX(外国為替証拠金取引)とは、ある国の通貨を別の国の通貨に交換するという意味です。
他国間で通貨を両替し、差益を得る仕組みという方がわかりやすいかもしれません。
例えば、アメリカに旅行する時に、30万円を1ドル150円のときに交換すると、2,000ドルと交換できます。
しかし1ドル120円のときに交換すると、2,500ドルと交換できるため、500ドル多く交換できますよね。
このように、為替レートが期待した方向に変動したタイミングで両替できれば、「為替差益」という利益が得られるというわけです。
ただし、FX取引では実際の通貨の受け渡しはせず、売買によって確定した損益だけを受け渡す「差金決済」と言う仕組みで取引を行います。
FXの特徴でありメリットとしては、レバレッジをかけて取引ができるという点です。
レバレッジとは少ない資金で、大きな金額の取引ができる仕組みです。
例えば1ドル150円のときに米ドルを10,000ドル購入するには、本来150万円が必要となります。
しかしレバレッジ25倍で取引する場合、25分の1にあたる6万円で、米ドル10,000ドル購入できることになります。
そのため、少ない資金で大きなリターンが期待できます。
ただし、さまざまな要因で期待とは反対の値動きとなった場合の損失リスクもあります。
レバレッジをかけて取引をしている場合は、為替レートが急激に変動した際に更に大幅な損失となる場合もあります。
そして損失となった際の最大の注意点は、ロスカットです。
FXによる損失などにより、FX口座に預け入れた証拠金が一定の証拠金維持率を下回った場合、保持しているポジションを自動的に清算するという仕組みをロスカットと言います。
ロスカットは損失の拡大を防ぐための役割でもありますが、自分の意図しないところで強制的に損失が確定することにもなるため十分に注意が必要です。
不動産投資
不動産投資は、アポートやマンションなどの不動産物件を取得し、家賃収入を得る方法です。
株やFXなどの投資とは違い、入居者が定着することで長期的に安定した収益が見込めるというメリットがあります。
ワンルームや1人暮らし向けの区分マンション経営であれば、比較的少ない費用から始められるということで会社員でも投資をされている方が多くいます。
しかし1室管理の場合、空室になった際のリスクが大きく、更に1棟経営に比べると運用利回りは低い傾向にあります。
本記事は、二拠点生活をするための資金作りの運用方法として紹介しているため、初期の投資費用が高い傾向にある「不動産投資から始めよう!」という方はあまりいらっしゃらないと思いますが、二拠点生活を機に自宅マンションを賃貸に出すというのも1つの資産運用の方法になるかと思います。
二拠点生活をするにはやりくりが大事

今回、二拠点生活をする上では家計の見直しや資産形成が大切だということをお伝えしました。
様々な金融商品を組合わせて資産運用をすることで、二拠点生活の住まいを購入する資金や、二拠点生活を楽しむための資金に充てることができます。
もちろん家計を見直す中で、今までの生活で使っていた支出を我慢をする部分も出てくるかもしれません。
必ずしも自宅と同じ快適さでなくてもいい
二拠点生活は別荘や旅行の「非日常」とは違い、「日常生活の延長線上」であることが大半です。
そうなると2つの拠点共に同じ部屋数に、同じ家電・家具が必要かというと、同じでなくても良いと思います。
少しの不便さを楽しむのも二拠点生活の1つということで、家電を揃えずに鍋でご飯を炊いているという方もいらっしゃいますし、自宅では各自の部屋でベッドで寝ているというご家族も、二拠点先では1部屋に布団を並べて寝ているという話も聞きます。
そういった日常でありながらも2つの拠点の違いを楽しむという点で全ての環境を同じにする必要もないのかもしれません。
とは言え、旅行気分での散財に注意
日常生活の延長線上に二拠点生活があるとは言っても、普段と違う環境で過ごすとついついお財布の紐も緩みがちになります。
その地域にしかない名産やアクティビティを楽しむことは、二拠点生活の醍醐味ですし是非ともおすすめしたい部分ではあります。
しかし、訪れる度に散財していては長い目で見た時に二拠点生活が立ち行かなくなりかねません。
二拠点生活の毎月の予算を立てておき、楽しみながらも予算の範囲内におさまるようにしたいですね。
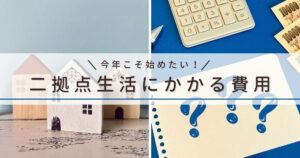
まとめ
今回は二拠点生活をするための、資産運用の基本や種類について解説しました。
- 資産運用の基本は「分散投資」
- 資産運用の金融商品にはそれぞれメリットとデメリットがある
- 目標額や自身にあった金融商品を選択して、二拠点生活の準備をしよう