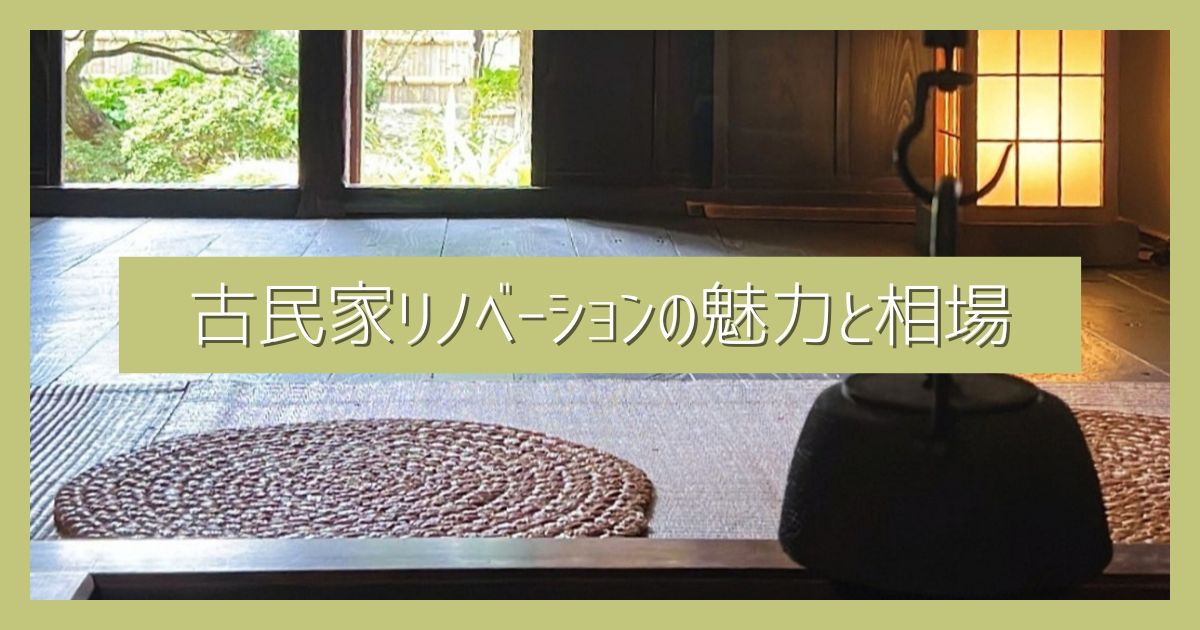地方移住や二拠点生活の住まい選びで、古民家をリノベーションして暮らしてみたい!」と考えている方もいるのではないでしょうか。
古民家には独特の趣があり、近年住まいにこだわる方からの人気が高まっています。
しかし、古民家のリノベーションに興味があるものの、デメリットや費用が気になる方も多いでしょう。
今回は、古民家リノベーションの魅力や抑えておきたいポイント、費用相場などを解説します。
古民家とは築何年から?

古民家とは、築50年を経過する木造軸組構法の伝統構法、または在来工法の住宅とされていますが、一般社団法人全国古民家再生協会での「古民家」の定義は、昭和25年の建築基準法の制定時に既に建てられていた「伝統的建造物の住宅」すなわち伝統構法としています。
柱や梁に「仕口」や「継手」といった凹凸を彫り、釘を使わずに組み合わせて構造体を作る「伝統構法」が用いられているほか、基礎がなく石を土台として建てられているケースもあります。
歴史のある武家民家や庄屋屋敷、農村民家などが代表的な建物ですが、古材を再利用した「古民家風の家」もよく見られます。
また、近年は、古民家カフェや民泊の運営など、古民家のさまざまな活用方法に注目が集まり、人気が高まっています。
古民家リノベーションの種類

古民家のリノベーションには、4種類あり、詳しくは以下の通りです。
一般的なリノベーション
古民家の一般的なリノベーションでは、水回りなどの設備の入れ替えや、外壁や屋根、床などの補修を中心に行います。
柱や梁など、建物の構造部分は基本的に変更しません。
劣化が目立つ部分に手を加え、快適に住めるようにします。
古民家の雰囲気をほぼそのまま残せるので、和風の一軒家に憧れがある方におすすめです。
半解体再生リノベーション
半解体再生リノベーションでは、屋根や壁、床を撤去し、柱や梁などの構造部分を補修・補強します。
古民家の良さを残しつつ、建物を補強したい場合によく用いられる方法です。
スケルトン解体と呼ばれることもあります。
構造を補修するため、土台が傾いている場合や、床に凹凸がある場合は改善が必要です。
長く安全に住めるよう、補修や補強に使う素材は新しく丈夫なものを使います。
全解体再生リノベーション
全解体再生リノベーションとは、古民家を一度解体し、柱や梁などの部材を洗ってから再利用する方法です。
傷んでいる部材があれば補強したり、新しい部材に交換したりします。
部材の多くを再利用するため、古民家の温もりを残したままリノベーションができます。
ただし、古い部材だけでは耐震性に不安が残るので、最新の耐震性の高い部材も取り入れると良いでしょう。
移築再生リノベーション
移築再生リノベーションは、古民家の場所を移動した上でリノベーションを実施する工法です。
気に入った古民家を理想の場所でリノベーションできる点が最大のメリットといえます。
また建物の基礎を新しくするため、強度を高めることも可能です。
ただし、解体や運搬などにコストがかかるため、費用は3,000万円から4,000万円程度かかります。
古民家リノベーションの魅力

古民家のリノベーションにはどのような魅力があるのでしょうか。ここでは、古民家をリノベーションする際のメリットをご紹介します。
①古民家ならではの趣
現代の住宅は基本的に工場で生産・加工された資材を使って建てますが、古民家には良質な木材や石などの天然素材が贅沢に使用されています。
元の木の姿がそのまま分かるような太い柱や梁は重厚感があります。
風情を感じられる梁などの木材を残しつつ、劣化した部分を改修して新しい設備を導入すれば、暮らしやすく趣のある素敵な住居を目指せます。
また、畳や障子、土壁といった古き良き「和」の心を感じさせるモノに囲まれて暮らせることが、古民家リノベーションの最大の魅力です。
流行に左右されず、日本の伝統的な建築の普遍的な魅力があるのも、古民家の良い点といえるでしょう。
日本家屋ならではの趣を感じられる家にしたい場合は、梁や柱といった木材のほか、吹き抜けや土間なども有効活用したリノベーションがおすすめです。
②自然と共生する暮らし
古民家は縁側や土間などの、屋外と屋内の中間のような場が設けられています。
縁側で四季によって姿を変える自然をながめたり、庭で靴が汚れたら土間でさっと洗い流したりと、現代の高気密な住宅とは違い、自然と共生した暮らしができる点が魅力でしょう。
家の広さや敷地のスペースにも余裕があり、自然を意識して建てられた古民家だからこそ実現できる暮らし方は都会の喧騒から離れて穏やかに過ごしたい方におすすめと言えるでしょう。
③地域活性化や建築物の保護
築50年や100年を超える古民家の中には、壊れた部分の補修や増築を繰り返しながら大切に受け継がれてきた家もあります。
しかし、引き継ぐ人がいなかったりで空き家になってしまうと、急速に建物の劣化が進んでしまいます。
このような建物の中には希少価値の高い建材が使われていることも多く、さらには文化財になっていることもあるため、資源などの保護に貢献できるメリットもあります。
また、古民家は空き家問題と通じる部分が多く、過疎化が進んでいる地域の古民家をリノベーションして活用すれば、地域活性化につながります。
リノベーションでバランスよく「今の時代」に合わせてつくり変えることが、結果として古民家の歴史やその地域守ることにつながります。
④固定資産税の軽減
古民家は、固定資産税や補助金などの面でもメリットがあります。
固定資産税は「固定資産税評価額×1.4%」の計算式で算出され、固定資産税評価額は、建物の築年数に応じて減額されます。
木造の建物の場合、おおよそ築25年で最低水準の補正率0.2まで補正されるため、古民家の場合、固定資産税が軽減できる可能性が高いです。
ただし、古民家の機能や耐久性が大幅に上がるリノベーションを行うと、新築に近い資産価値があるとみなされて固定資産税が高額になることもあります。
固定資産の評価額に関する基準は自治体によって異なるため、事前に自治体の窓口でリノベーション計画について相談してみることをおすすめします。
失敗したくない!古民家リノベーションのポイント

つづいて、古民家をリノベーションする際のポイントをご紹介します。
①余裕を持った予算設計をする
古民家リノベーションに限った話ではありませんが、実際に施工を開始してから新たに修繕すべき箇所が見つかることもあります。
そのため、余裕を持った予算設計が望ましいでしょう。
とくに築年数が経っている古民家では、図面がないケースも多く、耐震性や断熱性が事前にわからないと予算オーバーの可能性も高まります。
②住宅診断を受ける
古民家をリノベーションする際は、事前に住宅診断を受けておくと良いでしょう。
住宅診断では、住まいの外部だけでなく内部の状態までチェックし、改修が必要な部分や、劣化状況などを調べてもらえます。
新たに古民家を購入する場合は、住宅診断を受けることで、購入を避けるべき住まいを買うリスクを減らせます。
③耐震・断熱工事を行う
住宅診断で耐震性に問題が見つかった場合、耐震補強工事を行う必要があります。
住宅診断の結果によっては大規模な工事になることがありますが、安全性を考えると優先的に行ったほうが良いでしょう。
古民家は断熱性に劣ることも多いため、後から施工するのが困難な断熱工事も先に行うのがおすすめです。
④間取り変更と水まわりは同時に
古民家の水まわりは使いにくく、リノベーションするケースが多い箇所です。掃除が大変なタイル張りの在来浴室や、足腰に負担が大きい和式トイレなどは、新しいものに交換した方が良いでしょう。
また、配管などが古くなっている場合もあるため、リノベーションで新しくしておくのがおすすめです。
配管の劣化は水漏れにつながりますので、優先度の高い工事と言えるでしょう。
間取り変更を考えている場合は、配管などの位置もかかわってくるため、同時に検討すると良いです。
⑤補助金や減税制度が利用できるか確認
古民家をリノベーションする際は、補助金を提供してくれる自治体も存在します。
主な補助金の対象工事としては、「耐震」「介護」「省エネ」の3つがあります。
特に古民家の場合、1981年の耐震基準の改正前に建てられた建物となることが多いため、耐震性能を向上させる工事をするケースが多いと思います。
そういった工事を行う場合は補助金が利用できるか確認すると良いでしょう。
そのほか、断熱工事やオール電化などの省エネ関係の補助金も多数ありますので、自治体に詳細を確認してみてください。
古民家リノベーションの費用の相場

古民家リノベーションは、水まわりや内装の交換のほか、耐震・断熱などの性能面の向上や間取り変更、基礎の補強など、大規模な工事になります。
特に古民家は、耐震や断熱などの性能面が現在の基準を満たしていないことが多く、旧耐震基準の建物を、現在の耐震基準まで引き上げるためには、150万円~200万円ほど予算をみておく必要があります。
また、断熱材がまったく入っていない古民家の断熱性能を、快適に暮らせる程度まで向上させるためには、300万円程度の予算が必要です。
他にも間取りの変更や水回りの交換など、古民家リノベーションは工事箇所が多く、規模も大きいため高額になる傾向があります。
- 一般的なリノベーション:300万円〜2,000万円程度
- 半解体再生リノベーション:2,000万円程度
- 全解体再生リノベーション:2,000万円〜3,000万円程度
- 移築再生リノベーション:3,000万円〜4,000万円程度
個別に少しずつ改修するよりも、できるだけまとめて工事を進めたほうが割安になります。
予算が限られている方は、外壁・屋根などの外まわりの改修や断熱改修を優先すると良いでしょう。
外まわりの断熱・防水処理を強化すると家が長持ちし、さらにエアコン効率がよくなることで電気代の削減にもつながります。
古民家リノベーションで費用を抑えるポイント

できるだけ費用を抑えてリノベーションしたいという方に、費用を抑えるポイントをご紹介します。
良好な状態の古民家を選ぶ
当然ですが、古民家の修繕箇所が少ないほど、リノベーション費用は安くなります。特に、屋根や骨組みの状態が良好でそのまま使える場合は大幅に費用を削減できるため、物件を選ぶ際に以下のポイントをチェックしてみてください。
- 屋根や天井に雨漏りの跡がないか
- 柱や基礎にシロアリ被害の跡がないか
- 土台の木材が腐っていないか
- 見た目で分かるほど柱や床が傾いていないか
- 室内や床下がカビ臭くないか
なお、家の状態は単純に古さで決まるわけではありません。築年数が浅い物件でも状態が悪いケースもあるため、気になる物件があれば必ず内覧や住宅診断してから決めましょう。
自身で部分的にDIYをする
リノベーション会社に工事を依頼する範囲が少ないほど、費用を抑えられる傾向があります。
初めに必要最低限の部分だけをリノベーションして、住みながら少しずつDIYで変えていくのもいいでしょう。
古民家の状態が良く、実務経験がある方やDIYに慣れている方が作業するのであれば工事費用を約300万円〜700万円に抑えることも可能です。
- クロスやフローリングの張り替え
- 室内の壁の塗装
- 建具のリメイク、など
- 建物の骨組みの解体・改修
- 屋根や外壁の改修
- 配管・配線作業
上記の通り、骨組みの解体や高所での作業は専門知識や技術がない方が行うと大変危険なため、DIYするのはおすすめできません。
また、電気工事ができるのは、法律で有資格者のみと規定されています。
DIYで古民家をリノベーションしたい方も、まずは専門家に相談し、できる範囲を確認することから始めましょう。
リノベーション補助金を利用する
古民家リノベーションには補助金が利用できる場合があります。
断熱のエコ・省エネ繋がる工事や耐震リノベーション等は補助金を出している自治体が多く、補助金事業によっては最大100万円や200万円といったまとまった金額を受け取れる場合もあります。
なお、補助金を利用するには、基本的に契約前や工事を始める前に申請する必要があります。
リノベーションを依頼する工務店や建築家が決まったら、早い段階で補助金を利用したいことを伝えておくとよいでしょう。
まとめ
今回は、古民家リノベーションの魅力や抑えておきたいポイント、費用相場などを解説しました。
- 古民家の魅力は趣のある建物と自然と共生する暮らし
- リノベーションは耐震・耐熱や水回りを優先すると良い
- 余裕を持った費用計画とリノベーション補助金を事前に確認しよう

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!