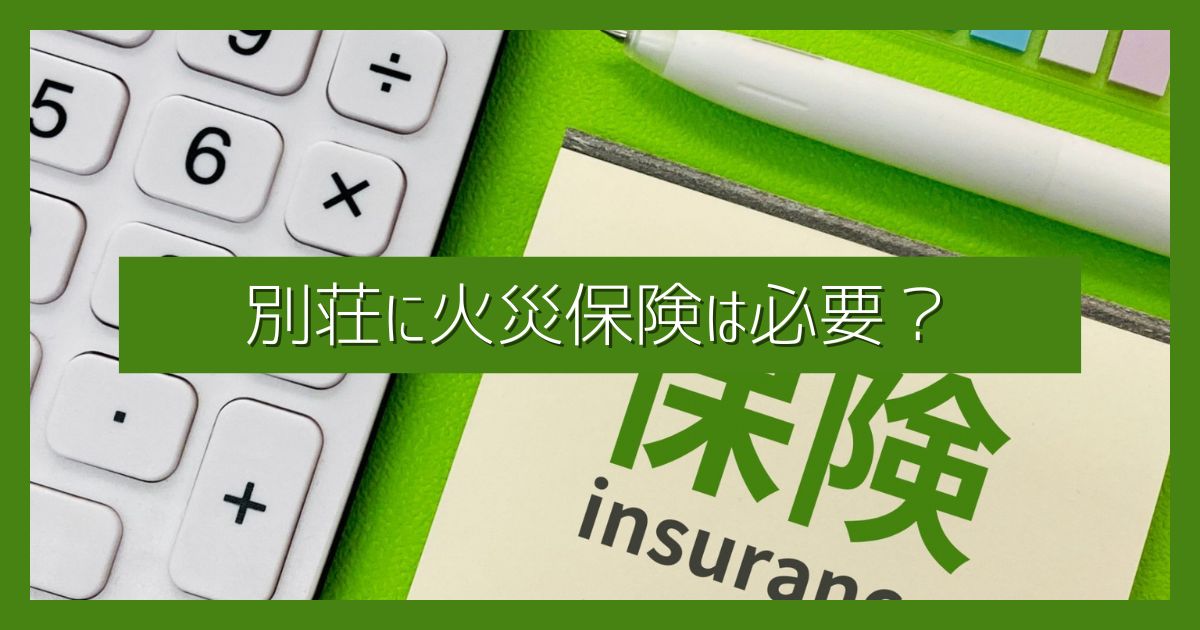加入率が低いといわれる別荘の火災保険加入率。
「別荘に火災保険って必要?」
「年に数回しか行っていないし・・・」
別荘は1年の大半が空き家になることがほとんどでしょう。
誰も住んでいない家に保険料を払い続けるのは、もったいなく感じるのが正直なところだと思います。
しかし、別荘も自宅同様に火事や自然災害に合えば被害を受けます。
かえって、あまり行く機会がない別荘ほど、被害が大きくなるリスクが高くなります。
今回は、別荘やセカンドハウス火災保険について必要な理由や、保険選びのポイントをご紹介します。
火災保険は義務ではない

実は火災保険は、自動車の自賠責保険のように法律で加入が義務づけられている強制保険ではなく、加入するかしないかは個人が自由に決められる任意保険となります。
しかし、賃貸物件でも持ち家でも、多くの場合は火災保険の加入が必要です。
賃貸の場合、建物の火災保険には貸主である大家さんが加入していますが、建物内部の損害については入居者に損害賠償責任が生じます。
そのため、賃貸契約をする際には多くの不動産会社から火災保険の加入を求められます。
持ち家の場合、住宅ローンを組む際にはほとんどの金融機関で火災保険の加入を必須の条件としています。
その理由は、火災で住宅を失った際に住宅ローンだけが残り、融資したお金を回収できなくなる可能性があるからです。
しかし別荘やセカンドハウスの場合、住宅ローンを使えないケースも多く保険加入を後押しするものがないため加入率が低いという現状があります。
別荘の保険加入率が低い理由

別荘の火災保険加入率が低い理由には、以下のようなことが考えられるでしょう。
①住んでいるわけではないので保険料がもったいない
火災保険は年単位の契約となります。
通常の住宅のように、常時使っているものと比べると、別荘に同じ内容で火災保険をかけると、気持ちとしては割高に感じてしまうものでしょう。
②一般向け扱いになると火災保険料が高くなる
保険料についても、住宅としての加入が認められず、一般向けとなった場合には火災保険料が高くなってしまいます。
いつ使うかも分からない別荘に対して、高い保険料をかけたくないと感じる方は多いのではないでしょうか。
③万が一なくなっても生活に大きな影響が及ばない
いつも住んでいる住宅が消失してしまったら、生活の拠点が失われてしまうため大問題ですが、一方、万が一火災に遭って別荘が消失してしまったとしても、生活に困るというわけではありません。
④住宅ローンのように火災保険加入を後押しするものがない
住宅の場合は住宅ローンを使って購入することがほとんどでしょうから、本人の意思と関わらず加入しなければならないという事情もあります。
もしかしたら、通常の住宅でも住宅ローンで火災保険加入を必須としていなければ、もう少し火災保険への加入率は低くなるかもしれません。
別荘に火災保険は必要?

1年の大半が空き家状態になるとは言え、火事や自然災害に合えば当然、大きな被害を受けます。
そういったことから別荘・セカンドハウスでも火災保険は加入した方が良いと言えるでしょう。
別荘は火事になりやすい
別荘なら火を使うことが少ないので、火事になる危険性は低いと思われがちです。
そのため、「別荘に火災保険はもったいない」と考える人も多くいます。
しかし別荘は普通の住宅よりも、火事になる可能性が高いです。
たとえば放火犯が狙うのは、チラシがポストからあふれている空き家だったりします。
空き家なら人に見つかる可能性が低く、火をつけやすいもの(チラシ等)がそこにあるためです。
また管理が行き届いていない場合、ガス漏れや配線器具のトラブルなどで火が出ることもあるでしょう。
自身が気をつけていても近所からもらい火で、火事になる可能性もあります。
人が住んでいないと火事や災害の発見が遅れるので、被害も大きくなりがちです。
そのため別荘は火事が起こりやすいだけでなく、その被害額も高くなる傾向があります。
別荘は災害や盗難に弱い
さらに別荘は空気が入れ替わらないので、カビなどが発生しやすく傷みやすいという欠点があります。
建物が傷んでいると台風や大雪などの自然災害で、傷んだ箇所から壊れやすくなったりもします。
また不在がちな別荘は不法侵入のリスクも高く、盗難事件も起こりやすいです。
侵入の際には窓ガラスなどが割られたりなど、家の破損にもつながります。
火災保険はその名前から、火事だけにしか使えないと考えられがちですが・・・
しかし契約によっては、自然災害・盗難・破損などで被害を受けた場合でも補償があります。
一般的な火災保険の補償内容は、火災のほか、風災・水災・盗難・水漏れ・破損など様々なリスクに対応しているものが多くあります。
利用頻度が少ないとはいえ、別荘も自宅同様火事や自然災害に合えば、当然被害を受けます。
そのような損害にも備えて、火災保険は別荘でも加入しておいたほうが得策です。
別荘の火災保険の種類

別荘にかけられる火災保険は、別荘の使い方で加入できる保険の種類が異なります。
使い方によって、火災保険の“物件種別”が決まり、加入できる火災保険が制限されるからです。
火災保険では、居住物件を「住宅物件」と「一般物件」に分類します。
住宅物件
専用住宅物件とは、居住の目的で建てられた住宅で、店舗、作業場、事務所などに使用する部分がない住宅となり、季節的に居住として使用される別荘も住宅物件として住宅用の火災保険に契約することができます。
住宅物件として扱われる場合、住宅火災保険や住宅総合保険で火災保険契約を行う事ができます。
ただし、1年の大半が空き家となる事の多い別荘の場合、住宅物件用の火災保険に加入できない保険会社も多くあります。
一般物件
一般物件は、店舗や事務所が該当となり、空き家となっている期間が長い別荘は居住用の建物とみなされず店舗や事務所と同じ一般物件として火災保険に契約することになります。
その場合は、住宅物件より保険料が高くなってしまいます。
空き家を引受していない保険会社や共済もありますが、最近では、別荘向けの火災保険もあるようです。
別荘に火災保険契約を検討している場合は保険会社や代理店に相談してみるとよいでしょう。
特約や地震保険は必要?

日頃から家の状態を観察できる自宅とは異なり、年に何度かの訪問になりがちな別荘では、台風や大雪などの自然災害に見舞われた際のアフターフォローが迅速におこなえない傾向にあります。
また、空き家になっている期間が長いため、不法侵入や盗難も起こりやすい状況です。
侵入時には窓が割られたり、家の中が荒らされたりと、物件の破損にもつながります。
そのため、災害や盗難などの特約加入をおすすめします。
保険会社によって、どこまでが補償範囲でどこからが特約なのか範囲がバラバラなので、見積もりをとって比較するのが良いでしょう。
火災のほか、風災・水災・盗難・水漏れ・破損など、ハザードマップや地域の治安などと相談しながら、なんの特約が必要か決めましょう。
また、地震保険は火災保険とセットで契約するため、別荘が「住宅用物件」として火災保険に契約している場合は、地震保険に契約できます。
しかし、別荘が「併用住宅物件」や「一般物件」として火災保険に加入する場合は、地震保険に加入ができない場合があります。
詳しくは保険会社に確認してみましょう。
別荘の火災保険選びのポイント
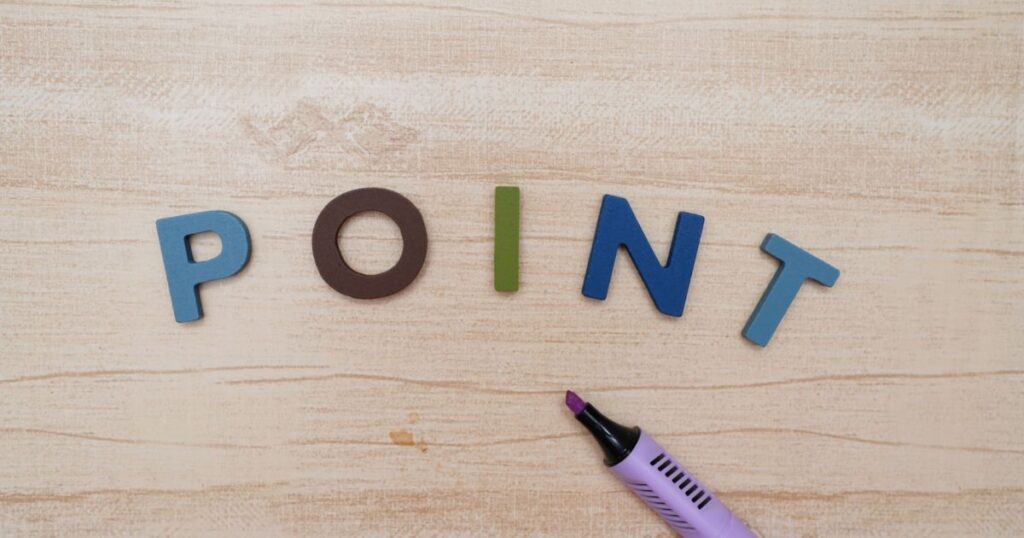
火災保険料はおもに以下のような項目を考慮して、物件ごとに価格が設定されます。
- 構造
- 床面積
- 建築年月
- 建築金額
- 補償範囲
しかし、普段住んでいない別荘に多額の保険料を払うのは躊躇するというのも正直なところです。
別荘にかける火災保険は、万が一火災で焼失した場合に備え、片づけの費用をまかなえる必要最低限の保険にするのがおすすめです。
自宅など、通常の住宅では、火災保険金額を、物件評価額の100%で設定するのが一般的です。
ですが、別荘の場合仮に焼失してしまっても、新たに建て直しや買い替えをしないという場合も多いでしょう。
しかし、焼け残った残物の撤去費用は必要となります。
撤去費用をまかなえるだけの保険金が受け取れるよう設定し、月々の保険料を抑えると良いでしょう。
個人賠償責任保険の検討も
別荘がある場所に自然災害での台風や大雨の警報が出ていても状況を確認しに行く事が難しい場合もあります。
別荘でも管理が不十分だったことにより台風で屋根の一部がはがれて近隣の住宅に被害を与えるなどで損害賠償責任を負ってしまえば、所有者に責任があります。
そのようなリスクに備えて個人賠償責任保険(住宅物件の場合)や施設賠償責任保険(一般物件の場合)があると安心です。
また、別荘などの人が住んでいない間の空き家は、放火の被害を受けるリスクが高くなります。
万が一、放火で損害を受けた場合は火災保険の契約があれば補償を受ける事ができますが、近隣の住宅に燃え広がる類焼のリスクもあります。
別荘であっても「失火責任法」により隣家への損害賠償責任を負う事はありません。しかし、別荘は、常にその場所に住んでいるわけではないため、メンテナンスや管理が行き届いていないと「重大な過失」として損害賠償責任が問われるリスクも一般の住宅より高くなります。
別荘は、常に居住する住宅とは異なるため管理が行き届いていない期間に起こるトラブルに備えるためにも個人賠償責任保険や施設賠償責任保険で準備しておきましょう。
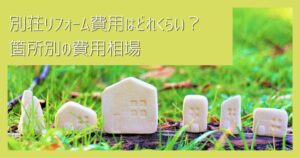
まとめ
今回は、別荘やセカンドハウス火災保険について必要な理由や、保険選びのポイントをご紹介しました。
- 別荘・セカンドハウスにも火災保険は必要
- 保険選びのポイントは最低限の保障にする
- 建物の状況によっては、盗難の特約や個人賠償責任保険の検討も

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!