働き方改革の一環として、厚生労働省がダブルワーク(以下、Wワーク)の普及や促進に取り組んでいます。
そのため、副業やWワークを解禁、就業規則の整備をする企業も増えてきました。
今後増えてくると考えられるWワークとはどのような働き方なのか、気になりますよね。
今回はWワークとはどのような働き方なのか、確定申告やどんな手続きが必要かをご紹介します。
Wワークとは?
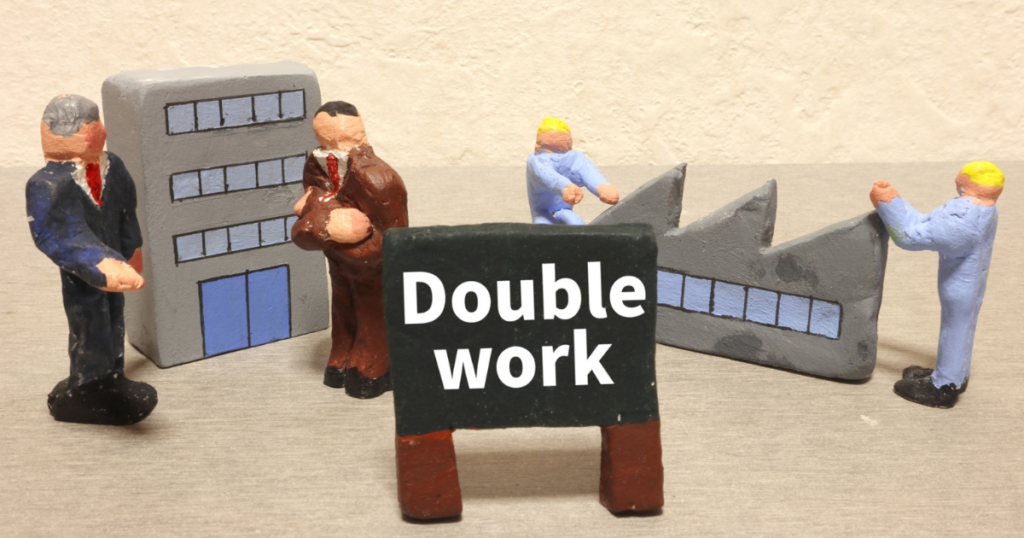
Wワークとは、「2つの仕事を掛け持つこと」をいいます。
例えば週の半分はコンビニ、他の日はデリバリーの配達員として働いてる場合、Wワークに該当します。
Wワークとして人気の職種としては、接客業、塾講師、飲食店勤務、引越し、デリバリー、クラウドソーシングを活用したフリーランスなどがあります。
Wワークは、2つ以上の仕事を掛け持っている状態ですが、どちらも本業ではなく、アルバイトやパートタイム労働者、フリーランス、非正規雇用として働いていることが多いです。
近年では、自身のスキルを活かして仕事を受注できるクラウドソーシングも登場し、Wワークに挑戦しやすい時代になりました。
今後はWワークをする方が当たり前の社会になるかもしれません。
副業・兼業とWワークの違い
副業とは、企業などに勤めている正社員が休日などの空き時間を使って、別の仕事を行うことをいいます。
「副」は「主なものに伴って補佐となること」という意味を持つことからも分かるように、正社員のように本業の仕事を持っている人がサブとして別の仕事を行うことを意味します。
Wワークはあくまで複数の仕事を掛け持つことを指すため、副業と似ていますが厳密には意味が異なります。
ちなみに、兼業とWワークは同じ意味を持つ用語なので、「兼業」と聞いた際はWワークのことを指すと考えてよいでしょう。
パラレルキャリアとWワークの違い
パラレルキャリアとは、本業を持ちながら第2のキャリアを築くことを指します。
Wワークは仕事を指す一方、パラレルキャリアはボランティア活動など無償活動も含まれるのがWワークとの大きな違いです。
例えば、サラリーマンとして勤務しつつ、バンドを組んで音楽活動している、趣味で描いた漫画を出版しているなど、収益の有無にかかわらず第2のキャリアを持っている方も「パラレルキャリアを築いている」といえるでしょう。
ボランティア活動の他、スキルアップや好きな分野での実績獲得などを目的に取り組む方が多いようです。
Wワークに向いている仕事

Wワークでは、向いている仕事とそうでない仕事があります。
Wワークに向いている仕事の例をご紹介します。
- 在宅でできるクラウドソーシング
- サービス業やコールセンターなどのシフト制の仕事
- 引っ越し作業などの単発の仕事
- デリバリーなどの短時間の仕事
いずれの仕事も時間に融通がききやすいという共通点があります。
Wワークをする場合、それぞれの仕事がおろそかになっては本末転倒です。
そのため、時間に融通がききやすい仕事で、双方の仕事のバランスがとれることが理想です。
Wワークのメリット

とはいえ、本業がある方が、いきなりWワークをするというのはなかなかハードルが高いかと思います。
ここではWワークをするメリットについてご紹介しますので、ご自身の現状と比較しながらWワークを始めるか検討しましょう。
メリット① 収入アップが期待できる
Wワークの大きなメリットとして挙げられるのは、やはり収入の増加です。
自身で働く時間や仕事内容を選ぶことができるため、収入アップが期待できます。
もし自分に合った仕事を見つけることができた場合、好きな仕事をしながら高い給料を得ることも可能です。
メリット② スキルアップができる
Wワークでは、異なる職種で働く人が多いため、このような場合には広い範囲のスキルが獲得できます。
また、Wワークで得たスキルを活かしキャリアアップを図る人も多くいます。
「やりたい仕事はあるが、いきなり転職するのは不安」という方も、まずはWワークで挑戦してみるのも有効な手段です。
Wワークで働いてみて仕事ができそうであれば、転職活動をスタートするというのも良いかもしれません。
メリット③ 働く場所に縛られない仕事が多い
プログラミングやイラストレーター、ライターなどフリーランスとして仕事を受注すれば、働く場所を自由に選ぶことができます。
在宅はもちろん、都会から離れて田舎で働いたりといった二拠点生活をすることも可能です。

メリット④新しい人間関係を築くことができる
職場が2つになれば、出会う人も2倍になるため新しい人間関係を築くことができます。
Wワークでの新しい人間関係の中で、新しい仕事を紹介してもらったり、友人として親睦を深めたりもできます。
メリット⑤リスク回避ができる
企業の業績が悪くなると、正社員ではなく非正規社員やアルバイトが先に解雇されます。
1つの職場に依存していた場合、一瞬で収入源をすべて失ってしまう危険がありますが、Wワークをしていれば収入源をすべて失うことがありません。
また、現在では正社員が安泰という時代は終わり、リストラということもあり得ます。
そういった面でもWワークはリスク回避ができると言えるでしょう。
Wワークの注意点

Wワークにはさまざまなメリットがある一方で、もちろん注意点もあります。
注意点も確認した上で、Wワークを始めるかを検討しましょう。
注意点①スケジュール管理が必要
Wワークを実施するためにはスケジュール管理が重要です。
複数の仕事を請け負うことができる分、うまくスケジュール管理をしないと休憩時間や休息日がなくなってしまうこともあります。
自由な時間をある程度確保したい方は、仕事に時間を費やしすぎないように意識しましょう。
ただし、仕事の時間を減らしすぎると、思ったように収入を得られないということにもなります。
Wワークを始める際は、いくら収入が必要なのか、どのくらい働かなければならないのかを事前に確認するのがおすすめです。
注意点② 会社の就業規則を確認する
掛け持ちで仕事をする場合、会社の就業規則でWワークを禁止している企業もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
一般的に、会社はパートやアルバイトに関してWワークを制限することはできませんが、情報の漏洩を避けるために、同業他社での副業やダブルワークを禁止している企業もあります。
企業の就業規則をしっかりと確認し、企業のルールに則って実施することをおすすめします。
注意点③休息する時間をしっかり設ける
Wワークでよく起こる問題が、休息する時間がないくらい仕事を入れてしまうことです。
働いた分だけお金を稼ぐことができるWワークですが、無理をすれば身体や心を壊すことにもなりかねません。
自身の健康や体調と相談の上、無理のない範囲で仕事をすることが大切です。
注意点④自身で保険等の手続きが必要
Wワークということは、一般的には正社員でないことが多いです。
そのため、健康保険や税金手続き、確定申告、年末調整など、自身でしなければならないことが多くなります。
正社員であれば会社が代行してくれる煩雑な税金の手続きを、非雇用のWワークでは自分で行わなければなりません。
Wワークをする前に知っておくべきこと

前項の注意点でも挙げたようにWワークをする上で、確定申告・社会保険など自身で手続きをする必要があります。
ここでは、Wワークをする前に知っておくべきことをご紹介します。
確定申告が必要となるケース
サラリーマンでも副業収入が年間20万円を超える場合、確定申告をしなければなりません。
また副業収入が給与の場合は、収入が20万円以下でも確定申告が必要です。
確定申告をしないと正しい納税額にならず、罰則が生じることがあります。
Wワークの場合、年間の収入の合計が103万円を超えると、超えた部分の金額に対して所得税が課税されます。
103万円を超えて課税された所得税は、確定申告の際に精算します。
パート・アルバイトでも確定申告が必要となりますので、自身の年間収入額はしっかりと把握する必要があります。
社会保険への加入要件
厚生労働省では社会保険の適用要件は、以下のいずれかを満たす者と定義しています。
- 週所定労働時間等が通常の労働者の4分の3以上の者
- 週所定労働時間が20時間以上、月額賃金8.8万円以上等の要件を満たす者(従業員501人以上の企業、及び、従業員500人以下で労使合意を行った企業のみ)
本業・副業ともに要件を満たしている場合、両社で社会保険に加入しなければなりません。
いずれかの会社に届出をして、保険料の支払いを按分してもらう必要があります。
Wワークで適用要件を満たす場合、会社に社会保険の手続きを相談しておきましょう。
Wワークをしてよいか就業規則の確認
Wワークをする前に、会社員の場合には勤め先の就業規則は必ず確認しましょう。
労働時間以外の時間をどのように利用するかは、基本的に労働者の自由です。
ただし本業に支障がでる、会社の秘密が漏洩する可能性があるようなケースでは、副業を制限・禁止されることがあります。
就業規則に定めがない場合でも、上司や人事部などに確認すると良いでしょう。
まとめ
今回はWワークとはどのような働き方なのか、確定申告やどんな手続きが必要かをご紹介しました。
- Wワーク、副業が今後はスタンダードな働き方になる可能性
- Wワークは収入アップ、スキルアップが期待できる
- 自身が費やせる時間や、知っておくべきことは事前に確認しておく

