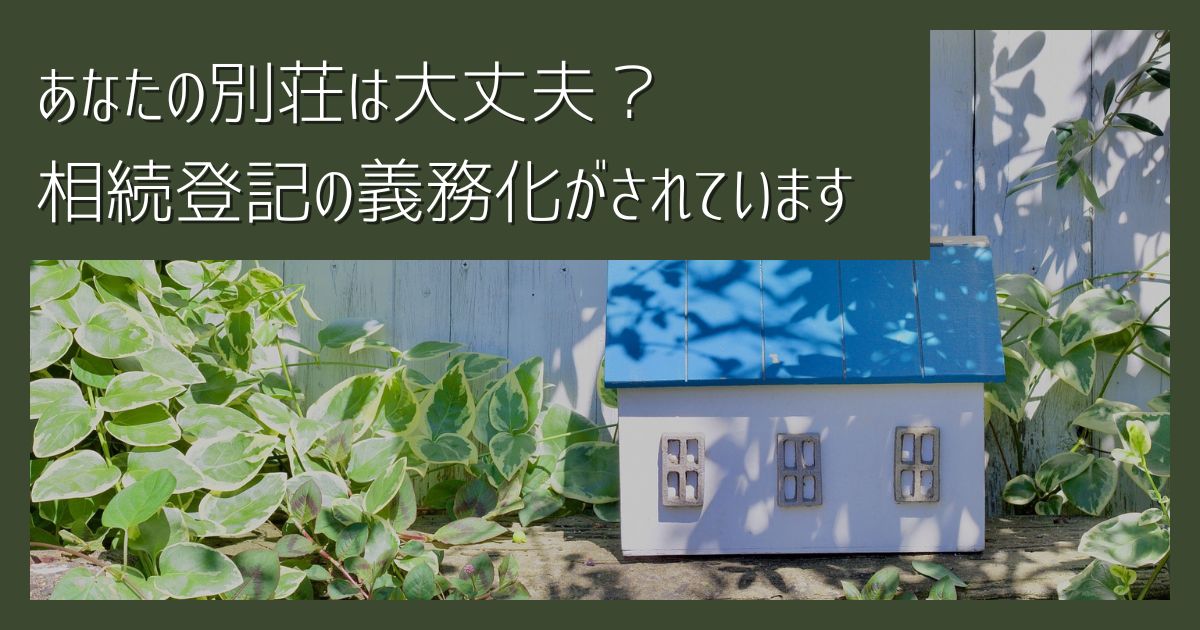昨今の所有者不明土地の問題を受けて、2024年4月より「相続登記が義務化」されました。
今後、義務化によって相続登記がされていない土地・建物は罰則の対象となります。
別荘を所有している方も、これから相続の可能性がある方も、現在の所有者がどうなっているか一度確認の必要があるかもしれません。
今回は、相続登記の義務化の内容、別荘やセカンドハウスを所有している方にとっての必要性や手続き方法を解説します。
2024年に義務化の「相続登記」とは

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)から不動産を相続した際に必要となる不動産の名義変更です。
不動産を相続した際に、相続登記が正しく行われていなければ、第三者に対して土地・建物の所有権を主張できません。
登記簿の情報は、不動産の売却や利活用、担保に入れる際に必要となります。
義務化以前は相続登記をいつまでに対応しなければならないといった法的なルールがありませんでした。
しかし、2024年4月に相続登記に具体的な期限が定められ、行わなかった者に対して罰則を加えるという「相続登記の義務化」が決定しました。
なぜ相続登記が義務化?
相続登記がされず所有者不明の空き家や空き地が増えてしまうと、適切に処分できず、不動産の取引だけでなく、都市開発の妨げにもなってしまいます。
また、所有者不明土地が増えてしまう理由のひとつに、所有者側が相続登記を行わないデメリットをさほど感じないという点があります。
複雑な相続登記の手続きを所有者自身が行うのは容易なことではなく、登記費用や固定資産税の支払いも生じてきます。
費用負担を避けるために登記しないといった理由も相続登記を行わないことに繋がっていると思われます。
これらの問題解消のため、2024年4月より不動産の所有者を明確にする相続登記の義務化がされました。
別荘・セカンドハウスは相続登記されていないケースが多い?

相続登記が義務化される前に相続が発生しているケースでは、別荘やセカンドハウスは相続登記されていない事も多くあります。
その理由は以下の通りです。
遠隔地での手続きになるため
相続登記は、「その不動産の所在地を管轄する法務局」に対して、申請しなければいけません。
例えば、軽井沢に別荘がある場合には長野県の法務局に申請が必要です。
居住地から遠い場所に別荘がある場合は現地まで赴く必要があり、補正があった場合、更に手間と時間がかかってしまいます。
その為、後回しになってしまいそのまま放置されているケースがあります。
登記費用がかかるため
不動産の評価額に応じて登記費用が発生するため、複数の不動産を相続する場合、費用負担が大きくなります。
そのため、住居と違い、相続の必要性が差し迫っていないため登記せずに放置しているケースです。
別荘所有を把握していない
別荘として建物が建っている場合以外にも、別荘地の土地を所有しているだけで、建物は存在していないケースもあります。
過去に流行した原野商法で別荘地を購入していた場合は、土地だけを所有していてそのまま放置されている場合があります。
資産価値が極端に低いような土地の場合、固定資産税がないこともありますので、相続人が把握できていないというケースがあります。
相続登記をしない場合のリスク

相続登記をしなかった場合のリスクはどのようなことがあるでしょう。
主に下記のようなケースが挙げられます。
相続登記の義務化における罰則
相続により取得した不動産を正当な理由なしに3年以内に登記しなかった場合、10万円以下の過料を求められる可能性があります。
また本改正では一緒に「住所変更登記の義務化」も行われます。
不動産の所有者に氏名・住所の変更がある際にも、2年以内に変更手続きを済ませておかないと、5万円以下の過料が請求される可能性があります。
法改正前に相続した不動産は?
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、相続登記を完了させていない場合、改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。
不動産を売却できない
相続登記のされていない所有者不明土地や不動産の名義が被相続人のままの場合、売却することができません。
売却を考えている場合は、速やかに相続登記を行う必要があります。
権利関係が複雑になる
遺産分割協議が行われず、相続登記をしないまま相続人のうちの誰かが亡くなると、次の遺産相続が開始されてしまいます。
また、法定相続人がすでに亡くなっている場合には、代襲相続が発生します。
このように、相続人の数が増えると権利関係はますます複雑化してしまいます。
相続人の間で面識がない場合や、連絡先が分からないような状態では、遺産分割協議を行うことさえ困難になります。
これらのリスクを回避するために、できるだけ速やかに相続登記を済ませましょう。
相続登記の手続き方法
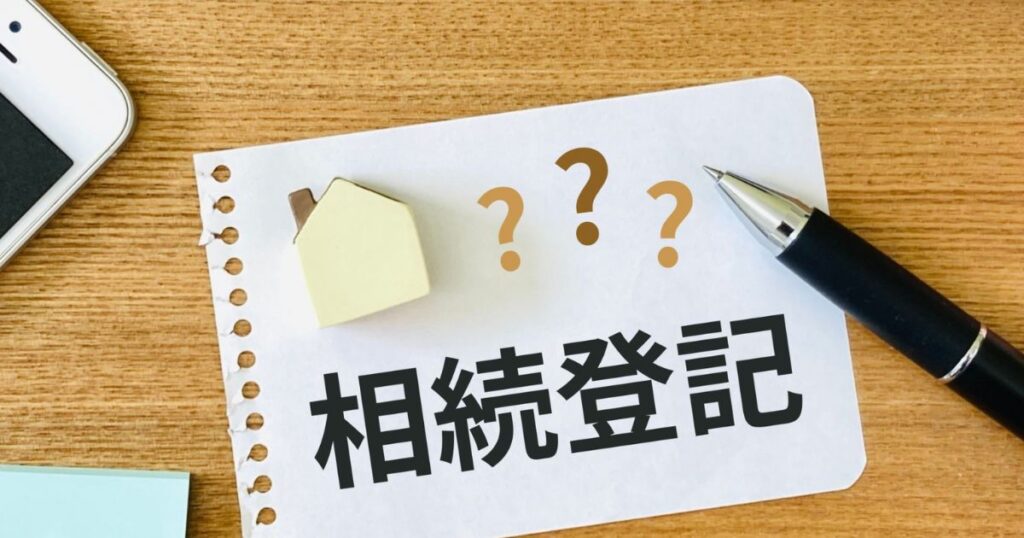
申請手続きは、相続する土地を管轄している法務局で行います。
①相続する不動産を確認する
亡くなった人が不動産を所有していたら、その不動産の状態、権利関係などを確認します。
自宅などに登記事項証明書(登記簿謄本)があれば、それで確認できますが、なければ管轄の法務局で入手して調べることもできます。
現在はオンラインでの閲覧や申請も可能です。
不動産は、土地と建物に分けて登記されているので、まずはそれぞれの所有者を確認しましょう。
土地は一つの敷地として利用していても、登記簿ではいくつかの筆に分かれていることがあり、一筆ごとに登記されているので、それぞれの面積も確認する必要があります。
建物は床面積のほか、構造なども確認しましょう。
また、敷地につながる私道が近隣世帯との共有名義になっている場合や、区分所有マンションの敷地も、亡くなった人の持分が登記簿に記載されているので、その持分を相続し名義を変更することになります。
②不動産を引き継ぐ人を決める
遺産相続は、遺言書があればそれが優先されるため、その遺言で不動産を引き継ぐ人を確認します。
遺言書がない場合は、相続人による遺産分割協議で遺産の分け方を話し合い、不動産についても誰が引き継ぐかを決めることになります。
決めた内容に全員が合意したら、それを遺産分割協議書にまとめ、相続人全員の署名・捺印をします。
③相続登記に必要な書類を収集・作成
相続登記に必要な書類は、亡くなった人の戸籍関係の書類や、相続人に関する書類、対象となる不動産の固定資産評価証明書など、複数あります。
登記申請書は法務局のホームページで書類の様式をダウンロードでき、記載例もついているので、それをもとに必要事項に記入して作成し、用意します。
相続登記の申請時に、法務局で実施する「法定相続情報証明制度」を利用し、法定相続情報一覧図の写しを入手すると、その写しが相続登記のほか、金融機関の相続手続きにも利用できるため、便利です。
④管轄の法務局へ申請する
対象の不動産(別荘)の住所地を管轄する法務局へ行き、該当の窓口へ登記申請書と添付書類一式を提出して申請します。
登記申請には登録免許税の納付が必要で、先に別の窓口でその分の収入印紙を購入し、申請書に貼り付けて提出します。
法務局での書類の審査と登記には1週間~10日くらいかかります。
登記が完了すると、登記識別情報の通知や登記完了証を受け取れるので、保管しましょう。
なお、遺産分割による登記と遺言書がある場合の登記では、必要な添付書類に違いがあるため、事前に確認しましょう。
相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等-法務局
将来売却するためにも「相続登記」と「維持管理」を

別荘地はその景観や環境を保全するために管理会社が維持管理をしていることが多く、別荘地特有の管理費が発生していることも多いです。
また、別荘として使っていた建物自体も劣化していくため、維持するための費用も発生します。
相続した方が別荘を使わない場合は、こういった費用は負担となりますので、別荘を売却するという選択肢も出てくると思います。
その為にもまずは「相続登記」を行っておく必要があります。
また、一般的な住宅地にある建物と違い、別荘地にある建物は売却成立までに時間がかかるケースが大半です。
自然環境に建てられていることも多く、建物劣化が進みやすいため、資産価値を落とさないよう売却までの間も管理・メンテナンスが必要です。
別荘管理区画である場合、管理会社が清掃やメンテナンスを有料で行ってくれる場合もありますが、そういったサービスがない、管理会社が入っていない場合は定期清掃や管理を行う専門業者に依頼することも可能です。
まとめ
今回は、相続登記の義務化の内容、別荘やセカンドハウスを所有している方にとっての必要性や手続き方法をご紹介しました。
- 2024年4月より相続登記は義務化され、手続きがされていないと罰則あり
- 別荘など住居以外の相続登記は放置されているケースが多い
- 将来の売却を見据えて現在の登記確認と、相続登記の準備を

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!