個人事業主を営んでいると、資金調達が課題となりがちです。
そこで活用したいのが国や自治体が行っている助成金・補助金等の支援制度です。
現在、個人事業主が活用できる助成金や補助金の制度は、ますます充実し多様化しています。
しかし、それぞれには独自のメリットと注意点が存在し、申請の流れや必要書類を適切に理解しなければ、支援を受けることができません。
今回は、助成金と補助金の基本情報からその違い、また個人事業主が利用できる主要な助成金や補助金の最新情報までを詳しく解説します。
個人事業主は資金調達が課題

個人事業主として事業を経営していると、資金調達に関する悩みにぶつかることが多いでしょう。
特に、新たな設備投資を検討している場合や、事業を拡大したいと考えている際には、まとまった資金が必要になります。
しかし、銀行融資を受けるには審査が必要であり、利息の負担も考慮しなければなりません。
そのため、返済不要な資金を確保できる助成金や補助金は、個人事業主にとって非常に重要な制度です。
助成金や補助金を活用することで、自己資金の負担を軽減しながら、事業の成長を後押しすることができるでしょう。
例えば、新たな販路を開拓するための広告費、業務の効率化を図るためのITツール導入など、多くの場面で支援を受けることが可能です。
こうした制度を上手に活用することで、経営の安定性を高め、より持続可能な事業運営を実現できるようになるでしょう。
ただし、助成金や補助金には申請条件や用途の制限があるため、事前にしっかりと情報を確認し、自身の事業に適した制度を選ぶことが重要です。
また、申請には一定の手続きが必要であり、場合によっては専門家のサポートを受けることも検討するとよいでしょう。
助成金?補助金?支援制度の種類

助成金、補助金、そして融資(貸付制度)は、いずれも事業を支援するための資金調達手段ですが、それぞれの特徴や条件に大きな違いがあります。
助成金
助成金は、原則として返済不要な資金援助で、主に国や自治体が提供するものです。
助成金の支給は、指定された要件を満たすことで、一定の条件に基づき自動的に受けられることが多いです。
例えば、雇用促進や労働環境の改善、働き方改革を支援するキャリアアップ助成金などが代表的な例です。
助成金を受け取るには、申請書の提出や必要書類の準備が必要ですが、審査を通過すれば比較的簡単に受給できる点が特徴です。
補助金
補助金も返済不要な資金援助ですが、助成金とは異なり、審査を経て採択される必要があります。
補助金は主に事業の成長や新技術の導入、設備投資などを支援するために使われます。
代表的な制度に、IT導入補助金やものづくり補助金などがあります。
補助金を申請する際には、事業計画書を提出し、審査を通過する必要があり、その結果に応じて受給できるかどうかが決まります。
審査が厳しく、競争も激しいため、申請の際には計画の明確さや実現可能かが重要となります。
融資(貸付)
融資(貸付)は、助成金や補助金とは異なり、受け取った資金を後で返済しなければならないという特徴があります。
国からの融資は、低金利で借りられることが多いですが、返済期間や利息が設定されています。
政府が提供する融資制度には「マル経融資」や「日本政策金融公庫」などがあります。
資金が必要な時に手軽に借りられる一方、返済の義務が生じるため、資金繰りを十分に考慮した上で利用する必要があります。
助成金・補助金を利用するメリットと注意点
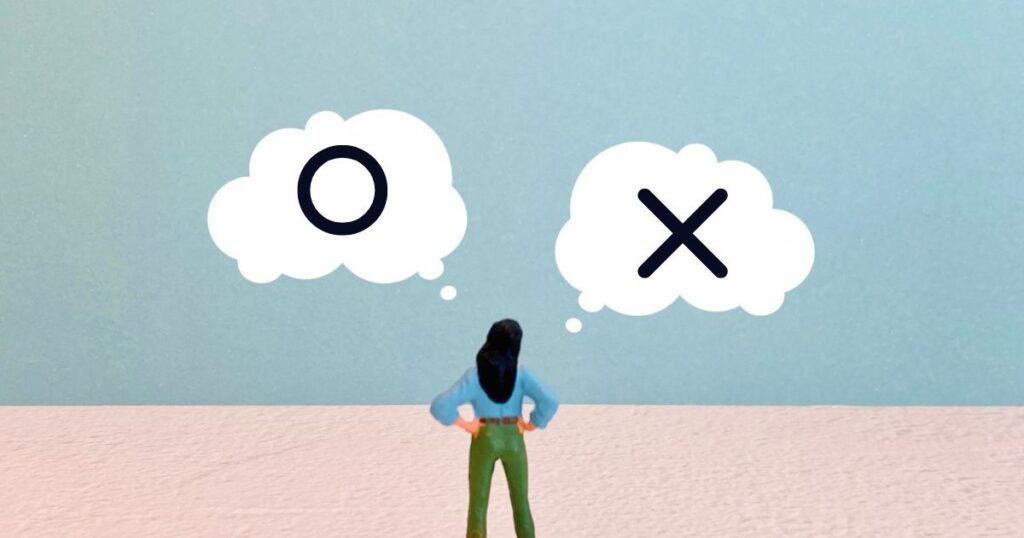
助成金・補助金等を利用することは、事業の成長を促進する上で多くのメリットがありますが、注意しなければならない点も多く存在します。
ここでは助成金・補助金等を利用するメリットと注意点を見ていきます。
助成金・補助金等のメリット
助成金・補助金等を利用するメリットには、以下の点が挙げられます。
- 助成金や補助金を活用することで、事業資金を確保できるため、自己資金の負担を減らしながら新たな投資を行うことが可能。
- 新しい取り組みや設備投資を支援する制度が多く、事業の成長や効率化に役立てることができる。
例えば、ITツールの導入や設備の購入など、事業の競争力を強化するための資金として活用できる。 - 経営の安定につながり、資金繰りの不安を軽減することができる。
特に、小規模事業者やスタートアップにとっては、資金面での支援が経営の持続性を高めるために重要。 - 国や自治体からの認定を受けたという安心感も得られるため、事業の成長とともに信用力も増す。
利用する際の注意点
助成金・補助金等を利用する際の注意点は以下の通りです。
- 助成金や補助金の申請には一定の時間と手間がかかる。
書類作成や要件確認が必要となるため、専門家に相談する、事前に準備を進めておくことが大切。 - 各制度には利用できる要件や用途に制限があるため、事前に詳細な条件を確認し、事業計画と合致するかを慎重に判断する必要がある。
- 不正受給を行った場合、返還請求だけでなく、罰則が科される可能性がある。
申請時には正しい情報を提出し、適切な形で制度を活用することが求められる。
【2025年】個人事業主向け補助金・融資制度

小規模事業者持続化補助金
小規模事業者が、販路開拓や業務効率化を目的として行う取り組みを支援する補助金制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 第17回:2025年6月13日締切 |
| 対象者 | 個人事業主などの小規模事業者 |
| 対象経費 | 販路開拓、業務効率化に関連する経費 (機械設備や広告費用、イベント出展など) |
| 補助金額 | 最大200万円 |
IT導入補助金
IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象者 | 中小企業・小規模事業者(個人事業主含む) |
| 申請期間 | 2025年3月31日~5月12日 |
| 対象経費 | 要件を満たしたITツール、及び役務費用 |
| 補助金額 | 最大450万円 |

リ・スキリング等教育訓練支援融資制度
新たなスキルを習得するための教育訓練を支援する制度。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請期間 | 2025年度10月開始予定 |
| 対象者 | 過去に3年以上の就業実績がある求職者 ※個人事業主も条件を満たせば利用可 |
| 対象経費 | 1カ月以上の職業訓練 大学・短大・専門学校などの正規課程 ハローワークが指定する講座、公共職業訓練、求職者支援訓練など |
| 融資額 | 受講料:年間最大120万円 生活費:月10万円×12ヶ月=120万円/年 ※貸付利率:年2.0% |
都道府県/市町村による補助金
都道府県や市町村ごとに、地域で新しく創業する人向けの補助金が設けられている場合があります。
制度を利用することで、事業を開始するために必要な機械や備品、販路開拓費等の初期費用を補助してくれます。
独立行政法人の中小企業基盤整備機構が運営する中小企業向けポータルサイト「J-Net21」において、自治体別支援金情報が確認できます。
▼自治体別支援金を調べる

助成金・補助金を活用するためのポイント
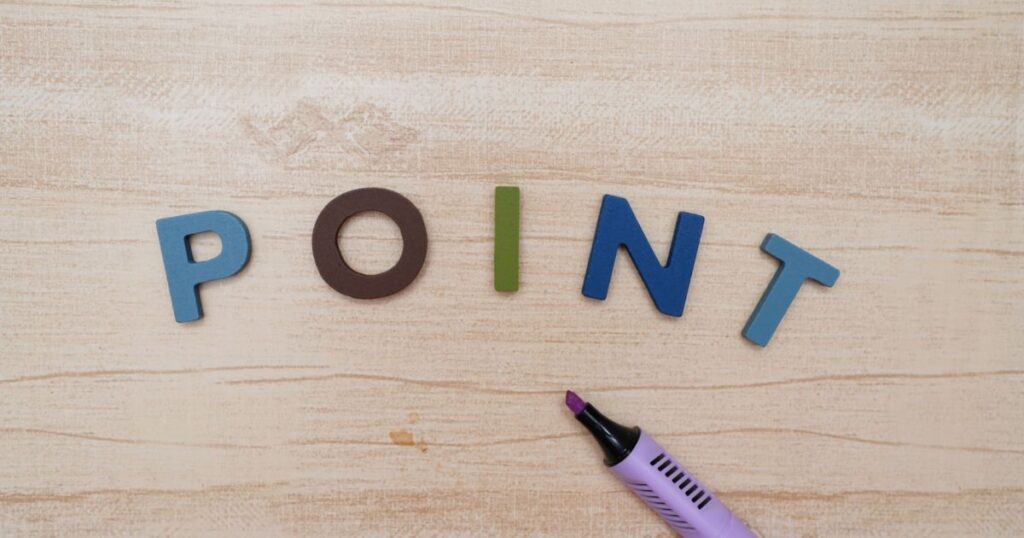
助成金や補助金は、事業の成長を支援する強力な制度ですが、正しく活用するためにはいくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。
以下の点に注意することで、スムーズに申請手続きを進め、制度を最大限に活用できるようになります。
申請前に要件をしっかり確認する
助成金や補助金には、それぞれ申請に必要な要件や条件があります。
事業者の規模や業種、利用目的に応じて適用される制度が異なるため、まずは自分の事業に適した助成金・補助金を選定することが大切です。
公式サイトや自治体の情報を確認し、制度の詳細をしっかりと理解した上で、申請を行いましょう。
また、条件を満たしていない場合、申請しても受給できないことがあるため、事前に十分な確認が必要です。
申請書類の作成は丁寧に
申請書類の作成は、助成金・補助金を受けるために非常に重要となります。
書類に不備があると申請が通らない可能性が高くなるため、事業計画書や収支計画書など、求められる書類を正確かつ丁寧に作成しましょう。
特に初めて申請する場合や書類作成に不安がある場合は、専門家(税理士や社会保険労務士、行政書士など)のサポートを受けるのも一つの方法です。
専門家に相談することで、書類に不備がなく、申請を通過する可能性が高まります。
締め切り日に注意
助成金・補助金には、申請の締め切りが定められています。
この締め切りを見落とすと、どんなに条件に合っていても申請することができません。
各制度の申請期間をしっかり把握し、余裕を持って申請手続きを進めることが大切です。
特に、複数の助成金・補助金を申請しようと考えている場合、それぞれの締め切りが異なることがあるため、カレンダーにメモするなどして、期日を管理しましょう。
また、申請書類を準備する時間も考慮に入れて早めに取り掛かることが重要です。
助成金や補助金を活用することで、事業の成長を支えるための資金を確保できる一方で、申請手続きにおける注意点を理解しておくことが、無駄なく制度を活用するための鍵となります。
まとめ
今回は、助成金と補助金の基本情報からその違い、また個人事業主が利用できる主要な助成金や補助金の最新情報までを詳しく解説しました。
- 助成金と補助金のメリットや注意点を理解し、賢く活用しよう
- 2025年の最新制度をチェックし、事業に役立てる
- 申請の際は慎重に準備し、支給の可能性を高めよう

