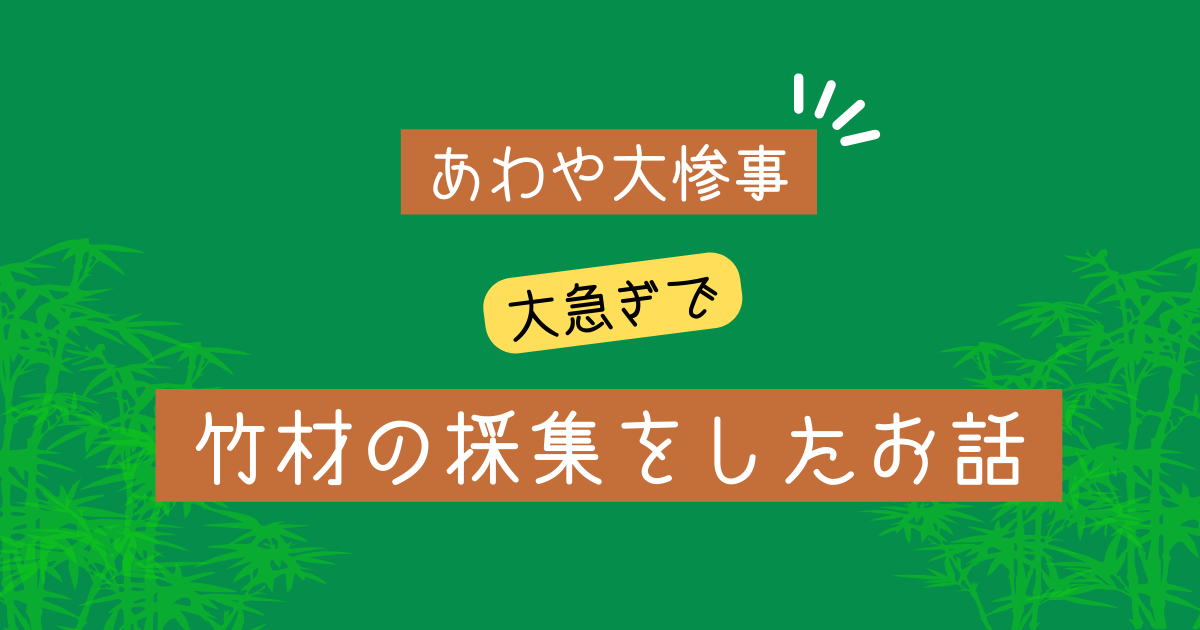こんにちは二拠点生活研究所のおさです。
前回の記事で庭で発見したお宝の話をしました。
外房の拠点庭に生えている竹が『布袋竹』という、和竿の材料として有名な竹だった事が判明。

詳しくは前記事をご参照下さい。

これから、放置竹林を整備しながら布袋竹を採取して、その採取した竹を利用して和竿を自作してみようかと思い、調査を行います。
正確にいうと、ちょっと忙しい時期だったので、調査をにきょらぼさんにお願いしました。

依頼を受けていた「布袋竹の採取~加工」についてのレポートが完成したのでお送りします

おっ!
相変わらず仕事早いねー
忙しい所ありがとう
助かるよ!

はい

どれどれ・・・
ふむふむ
伐採時期に関するレポート: 作成者 にきょらぼさん
竹を伐採するのに適した時期は、成長が鈍化して休眠状態になる秋から冬の間(11月から2月頃)です。
竹は他の樹木と同様、3月から9月頃に成長しますが、この時期は伐採には適していません。
秋から冬に伐採した竹は、水分が少ないため締まりが良く、質の良い竹材となります。
竹材として利用する目的がなくても、水分量の少ない竹は軽いため、伐採後の処理もしやすくなります。

なるほどー
竹には採取時期ってのがあるのね
11月~2月かぁ・・・・

って2月まで!!
※2月下旬のお話です

あと1週間ちょっとしかないじゃないか!
まずい!

なにより、何竿を作るのかさえ決まってないので、どんな個体を採取すればいいのか・・・
と、悩んでても仕方がないので、色んなサイズの布袋竹を採取して、乾燥することにしました。
手元に素材があれば何かには使えるでしょう。
その週末・・・
天候にも恵まれ、作業日和。
布袋竹の形が良いものを根本から切って

節の個性が強いものを大まかに切り出し

根つきの布袋竹も、グリップ素材によさそうなので頑張って掘り出しました。

掘り出した布袋竹はウッドデッキに並べて日干し

朝早くから大量の布袋竹を切り出しましたが、想像以上に大変な作業!
竹は背が高いので取り回しが難しかったです。
また、必要な部分を取った後の葉が付いた部分を一か所に集めて処分する訳ですが、その移動も中々の重労働。
竹林の中には既に枯れてしまった竹も大量に残っており、その古竹も一緒に移動しました。
一番大変だったのは、根つきの布袋竹を土の中から掘り出す作業。
竹の根元は、根が密集していてスコップなんて入らないくらい硬いので、竹の根から少し離れたところに大きく穴を掘って、少しずつ竹の根を切りながら掘り出しました。
普段運動不足の人が、
「一日中電動工具を使い」
「立ったり座ったり」
「処分の竹を移動したり」
「穴を掘ったり」
すると当然・・・

あーーー!
腰がぁーーーーー!!
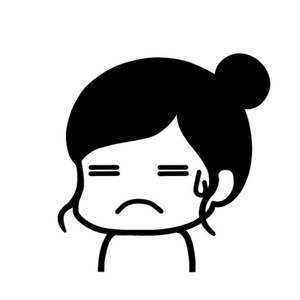
おつかれさま(苦笑)
おさって、一度作業始めると、倒れるギリギリまで動いてるイメージよね
日干しをした竹は、拠点の倉庫で陰干ししながら乾燥を進めている所です。
陰干しが終わったら油抜きという作業が待っているので、それまでは畑の拡張や手入れを行う予定です。(腰を労わりながら)
作業の後は、庭で収穫したほうれん草で晩酌 身体を動かした後のお酒はウマイ(毎日ウマイ)

秩父拠点の『山小屋』で、年末に収穫したゆずを添えました。
ゆずを入れると、ありふれたほうれん草のお浸しが急に上品な料理に早変わり。
最後までご覧頂きありがとうございました。
▼加工までは数か月を要します
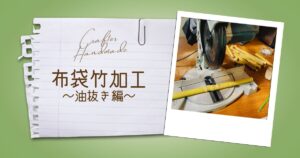
この記事を書いたのは

おさ
東京在住、3人家族
秩父・外房を中心に活動中
好きなことを好きなだけ
アウトドア・音楽・料理・家庭菜園・不動産…
好奇心旺盛がゆえに多趣味・多拠点生活中