「自然豊かな場所で生活したい」
「自給自足の暮らしをしてみたい」
と、地方の暮らしを考えている方におすすめなのが「地域おこし協力隊」という制度。
2022年度のデータでは、全国で約6,000人近くが活躍していると言われています。
また、働き方の多様化に伴いリモートワークを取り入れて地域おこし協力隊の活動を行う自治体も出てきました。
しかし、地域おこし協力隊という言葉は知っていても、あまり詳しく知らないという方も多いと思います。
今回は、国や自治体も力を入れている地域おこし協力隊についてご紹介します。
地域おこし協力隊とは

地域おこし協力隊とは、地方自治体の課題に取り組むために、全国からの応募者が派遣され、その地域への定住・定着を目指す制度です。
地域おこし協力隊員は、地域の特性や魅力を活かした活動を通じて、地域の活性化や定住促進、観光振興などを目指します。
具体的には、地域の特性や魅力を活かした観光資源の開発やPR、農業や漁業の振興、地域の文化や歴史の保護や活用、地域の子育て支援や高齢者支援など、様々な分野で活動を行います。
地域おこし協力隊は国の制度
地域おこし協力隊は、国が定め、地方自治体が実施している制度です。
この制度は2009年に開始され、2022年度の取組団体数(受入自治体数)は1,085団体で、6,015名の隊員が活躍しています。
政府はこの隊員数を2026年度までに10,000人に増やすという目標を掲げており、地域おこし協力隊等の強化を行うこととしています。
地域おこし協力隊の実情
隊員の男女比は6:4で、幅広い世代の隊員が活躍していますが、約7割は20~30代の若い世代となっています。
地域おこし協力隊の活動期間は、概ね1年から3年間となっており、活動期間中は各自治体で定められた給料が支払われます。
また、地域おこし協力隊の活動終了した人の6割が、活動地に定住しているというデータもあり、地方移住への足掛かりとなっています。
地域おこし協力隊はどんなことをするの?

地域おこし協力隊は、地方自治体が実施する制度であり、地域の活性化や地域社会の課題解決に貢献することを目的としています。
具体的には、以下のような活動が行われます。
①地域振興のための企画・実行
地域おこし協力隊は、地域の課題や問題点を把握し、その解決に向けてプロジェクトを立ち上げ、実行することが求められます。
例えば、地域の特産品を活かしたイベントの開催や、地域の観光資源の活用などが挙げられます
②地域の魅力の発信・PR
地域おこし協力隊は、地域の魅力を発信することで、地域に人を呼び込むことにも貢献します。
ブログやSNSなどを活用した情報発信や、地域PR用のパンフレットや動画制作などを行います。
③地域住民との交流・コミュニケーション
地域おこし協力隊は、地域住民との交流を大切にし、地域に根ざした活動を行います。
地域住民の声を聞き、意見を交換することで、地域の課題解決につながるアイデアを出し合ったり、地域の人間関係の構築に貢献したりします。
④地域の組織・団体の支援
地域おこし協力隊は、地域の組織・団体の活動支援も行います。
例えば、地域の農業団体や商工会のイベントの協力や、地域の子育て支援グループの運営支援などがあります。
地域おこし協力隊の雇用形態や給料

地域おこし協力隊員として活動する場合、どのような働き方・収入になるのか気になりますよね。
ここでは地域おこし協力隊の雇用形態や給料、二拠点生活をしながら兼業・副業はOKかなどをご紹介します。
期間
地域おこし協力隊は移住を促進するための制度であるため、活動できる期間が最長3年と決まっています。
給料
地域おこし協力隊には国から活動費として、年480万円(令和4年度※年によって変動あり)が支給されます。
活動費とは、活動する中で必要な費用を賄うお金となります。
その活動費の内訳は200万円が活動経費等、280万円が報酬の上限とそれぞれ決まっています。
そのため、協力隊の給料は最大280万円となります。
しかし、実際の給料額の平均は14万円~16万円というところが多いようです。
その他、住宅費用として5万円の補助や、移動費などの手当もあります。
ただし、自治体によって支給額や手当は異なるため確認が必要です。
雇用形態
地域おこし協力隊の働き方は大きく分けて「一般職」と「雇用関係なし」の二つに分けられます。
◎一般職
自治体に会計年度任用職員として任用されます。
そのため、扱いとしては一般の公務員と同じ扱いとなり、社会保険も公務員と同等となります。
その代わり、自治体によっては副業ができないところもあり、その場合は地域おこし協力隊の任期後に生計を立てる手段を任期中に確保するのが難しいケースもあります。
◎雇用関係なし
雇用契約がなく、地域おこしに関する業務を委託されるという形です。
個人事業主であるため、業務や働く時間の采配も自分で決めることができ、もちろん副業が可能です。
しかし、個人の裁量が大きい分責任も大きくなります。
また、自分で国民年金・国民健康保険・NPOなどで社会保険に入り、費用も自己負担で支払わなければなりません。
二拠点生活で地域おこし協力隊
まだまだ少ないのですが、都心と地方の二拠点での活動やテレワークでの発信、また移住サポート活動など、二拠点生活をしている人でも参加可能な地域おこし協力隊を募集している自治体(例:静岡市※現在は終了)もあります。
新しい働き方が定着してきた昨今では、今後も二拠点生活者向けの地域おこし協力隊募集が増えてくると予想されます。
地域おこし協力隊のメリット

地域おこし協力隊に参加することには、以下のようなメリットがあります。
①地方の暮らしを体験できる
現在、都市部に住んでいる方で、地方への移住を検討している場合、その地域に適応できるか不安を抱える方も少なくないと思います。
そのような方は、いきなり移住せずに、地域おこし協力隊の制度を利用することで、地方の暮らしを体験することができます。
地域おこし協力隊として活動できる約3年間を活用することで、実際に地方の暮らしを体験しながら、情報や人脈を深めていくことができるでしょう。
②地域に溶け込みやすい
地域おこし協力隊に参加すると、突然移住するよりも地域に溶け込みやすくなります。
多くの自治体では協力隊の受け入れ実績があるため、協力隊の先輩がおり、移住後のサポートをしてもらえる体制が整っています。
また、最低限活動を維持できるための収入をもらいながら移住できること、実家が都心部の人にとっては田舎をもてるということも協力隊に参加して地方移住するメリットと言えるでしょう。
③給料が支給される
自治体や募集内容によって金額は違いますが、地域おこし協力隊の任期中は給料が支給されます。
慣れない土地で収入がないのは不安を感じると思いますが、地域おこし協力隊であれば、その点を解消しながら地方で活動することができます。
また、自治体によっては住居や車を貸与してくれたり、ガソリン代などの補助がある場合もあります。
④新たなキャリアの形成
地域おこし協力隊に参加することで、新しいことに挑戦することができます。
地方自治体での地域課題解決に向けたアイデアの発信など、自己実現やキャリアアップの機会が得られます。
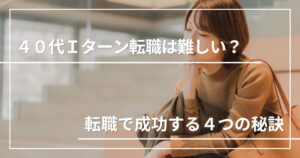
地域おこし協力隊の注意点

地域おこし協力隊に参加する際には、以下のような注意点があります。
①希望の仕事ができない可能性がある
契約内容にもよりますが、実際の活動内容が自分のやりたいことと違うケースがあります。
過疎地域が抱える課題は多岐に渡るため、募集要項に記載以外の活動をしなければならない場合もあるでしょう。
また、実際に働いてみると当初任されるはずだった仕事ができなくなったというケースもあります。
そのため事前に受け入れ団体側へ確認や認識のすり合わせをしておくことが大切です。
②地元住民への敬意
地域おこし協力隊は、地域の発展に貢献するために活動することが目的です。
そのため、地元住民への敬意を忘れず、地域の文化や風習を理解し、適切なマナーを守ることが重要です。
現在、都会で暮らしている場合は地方特有の風習に驚くことも多いかもしれません。
しかし、地域おこし協力隊員として活動を行う上では、その地域毎の特性を理解することが必要です。
③自己責任と安全確保
地域おこし協力隊は、自治体からの指導の下、活動することが基本ですが、自己責任で活動することもあります。
そのため、自己責任で活動する際には、自分の安全を確保するための十分な準備をしておく必要があります。
地方は自然も多く、整備が行き届いていない場所もあるため、活動をする場合には十分に気をつけましょう。
④定住への期待がある
地域おこし協力隊の制度目的が「定住促進」のため、「いずれはここに住むんでしょ?」というように地元の方に期待されることは多くあります。
まだ移住をしようか迷っている人の場合は、それを言われ続けるのがプレッシャーに感じてしまうことがあるかもしれません。
地域おこし協力隊の参加条件

地域おこし協力隊に参加するにはどのような条件があるのでしょうか。
自治体によって応募要件は様々ですが、一般的な条件をご紹介します。
居住地
地域おこし協力隊に参加するには、現在の住まいが三大都市圏(東京近隣、大阪近隣、愛知近隣)やその他都市、政令指定都市に居住しており、任務先が決まった際には住民票を移動できることが条件になっています。
地域おこし協力隊の制度は「地域への定住促進」を目的としているため、現在、都市部にお住まいの方を募集しているということになります。
年齢
原則、年齢制限はありませんが、移住、および働くという観点から18歳以上と定められているところが多く見受けられます。
また、上限はさまざまですが、一般的に45歳までが多い印象です。
他にも、活動内容によって年齢制限が設けられていることがありますので、応募の際は確認をしましょう。
学歴・職歴
応募時に聞かれることがありますが、参加条件での制限はほとんどのところがありません。
しかし、自治体によっては独自の条件を設けている場合があります。
資格・スキル
参加するために必須の資格はありませんが、地方であることを考えると、運転免許証があれば活動の際の移動に便利です。
また、スキルについても必須条件としているところはありませんが、観光のPRを行うような活動内容の場合、SNSの活用方法や、PCのスキルがあると有利になるでしょう。
その他
その他、参加条件ではありませんが、任期が終了しても活動先に定住する意思がある人が採用されやすくなっています。
その他、幅広い年齢層の方とも人間関係が築けるコミュニケーション能力や、溶け込もうとする姿勢・誠実さがあれば、現地での活動をスムーズに遂行するための助けになるでしょう。
以上が、一般的な参加条件と言われています。
しかし、実際に応募される場合は、対象地域の参加条件を事前に確認しましょう。
◎全国の地域おこし協力隊 活動情報
・ニッポン移住・交流ナビ JOIN:https://www.iju-join.jp/chiikiokoshi/
まとめ
今回は、地域おこし協力隊の内容やメリット・応募条件等についてご紹介しました。
- 地域おこし協力隊は地方への定住促進を目的とした国の制度
- 活動期間中は給料が発生し、自治体によっては住居補助もある
- 任期終了後6割が定住しており、地方移住の足掛かりとしておすすめ

