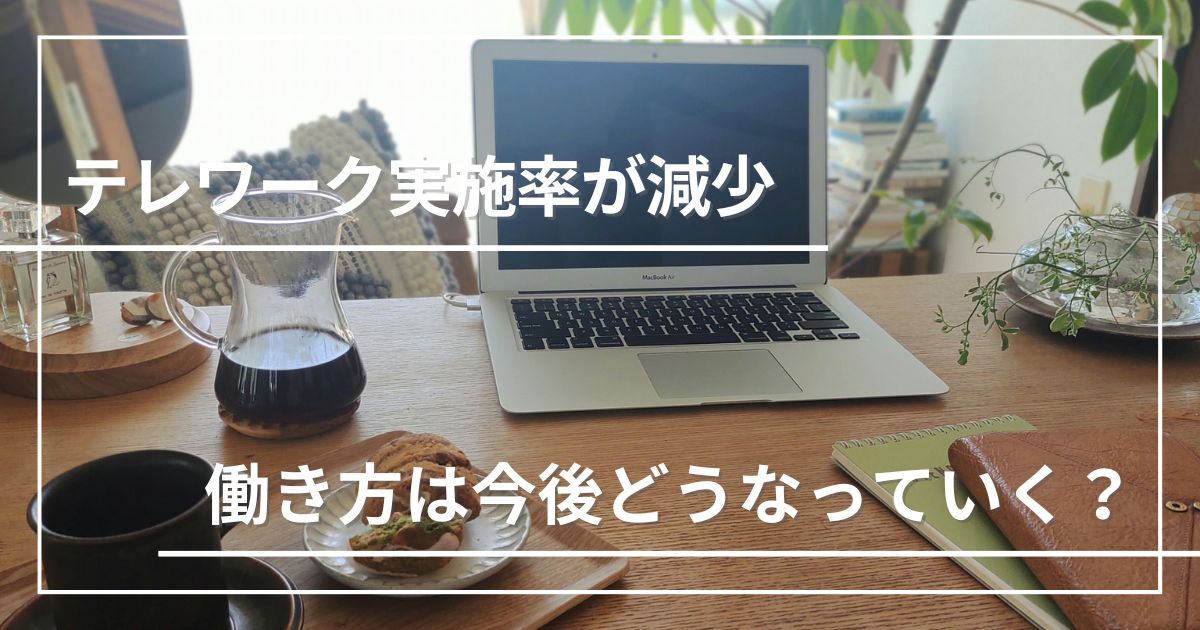日本では感染症対策の一環として「テレワーク」を導入する企業が増え、現在では一般的な働き方の1つとなりました。
しかし、コロナウィルス感染症の第5類への移行に伴い、テレワーク廃止を検討している企業も多いようです。
「テレワークから完全出社に戻ってしまった」
「テレワーク制度は残っているが、周りが出社していてテレワークしづらい」
というような声を多く聞きます。
テレワークによる働き方に慣れてしまった方は、完全出社になると生活スタイルに変更が出てきますし、仕事についても考えるきっかけになります。
経営者は、従業員にネガティブな影響をもたらす可能性を考慮して廃止すべきかの検討する必要があるでしょう。
今回は、企業のテレワーク実施の状況や、今後の働き方についてまとめました。
テレワークとは

テレワーク(Telework)とは、通信技術を活用して場所や時間に制約されずに仕事を行う働き方のことを指します。
具体的には、従業員が自宅やコワーキングスペースなどの場所で、インターネットや電話、ビデオ会議などのツールを使用して業務を遂行する形態です。
テレワークには以下のような特徴があります。
①場所にとらわれない
テレワークはオフィスから離れた場所で仕事を行います。
そのため自宅や地方の拠点、移動中の場所など、場所に制約されずに業務を遂行できます。
従来の外回り営業マンが出先のカフェで、電話やメール等の業務を行うこともテレワークの1つだったということになります。
②コミュニケーション技術の活用
テレワークでは、電子メール、ビデオ会議、チャットツール、プロジェクト管理ツールなどのテクノロジーを活用してチームや上司とコミュニケーションを行います。
以前からメールやチャットツールは普及していましたが、ビデオ会議やプロジェクト管理ツール等はコロナ禍以降に爆発的に普及しました。
③柔軟な働き方
テレワークによって、従業員の日常に柔軟性を与え、個々の生産性やワークライフバランスを向上させる特徴があります。
例えば、通勤時間の削減によって家事や家族とのコミュニケーション時間が確保できることにより、心身のバランスが保たれ、生産性のアップにも繋がります。
テレワークが普及した背景
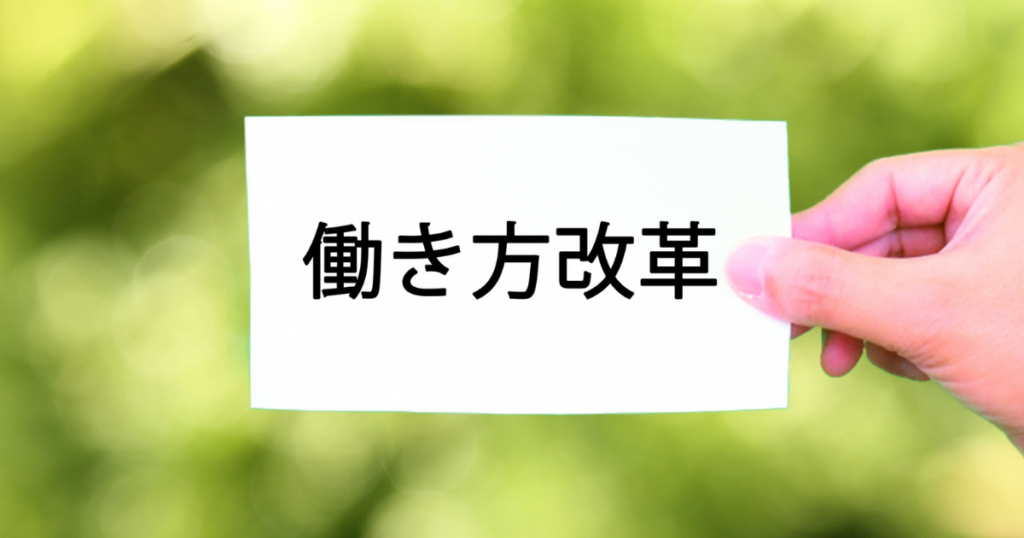
日本でテレワークが急速に普及したのはコロナ禍によるものでしたが、その以前から国が働き方改革の一環として国内企業にテレワークを推奨する動きがありました。
どのような背景があったのか改めて見ていきましょう。
技術の進歩とデジタル化の促進
インターネットの普及や高速通信技術の進歩により、リモートでの業務が可能になりました。
クラウドツールやウェブ会議ツールの進化もテレワークを支え、効率的なリモートワーク環境が実現したため、テレワークを導入しやすい環境が整ったのです。
働き方改革の一環
日本では働き方改革を、「個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で選択できるようにするための改革」としており、従業員のワークライフバランスの重視や、環境制約の克服に繋がるとしてテレワークが推進されました。
また、テレワークは子育て世代やシニア世代、障害のある方も含め、国民一人一人のライフステージに応じて生活スタイルに合った働き方を実現できるとされています。
オリンピックの交通緩和
2012年ロンドンオリンピック・パラリンピック競技大会では、交通混雑によってロンドン市内での移動に支障が生じるとの予測から、市内の企業の約8割がテレワークを導入しました。
こうしたロンドンの成功事例にならい、東京オリンピックの開会式予定だった7月24日を「テレワーク・デイ」と位置づけて、2017年より多くの企業・団体・官公庁の職員がテレワークを一斉に実施するよう呼びかけました。
パンデミックによる働き方の変化
新型コロナウイルスの世界的な流行により、多くの企業がテレワークへの移行に踏み切りました。
感染リスクの低減や社会的距離の確保のため、従業員が自宅や安全な場所で働く必要性があったためです。
この時期の経験がテレワークの普及を加速させ、企業や従業員がテレワークの利点や可能性に目を向ける契機となりました。
テレワークの現状(2023年)

では、テレワークによる働き方は現状どうなっているのでしょうか。
テレワークの実施率とニーズについてまとめてみました。
テレワーク実施率は減少傾向
公益財団法人日本生産性本部の「第12回働く人の意識調査(2023年1月)」によると、2020年5月に比べ、すべての規模の企業でテレワークの実施率が減少していることがわかっています。
- 全体テレワークの実施率は16.8%(2020年5月では実施率31.5%)
- 従業員100名以下では12.9%、101~1,000名では13.2%と中小企業における減少が大きい
- 1,001名以上は34.0%となっており、依然として実施率が高い
※出典:公益財団法人日本生産性本部「第12回働く人の意識調査」
従業員からのニーズは高い
前述の同調査では、テレワーク実施企業の従業員を対象にした調査も実施しています。
- 自宅での勤務で「効率が上がった」「やや上がった」と回答した割合は過去最高66.7%
- 自宅での勤務に「満足している」「どちらかと言えば満足している」の合計も87.4%と過去最高となった
- コロナ禍収束後もテレワークを行いたいかについて、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」の合計は、2022年10月調査の76.7%から84.9%へと増加
この結果から、緊急事態宣言などをきっかけとしてテレワークを開始した人のほとんどは、今後もテレワークを続けたいと考えていることがわかります。
なぜ廃止?企業が考えるテレワークのデメリット

感染症対策としてテレワークを導入した企業のなかには、すでに廃止を決断した企業もあります。
企業が廃止に至った理由には、テレワークによるさまざまな課題が大きく影響しています。
感染症による導入だったため
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020年4月に1回目の緊急事態宣言が発令されました。
同時期には感染症拡大の防止を目的として、国や自治体が企業にテレワークの実施を推奨しています。
そのため、一時的な措置として、テレワークを導入した企業が増えました。
総務省の「令和3年情報通信白書」によると、1回目の緊急事態宣言発令時には、テレワークの実施率がそれ以前と比べ3倍以上に上昇したことがわかっています。
しかし新型コロナウイルス感染症は第5類感染症へ移行し、状況が落ち着き始めたことから一時的にテレワークを導入していた多くの企業で、従来の「オフィスに出社するワークスタイル」に戻す動きがあります。
こういった理由から、テレワーク廃止の動きが出始めています。
コミュニケーション不足による課題
テレワーク導入後、従業員同士が直接顔を合わせる機会が減ったことでの、コミュニケーション不足を課題に抱える企業が増えました。
具体的にはテレワークの長期化によって、一人で仕事をすることに孤独感、閉塞感を覚える従業員が増えたということでした。
オフィスは単に仕事をする場ではなく、ときには雑談や相談などを通して従業員同士が気軽にコミュニケーションをとれるスペースとなります。
しかし、テレワークの長期化で出社しない従業員が増えると、どうしてもコミュニケーション不足が起きてしまうのです。
コミュニケーション不足は、業務効率や生産性の低下につながり、最悪の場合には離職に繋がってしまう可能性があります。
そういったことから、社内のコミュニケーション不足を解消するために、テレワークの廃止に踏み切る企業もあります。
従業員のモチベーション低下を懸念
テレワークの長期化で、仕事のやり方やスタイルが大きく変化したという人は多いです。
自宅で黙々とテレワークをおこなっても、仕事ぶりを見てくれる上司や同僚はいません。
そのため、「正当に評価されない」という不満を抱え、モチベーションを維持できなくなってしまいます。
また、上司が従業員の働きぶりをチェックすることができず、どのように評価をおこなえばいいか判断できなくなってしまうことがあります。
テレワークは今までの人事評価では透明性が確保できないという課題があり、企業との物理的・心理的距離感が生じやすいため、従業員のモチベーション低下を懸念する企業は多いようです。
社内の平等性を維持するため
テレワークは職種によって向き不向きがあるため、社内すべての従業員に適用できるとは限りません。
たとえば店舗でお客様とやりとりをするような販売職や、工事現場での作業はテレワークができない職種ですよね。
さまざまな職種を抱える企業では、テレワークができない職種もあるため、テレワークを行っている従業員に対して不満を持ちやすくなるでしょう。
また、自宅ではテレワークに必要な環境が整備されておらず、断念せざるを得ない従業員がいるケースもあります。
テレワーク廃止の背景には、こういった従業員同士の平等性が損なわれるという課題もあるようです。
テレワークを継続する企業は何が違う?

テレワークの廃止を決定する企業がある一方、テレワークを今後も継続するという企業ももちろん多くあります。
その違いはどこにあるのでしょうか。
テレワークを今後も継続するという企業が実際に行っている内容をご紹介していきます。
コミュニケーションの取りやすい環境整備
テレワークというものは、コミュニケーション不足が生じやすいことが課題です。
そのため、テレワークを継続している企業で力を入れているのが、コミュニケーションの取りやすい環境づくりです。
例えば、ビデオ会議ツールやチャットツールを導入し、従業員同士がストレスなく交流できるよう対策を講じています。
部署関係なく交流ができる雑談用チャットルームの開設や、オンラインゲームを使ったレクレーションをしている企業もあります。
また、コミュニケーションを意識的に取れるように、ツール導入以外にも、オフィスにコミュニケーションスペースを用意しているところもあります。
テレワークを行っている従業員に、週に1回や月に1回程度、コミュニケーションスペースに集まってもらい、交流や意見交換を行うというものです。
意図的にコミュニケーションの場を作ると、長期的なテレワークを円滑に行うことができるようです。
テレワークを軸とした評価制度の導入
オフィスワークを前提とした人事評価では、目に見えやすい働きぶりを評価のポイントとする傾向があります。
しかし、テレワークでは、そういった勤務姿勢が見えにくいという課題があります。
そのため、長期間テレワークをおこなっている企業は、評価制度を改めたというところが多いです。
例えばある企業では、個々の仕事の目標と実現のための取り組みを可視化する、目標管理制度を導入しています。
また、クラウドシステムを導入して進捗を管理し、人事評価に役立てている企業も多いです。
そうすることで、社員の不公平感が減り、やる気の低下を防げ、テレワークでの業務を正当に評価できます。
テレワークに適した労働環境の整備
テレワークを軸とした働き方に変え、広いオフィスから小さなオフィスへ引っ越したという話を聞きます。
出社人数が減ると広いオフィスは不要となりますが、引っ越し先のオフィスでも従業員が働きやすいレイアウトにすることは大切です。
テレワークを継続している企業は、今まで個別のデスクだったものを、フリーアドレス化しオープンテーブルにしたり、作業に集中するための個室ブースを設けたりと、狭くなったスペースでも従業員が快適に仕事ができる空間を第一に考えています。
また、自宅で仕事をする従業員にWi-Fiの貸し出しや、インターネット通信料の負担をしている企業もあります。
以前オフィスで使っていた、デスクやチェアの貸し出しを行っている企業もあったりと、長期的にテレワークを行っている企業は、従業員の労働環境の整備を考えているところが多く見られます。
他にも、テレワーク教育を実施している企業もあります。
ITスキルは、従業員によって異なります。
オフィス出社が当然だった年齢層の従業員のなかには、テレワークに慣れない人もいるでしょう。
そのためチャットやビデオ会議ツール、クラウドツールの使い方など、テレワーク教育を実施している企業も多いです。
ツールの使い方やコミュニケーション方法などを学ぶ機会があると、苦手意識のある従業員もテレワークへの抵抗感が薄れます。
社内で研修を実施する人材を確保できない場合は、外部の専門家に相談するのも選択肢の一つでしょう。
業務ツールの見直し
感染症拡大によるテレワーク導入では暫定的に移行したため、オフィスワークの時に使用していたものが手元になく、生産性が下がったという企業は多かったと思います。
しかし、テレワークを主軸にした働き方に舵を切った企業は、今まで使っていた業務ツールを見直しています。
具体的には以下のようなツールを新規導入し、リモート環境でも業務が滞りなく進めるようにしています。
- チャットツール(Slack、Temas等)
- Web会議システム(Zoom等)
- クラウドストレージ
- クラウドPBX
- 勤怠管理システム
- 業務システムのクラウド版移行
他にも、注文書や請求書の電子化対応で、郵送物の抑制を行ったりと、様々な工夫を行っています。
ツールの導入においては、厚生労働省や経済産業省が主催している助成金制度を利用できます。

テレワークの今後は

長期間に渡ったコロナ禍という状況が、多くの企業にとって未経験の事態であったことで、一時的な対応でテレワークを導入したため、現状では廃止の動きが出ているということをお伝えしてきました。
そんなテレワークですが、今後も廃止の動きが高まるのでしょうか。
日本は少子高齢化等のさまざまな問題を抱えており、2025年や2035年には大きく変わるのではないかと言われています。
実は、厚生労働省は2016年8月に「働き方の未来2035」というものを公開しています。
2035年の技術や社会、働き方、制度がどう変化しているのかという考察になります。
内容としては、以前までは同じ空間・時間で仕事をしていたことにより、時間での評価が中心に行われていたが、今後は時間や空間に縛られない働き方になるため、時間での評価ではなく、実際の成果による評価が重要視されるのではないかと考察されています。
まさに「働き方の未来2035」の考察通り、現在テレワークを行っている企業は成果が重要視されている状態です。
SNSなどのコミュニケーションから、エンターテイメントに至るまで、日常で利用するサービスの多くがインターネットをベースとしている以上、オンラインを利用したテレワークという働き方が完全になくなることは想像しがたく、今後も選択可能な働き方が生まれていくと考えます。
また、企業にとっては、このような機会にこそ、その企業のコアの部分が表面化することになりますし、制度を見直しをしたり、実験・検証をしながら、組織を進化させていくチャンスにもなります。
現在、デジタル格差が広がっていることも懸念されていますが、自力では対応の難しい中小企業においても、テレワークを取り入れながら、会社の価値提供を継続していく必要があると考えます。
まとめ
今回は、企業のテレワーク実施の状況や、今後の働き方についてご紹介しました。
- テレワークの実施率は中小企業を中心に減少傾向にある
- テレワークを廃止する企業と継続している企業の差は環境整備
- 今後もテレワークは働き方の1つの選択肢となる