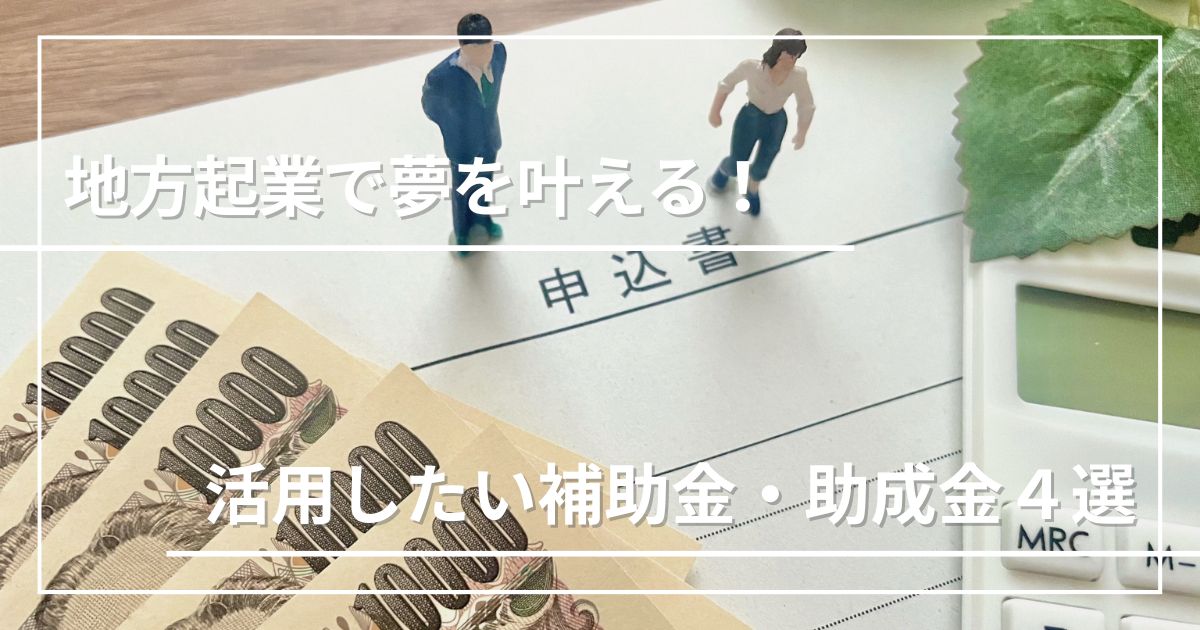若年層30~40代に注目を浴びている二拠点生活や地方移住。
しかし地方移住を考えた時、現役世代の私たちが真っ先に思い浮かぶのが仕事ではないでしょうか。
「地方で転職をするか、起業するか。」
また、中には
「地方移住をして古民家でカフェを開業したい」
と、最初から起業を考えている方もいるでしょう。
今回は、地方起業をする上で知っておきたいメリット・デメリットと、活用できる補助金・助成金についてご紹介します。
起業の種類

ひと口に「起業」といってもいくつか種類があります。
まずは大きく分けて、個人で事業を行う場合と、会社(法人)を設立する場合の2つパターンがあります。
個人事業主として起業する
個人で事業を起こす場合は、税務署に個人事業主として「開業届」を提出します。
個人事業主は、設立資金も必須ではないため比較的容易になれる分、法人格に比べて税制や社会的信用面等で不利になる可能性があります。
会社を設立して起業する
会社を設立する場合、事業内容や目的、資金調達方法等によって、更に4種類から選択することができます。
①株式会社
株式を発行して資金調達を行う会社携帯形態のこと指します。
出資者と経営者は別で、決算の公示が義務付けられており、社会的信用度が高いのが特徴です。
設立に掛かる費用は、収入印紙代(4万円)、定款の認証手数料(3~5万円)、謄本の発行手数料(約2千円)、登録免許税(約15万円)で22~24万円ほどかかります。
②合同会社
出資者と経営者が同一で、出資者全員が有限責任社員(会社の債務に出資額までの責任を負う社員)である会社形態のことを指します。
株式会社と違い簡易的なため、設立に掛かる費用は、登録免許税6万円、印紙4万円などを合わせて約10万円ほどで設立できます。
③合資会社
「有限責任社員」と、会社の債務に対し無制限に責任を負う「無限責任社員」とで構成される会社形態のことを指します。
設立に掛かる費用は、合同会社と同様で、登録免許税6万円、印紙4万円などを合わせて約10万円ほどで設立できます。
④合名会社
無限責任社員のみで構成されている会社形態のことを指します。
設立に掛かる費用は、合同会社と同様で、登録免許税6万円、印紙4万円などを合わせて約10万円ほどで設立できます。
地方起業のメリット

場所を問わずにできる「起業」ですが、地方起業ではどのようなメリットがあるでしょう。
ここでは地方起業のメリットをご紹介します。
メリット1:費用や固定費が抑えられる
起業するためには、登録免許税、定款認証、印紙代の他に、オフィスの契約・賃貸費、通信設備費、従業員の給料など、様々な費用が掛かります。
都会の場合オフィスの賃料や人件費が高くなりがちで、準備資金のハードルが上がってしまい、起業自体をあきらめてしまうケースも多くあります。
その点、地方起業する場合は都会での起業に比べて、主に土地と人に関わる費用を抑えることができます。
ランニングコストを抑えられることは、起業時だけでなく中長期な観点で利益を見込む上でも大きなメリットとなります。
メリット2:補助金を活用できる
国や地方自治体、各種行政法人等は、地方創生や地域経済活性化施策の一環として、地方移住後に起業する方への補助金給付等の支援を積極的に展開しています。
起業資金を一定額支給したり、税金の免除が受けられるなど支援内容は様々で、中には移住+起業で最大300万円の支援が受けられる制度も設けられています。
具体的な支援制度については、本稿内でご紹介します。
メリット3:競合が少ない
起業の成功ポイントは、他社が行っていない商品やサービスを提供し、できる限り多くの需要に応えることです。
都会では競合が多く埋もれてしまう事業も、地方に行けば競合が減り、地域ニーズを一手に引き受けられる可能性もあります。
競合他社との激しい顧客獲得競争から離れ、人と人との繋がりと信頼の中で仕事ができることも、地方起業のメリットの1つです。
地方起業のデメリット

前述で地方起業のメリットをご紹介しましたが、もちろん地方ならではのデメリットも存在します。
デメリット1:市場規模が小さい
一般的には人口が多い地域ほど需要も多く、人口が少ない地域では需要も限られる傾向があります。
そのため、都会では需要の高いサービスも、地方ではそもそもニーズが少なかったり、供給の方が上回っていて採算がとれない可能性が出てきます。
安定・継続して事業を行っていくためにも、移住して起業する場合は、「住みたい」という観点と同時に、提供予定のサービス・商品の需要があるかなど、暮らしとビジネスの両方の視点から地域を見る必要があります。
デメリット2:人材確保が難しい
人口の多い都会であれば人材確保はそこまで難しくありませんが、地方では好条件で求人を出していても応募者がいないといケースも少なくありません。
急に案件が増えた時や大きなチャンスが巡ってきた時にスムーズに対応するためにも、移住前から人材の目星をつけておくと安心です。
また、昨今ではクラウドソーシング等のフリーランスへの外注サービスがありますので、リモートで対応できる業務は積極的に活用するというのも一つの方法です。
デメリット3:最新情報を仕入れにくい
ネットやSNSを活用すればいくらでも情報を得られるように思われがちですが、人と会うことで得られる情報が新しいビジネスチャンスに繋がることが多々あります。
しかし、都会ほど同業者の交流会やセミナーが開催されていないことが多く、情報収集や人脈作りが難しいところがあります。
また、業界トレンドや最新のサービスは都会からスタートして地方に広がっていくため、地方にいながら最新の情報が得られるよう、移住前にビジネスに関わる情報網を築いておくと良いかもしれません。
地方起業を成功させるステップ

誰しも起業するからには成功させたいと思っているでしょう。
しかし起業は継続が難しいと言われており、起業3年以内に約4割の事業者が廃業するというデータもあります。
起業を成功させるには事前の準備が大事です。
ここでは準備に関するステップをご紹介します。
ステップ1起業の理由を明確に
起業を成功させるには起業の理由を明確にすることが重要です。
自分はなぜ起業するのか、起業することで何を実現したいのかなど、「起業する理由と目的」を様々な角度から掘り下げましょう。
明確な理由、目的を持たないまま起業してしまうと、次第にモチベーションを維持することが難しくなったり、トラブルや資金難等の困難に見舞われた際に事業を続けていく意義が見出せなくなりかねません。
ステップ2起業のアイデアをまとめる
起業の理由を明確にしたら、次はビジネスのアイディアをまとめていきます。
ビジネスは下記の4つが揃っていると成功しやすいと言われています。
- 自分が得意なこと・好きなこと
- 市場にニーズがあること
- 収益性があること
- 独自性があること
上記を基に様々なアイディアを考えていきましょう。
どんなビジネスをやるかが見えてきたら、次にペルソナの設定をします。
具体的には、
- 誰に(ターゲット)
- 何を(商品・サービス)
- どのように(提供方法)
ということを、それぞれの項目毎にできる限り具体的に考えます。
ターゲットの年齢層や性別、興味・関心、抱えている課題等に訴求するために、どのような商品やサービスを、どのような方法で提供すれば喜ばれるのかを明確にすることで、事業全体の方向性が定まり、その後のステップが見えやすくなります。
ステップ3事業計画書を作成する
事業計画書とは、これからどのように事業を展開するのか具体的に示したものです。
アイディアを元に計画書をまとめることで、事業展開に向けた行動を具体化できるようになります。
また、融資を得たい場合や補助金申請をする場合も、事業計画書があることで説明しやすくなるため、計画書は起業に必要不可欠だといえるでしょう。
事業計画書は、具体的な数字や計画のほか、事業の概要やビジネスモデルなどを細かく記載するのがポイントです。
なお、主な事業計画書の内容は以下の通りです。
- 企業概要
- 事業理念・目的・ビジョン
- 事業内容
- サービスの強み・特徴・独自性
- 販売・マーケティング戦略
- 競合他社比較
- 販売訴求方法・経路
- 事業上の問題点・解決策
- 組織・人員計画
- 資金計画協力者・支援者
- 売上や利益の見込み・計画
ステップ4起業の準備
事業計画書を作成したら、次は事業を始めるのに必要な資金や人材、オフィス、各種備品を準備します。
開業資金については、設備・事業資金とランニングコストを合算し6カ月分ほどを準備しておくのが一般的です。
人件費は、月給のほか、労災保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料などが掛かります。
オフィスのテナント代や水道光熱費、通信費、移動費、広告宣伝費、消耗品費なども考慮の上、損益計算をして月の最低売り上げ高を設定し、必要に応じて事業計画書の見直しと修正を行います。
ステップ5起業手続き
起業準備が整ったら、開業するための手続きを行います。
■個人事業主として起業する場合
- 開業届(個人事業主の開業・廃業等届出書)の提出
- 個人事業主として起業する場合は、税務署長に「開業届」を提出すれば完了です。
- 青色申告承認申請書の提出
- 青色申告を行う場合は、起業後に「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
青色申告とは確定申告の一種で、最大65万円の特別控除が受けられるなど節税メリットを得ることができる申告種別です。
■法人設立して起業する場合
- 基本事項の決定
- 屋号や会社員、役員報酬、資本金を決定します。
- 定款作成
- 定款とは「会社を運営していく上でのルール」をまとめたものです。
- 資本金の払込み
- 資本金は1円でも良いとされていますが、一般的な目安は100万円です。
- 登記書類作成
- 代表的なものとしては、定款、登記事項証明書、株主名簿、設立趣意書、設立時貸借対照表などが挙げられます。
- 法務局への登記申請
- 資本金払込後2週間以内に、原則として会社の代表取締役が法務局へ登記申請を行います。
- 登記後の各種行政などへの手続き
- 税務署や都道府県及び市町村、年金事務所、労働基準監督署、公共職業安定所等への各種申請を行います。
ステップ6事業をスタートする
各種届出が受理されたら、いよいよ事業のスタートです。
順調にビジネスが進めば良いですが、初めは失敗や悩みがつきものです。
必要に応じて従業員を増やしたり、場合によっては新たな資金調達も必要になることがあるため、事業開始後も工夫を凝らしながら事業を進めていくことが必要となります。
もしも上手くいかない場合は、ステップ1の起業理由や目的に立ち返ったり、ステップ2で考えたペルソナや市場ニーズの再精査など、課題に対応しながら乗り越えていきましょう。
利用する前に助成金・補助金を知ろう
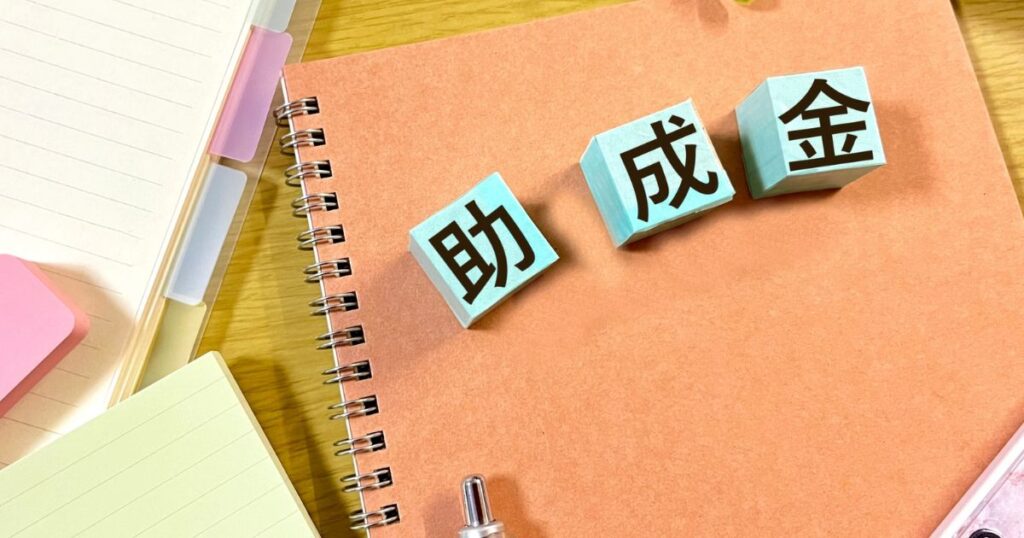
起業するにあたって賢く利用したいのが国や自治体の助成金や補助金です。
しかし、いまいち違いがよくわからないという方のために、ここでは助成金と補助金についてご説明します。
助成金と補助金は原則返済不要
補助金・助成金とは、公益上必要があると政府が判断した場合、民間もしくは政府に対して交付する金銭的な給付金のことです。
融資とは違い、補助金・助成金は原則的に返済不要なことが特徴です。
創業時、融資による資金調達は、起業時に必要な資金をすぐに調達できるため活用する人も多いですが、融資はあくまで借入れです。
いずれ、利益の中から返済しなければなりません。
補助金・助成金を活用できたなら、原則的には返済が不要な資金を事業に活用できるということになります。
助成金や補助金は、提示された要件に合う種類のものを探すのではなく、要件に合わせて事業をうまく再設計することが重要です。
そのためにも、助成金や補助金に関してしっかり理解することが必要です。
助成金と補助金の違いとは?
補助金と助成金には、以下のような特徴があります。
■補助金
補助金の特徴
- 受給の難易度が高い
- 給付額は数百万円~数十億円
- 申請手続きが大変
- 財源は税金
補助金の注意点
- 申請期間が短い場合が多い
- 予算が決まっている場合が多い
- 採択されても給付までに時間がかかる
- 補助は事業に対する一部の費用のみのことも
補助金は予算の関係上、採択の上限が確定していることが多く、申請しても受給できない場合も少なくありません。
そのため受給難易度は高めとなっています。
また、補助金の募集先は経済産業省や地方自治体で、財源は税金となるため申請数の枠が限られている場合が多く、結果的に難易度が高くなっています。
■助成金
助成金の特徴
- 条件に合っていればほぼ受給できる
- 給付額は数十万円~高くても百万円
- 募集期間が長い
- 財源は雇用保険
助成金の注意点
- 雇用保険加入従業員が1名以上いる
- 書類に問題があれば修正が入る
- 人気の助成金は早期終了の恐れあり
- 労働関連法規に違反しないこと
助成金は厚生労働省による給付が多くなっており、財源は雇用保険料です。
また、雇用を促す目的から国や地方公共団体からの募集もあります。
助成金はある一定の要件を満たすことで支給されるものなので、基本的には随時募集されているものが多く、募集期間が長めという特徴があります。
地方起業向け補助金・助成金4選【2023年版】

前述で補助金・助成金の違いをご説明しました。
ここでは地方起業に活用したい補助金・助成金を4つご紹介します。
①地方創生起業・移住支援金
東京圏から地方で起業する方を対象に、内閣府が都道府県や市町村通して支援する形で、起業支援金最大100万円(単身者は最大60万円)と移住支援金最大200万円を給付しています。
■起業支援金
起業支援金の対象者
次の①~⑥全てを満たす必要があります。
- 東京圏以外の道府県又は東京圏内の 条件不利地域において社会的事業の起業を行うこと
- 公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、個人開業届又は法人の設立を行うこと
- 起業地の都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること
- 東京圏以外の道府県又は東京圏の 条件不利地域において、Society5.0関連業種等の付加価値の高い分野で、社会的事業を 事業承継又は第二創業により実施すること
- 公募開始日以降、補助事業期間完了日までに、事業承継又は第二創業を行うもの
- 本事業を行う都道府県内に居住していること、又は居住する予定であること
最大給付金
100万円(単身者は最大60万円)
■移住支援金について
移住支援金の対象者
- 移住元:東京23区の在住者または東京圏から東京23区へ通勤している者
- 移住先:東京圏以外の道府県又は東京圏の条件不利地域への移住者(移住支援事業実施都道府県・市町村に限る)
- 就業等:地域の中小企業等への就業やテレワークにより移住前の業務を継続、地域で社会的起業などを実施していること
最大給付金
200万円
②地域雇用開発助成金
地域雇用開発助成金とは、特定の地域にて事業所を設置・整備し、その地域の求職者を雇用した事業者に支給されるお金です。
地域雇用開発助成金の対象者
この助成金は主に以下のような地域での雇用を行った事業者が対象です。
- 同意雇用開発促進地域(求職者に比べて求人が著しく不足している地域)
- 過疎等雇用改善地域(働きざかり世代に該当する青年~壮年期の流出が顕著な地域)
- 特定有人国境離島等地域
最大給付金
48万円~960万円
これらの地域に新しく事業所を設置し、雇用保険適用事業所の届出や従業員の雇用保険に関する届出を行う事業所の設置・整備費用や雇用人数に応じて定められた助成金が支給されます。
③創業促進補助金
創業促進補助金とは、地方公共団体が独自に創業する事業主に提供している補助金です。
創業促進補助金はその地域によって名称が異なります。
下記は一例です。
■茂原市創業支援補助金(千葉県)
創業支援補助金の対象者
- 申請年度内に開業するかまたは申請時点で開業届の提出から5年以内の個人事業主または法人
- 市内に事業所を設置するかしようとしていること
最大給付金
30万円以内かつ対象経費の2分の1以内
※開業申請にかかる経費、事業所等の借入費、設備費用、広告費など
④IT導入補助金
IT導入補助金とは、主にサービス業の個人事業主や中小企業が生産性向上のために導入するITツールやソフトウェアの導入費用に対して支払われるお金です。
主なサービス業は飲食業、宿泊業、小売・卸業、運送事業、医療・介護・保育等です。
支給対象となる経費
- IT導入補助金の支給対象となる経費
- ITツール(ソフトウェア・サービスなど)
- デジタル化基盤導入枠の場合、ITツールと併用するハードウェア(PC・タブレット・レジ・券売機など)も対象
最大給付金
・通常枠30~450万円
・デジタル化基盤導入枠5~350万円
補助金・助成金を利用する際の注意点

各種支援金を活用するにあたって、事前に考慮してしておきたい注意点をご紹介します。
補助金は後払い
補助金は後払い制が基本です。
例えば総額500万円の事業で1/3の補助がある場合は、まず自社の資金から500万円を支払い、対象期間内に証明書とあわせて補助申請する必要があります。
対象期間に注意
事業期間内に支出した経費以外は経費として認められず、補助を受けられないこともあります。
例えば、事業期間が2月28日までなのであれば、3月1日以降の支出については補助を受けることができません。
また、事業期間は公的機関の繁忙期である年度末を避けて設定されているケースが多いので注意が必要です。
申請書類の不備に注意
事業期間終了後、一定期間内に報告書や支払証明を提出する必要があります。
書類に不備がある場合や真偽が疑われる場合は、支援金を受けられない可能性がある他、会計検査院の検査が入るケースもありますのでご注意ください。
常に最新情報を確認
補助金・助成金はどんどんと新しい制度が出てきたり、なくなったりします。
そのため、常に最新情報を確認した上で申請しましょう。
また、全体的な傾向や、政府が補助金・助成金についてどう考えているかを知ることも、受給を考えるにあたっては重要になってきます。
まとめ
今回は地方起業をする上で知っておきたいメリット・デメリットと、活用できる補助金・助成金についてご紹介しました。
- 地方起業ならではのメリットとデメリットを理解
- 起業するには準備やステップが重要
- 補助金・助成金の情報は常に最新をチェック