別荘地に代表される軽井沢や那須、八ヶ岳。
夏は涼しく、避暑地として今でも人気のエリアです。
夏の利用をメインとして避暑地エリアで別荘やセカンドハウスを購入したいと考えている人は多いかと思います。
しかし、夏しか利用をしない場合でも、避暑地ならではの冬の対策が必要です。
また、せっかく購入した別荘・セカンドハウスですから1年を通して利用したいという方もいるでしょう。
都会とは違う避暑地ならではの特性があるため、快適に過ごすためには都会とは違った冬の対策が必要です。
そこで今回は、冬の別荘でやっておきたい対策と快適に過ごす方法をご紹介します。
人気別荘地の冬は寒い

夏を涼しく過ごせるとして、軽井沢や那須、八ヶ岳など山・高原の避暑地は人気の別荘エリアです。
しかし、夏が涼しいということは冬は寒く、降雪があるということになります。
夏の快適な気候とは裏腹に、避暑地の冬は厳しい気候で朝晩は特に冷えこみます。
気象庁のデータによると、避暑地の別荘として人気の軽井沢における2月上旬の最低気温はマイナス9℃。
中部の盆地になると朝の最低気温がマイナス15℃になることもあり、北海道並みの寒さになります。
また一部の別荘は、夏の利用を想定しているため、冬の寒さに対する対策が不十分な場合があります。
冬場の利用を考慮していないため、寒さが室内に侵入しやすくなります。
更に人気の別荘地のほとんどが築年数の古い建物となっており、十分な断熱設備を持っていない場合があります。
断熱材の不足や古い窓やドアのシーリングが劣化していると、室内の暖房が逃げやすく部屋全体が冷え込みやすくなっていることもあります。
別荘で冬に気をつけること

夏だけの利用であっても、冬場も別荘で過ごす場合でも別荘を所有している場合は冬の期間に気をつけるべき点があります。
以下に、気をつけるべき点をまとめました。
①水道管の凍結・破裂
気温が氷点下を下回ると、水道管の中の水が凍結し、水道管を破裂させてしまうことがあります。
特に、気温がマイナス4度以下になると、凍結・破裂する可能性が非常に高くなると言われています。
他にも、真冬日(氷点下)の日が数日続いたときや、冬場に水抜きしないまま長期間水道を使用しなかったときに凍結しやすくなります。
また、屋外にある蛇口や露出した水道管や、北向きの風通しのよいところにある水道管は更に凍結しやすくなっています。
標高の高い別荘地の場合は、平地よりも気温が低く、木などによって日当たりが悪いため実際の外気温は低くなりやすいです。
水は凍結すると、体積が約9%増加します。
上水道の水道管内は、浄水場から常にポンプで圧力がかけられており、水道水で満たされています。
その水道管内に満たされた水が凍ってしまうと、元々圧力がかけられて水が逃げ場を失っている状態で体積が9%増え、水道管の耐えられる膨張率を超えてしまい、水道管が破裂してしまうというわけです。
水道管が破裂すると室内への水漏れが発生し、壁やクロスが剥がれる、床が浸水するなど建物への影響が大きい上に、室内の電気配線が濡れてしまうと重大な事故につながる懸念があるため、冬場の別荘において一番気をつけるべき点となります。
②降雪による建物への影響
人気の避暑地は降雪地帯であることが多く、場合によって人間の身長を超える高さまで雪が積もることもあるため、まずはしっかりと地域や近隣の土地の傾向を知っておきましょう。
都市部に住んでいると雪は非常に軽いものというイメージがあるかもしれません。
しかし、雪が降り積もることにより固くなった状態では、1㎡あたり約250~500kgの重量になると言われています。
つまり、雪が降り続けばその分、建物への負担も大きくなっていくということです。
実際に関東地方にある体育館で、積雪によって屋根が崩落したという被害が過去に発生しています。
体育館ほどの大きな建物となれば、鉄骨造で建てられるため強度は十分にあります。
しかし、降り積もった雪の重みで屋根だけが耐えられなくなり、最終的に崩落してしまう可能性があるのです。
屋根から落ちる雪は建物の出入りの妨げになる場合もあります。
そのため、別荘のある地域によっては雪かき、雪下ろしが必要になってくるでしょう。
③室内の寒さ
夏は涼しくて過ごしやすいという理由で人気の避暑地ですが、冬の楽しみもあります。
夏に比べて観光客も少なく、雪景色をゆっくりと眺めるのも良いものです。
しかし、避暑地に別荘を持っている方から多く聞かれるのが、
「こんなに冬が寒いとは思わなかった」
という声です。
避暑地の別荘では建物構造が寒さを考えられているものも多いですが、コテージ、ロッジ風の建物や、古い物件の場合は室内が驚くほど寒いということもあり得る話です。
また、人気別荘地の軽井沢や、東京から近い埼玉の秩父の山間部では移動時間こそ1時間程度ですが、実は北海道の札幌より冬の気温は低く、10月ごろから暖房が必要となります。
そのため、都市部の暖房設備と同じようにエアコンだけでは冬を快適に過ごすことはできず、複数の暖房設備を用意する必要があります。
他にも、室内で過ごす衣服を雪国仕様にするなど工夫が必要となるでしょう。
冬が来る前に別荘でやっておきたい対策

前項では冬の別荘で気をつける点をご紹介しました。
ここでは気をつける点を踏まえて、本格的に冬が来る前にやっておきたい対策についてご紹介します。
①水抜き・水出し
水抜きとは建物に関わる水道管内の水を抜く作業をさします。
気温が氷点下を下回ると、水道管の中に残った水が凍結し、水道管を破裂させてしまうことがあります。
夜中の気温が氷点下になる可能性がある日から、水抜きの作業が必要になります。
凡そ12~2月の間がその時期にあたるでしょう。
しかし、標高が1000mを越えるような避暑地であれば、10月下旬から氷点下になる日が出てきます。
水抜き作業を行う際は、道路から引き込まれている水栓を閉めることで新たに水が入ってこないようにした上で、蛇口などを開けっ放しにして水道の水を全部出します。
もし、配管が複雑で水が抜けきらない箇所がある場合は、不凍液で満たすなどの作業を行います。
水回りはすべてこの作業が必要になるため、お風呂やキッチン、トイレも忘れずに対策が必要です。
水抜きができておらず破裂してしまうと、家が水浸しになってしまうケースもありますので、しっかりと対策をしましょう。
水抜きをした水道管を再度利用する際には、「水出し」作業を行います。
作業手順は水抜きと逆に水道の元栓を開け、水道管に水を流し込んでから蛇口を開きます。
②凍結防止ヒーター
冬場に別荘滞在中は、夜眠るときや暖房を切って別荘を離れるときに「凍結防止ヒーター」のスイッチを入れておきましょう。
「凍結防止ヒーター」は水道管が凍結してしまわないよう、巻きつけた電熱線で水道管を暖める仕組みです。
暖房をつけて過ごしている間は水道管が凍る心配はないので、「凍結防止ヒーター」を切っても大丈夫です。
ただ、別荘から帰宅する際には「水抜き」が、自宅から別荘に到着したときは「水出し」がやはり必要になります。
一晩で水道管は凍ってしまうので、気をつけましょう。
また、ヒーター線も古くなると効きが悪くなってきます。
寿命は約10年程度と言われているため、ご自身の別荘に取り付けられている凍結防止ヒーターの年数を確認してみましょう。
③積雪の対策
降雪のある地域では、建物への雪の影響も対策しておく必要があります。
例えばバルコニーの途中までしか屋根がない場合には、屋根から落ちた雪でバルコニーが壊れたり、積もった雪が痛みの原因になる場合があります。
そういったバルコニーや、雪が吹き込んでほしくない玄関等には「防雪シート」を設置しておくと良いでしょう。
もしも雪を原因とする家への損傷があっても、雪害ということで保険の対象となる場合が多いので、購入の際には忘れず加入しておくと更に安心です。
また、降雪の時期に別荘を利用する場合は、路面が凍結して滑りやすくなっているため、車は冬装備(スタッドレスタイヤやタイヤチェーン)にしておく必要があります。
出かける際の靴も滑りやすい靴を避け、転倒などケガがないよう気をつけたいところです。
別荘の敷地内は、自身で雪かきをすることになります。
積雪量によっては屋根に積もった雪下ろしが必要な場合がありますが、転落の危険もあるため慣れていない場合は無理をせず有償で行ってくれるところへ依頼することも考えましょう。
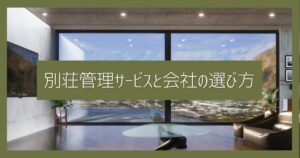
冬の別荘を快適にする設備

ここでは冬の別荘を快適に過ごすための設備についてご紹介します。
別荘をこれから購入する人や、既に所有している人もリフォームの参考にしてみてください。
断熱材
室内の暖かさを保つには、断熱材が重要となってきます。
「中の暖かい空気を外に漏らさず、外の冷たい空気を室内に入れない」が基本。
素材によっては、保温だけでなく防音性や耐火性、防虫・防カビ性が高まるといったメリットもあります。
断熱材にはさまざまな種類がありますが、大きく「繊維系」「天然素材系」「発泡プラスチック系」の3つに分類することができます。
①繊維系
主に化学繊維のグラスウールや木質繊維のセルロースファイバーなどがあります。
グラスウールは比較的安価ですが湿気などに弱く、性能が低下してしまう可能性があります。
セルロースファイバーは価格が高い点はありますが、断熱性が高く、環境負荷が低いという特徴があります。
②天然素材系
羊毛や炭化コルクなどが代表的で、近年はさまざまな素材が商品として販売されています。
環境や人体への負荷が少ない半面、断熱性能の割には高価な点がやや欠点となります。
③発泡プラスチック系
押し出し発泡ポリスチレンやウレタンフォーム、高発泡ポリエチレンなどが代表的な断熱材です。
厚さに対して断熱性能が高く、防湿性にも優れているものが多いです。
しかしグラスウールなどに比べてコストがかかってしまう傾向にあります。
樹脂窓(樹脂サッシ)
日本の住宅では寒冷地を除き、窓のサッシにアルミを使用している住宅が多くあります。
しかしアルミは熱伝導率が高く、外の冷気や熱を室内に通してしまいます。
そのサッシを樹脂製に変えることで、断熱効果を高めることが可能になります。
樹脂サッシの断熱性能はアルミの1000倍とも言われており、屋内の熱が逃げるのを防いでくれます。
この樹脂サッシと合わせて、2枚のガラスを使用し間に密閉された中空層を持つ「ペアガラス」取り入れることで、更に断熱効果が期待できるでしょう。
薪ストーブなどの暖房器具
避暑地のような寒冷地はエアコンといった暖房設備だけでは室内が寒いことがあります。
そのため、エアコン以外の暖房器具を用意したいところです。
そこでおすすめなのが「薪ストーブ」です。
都市部の暮らしではなかなか難しい薪ストーブを導入できるのは、別荘ならではと言えるでしょう。
「部屋の中で揺れる炎を見ながら、のんびりした時間を過ごす」
という暮らしに憧れを抱いている方も少なくないはずです。
薪ストーブはインテリアとしての存在感もさることながら、他の暖房器具とは違い遠赤外線効果によって身体の芯から温まることができます。
しかし薪ストーブは温まるまでに時間がかかるため、ファンヒーターや電気ストーブなどの暖房器具との併用が欠かせません。
冬ならではの別荘を楽しもう
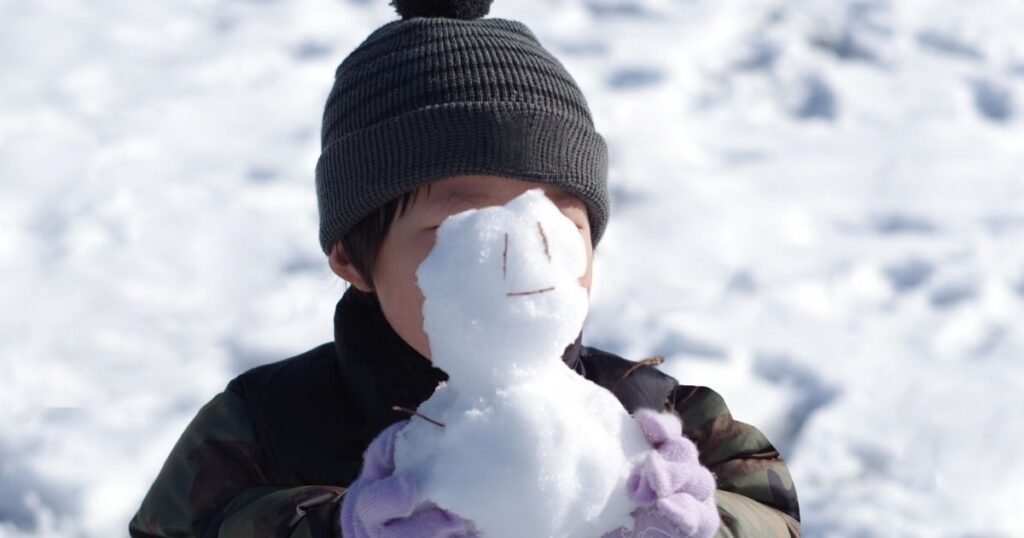
避暑地の別荘では、冬は美しい雪景色を楽しむことができます。
雪が積もった庭や周囲の景色を眺めながら、静寂の中でリラックスするのも良いでしょう。
また、雪遊びや雪だるま作りなど、子供と一緒に外で雪を楽しむということもできます。
他にも、別荘の暖炉や薪ストーブで暖を取りながら、家族や友人とくつろぐのも冬の別荘ならではの過ごし方です。
暖炉の火を眺めながら読書したり、対話を楽しんだりすると、冬の寒さを忘れて心地よい時間を過ごせます。
冬の別荘滞在は、夏とはまた違った魅力があるものです。
まとめ
今回は、冬の別荘でやっておきたい対策と快適に過ごす方法をご紹介しました。
- 避暑地ということは冬は降雪地帯でもある
- 冬に利用をする場合もしない場合も、建物への対策が必要
- きちんと対策をして冬の別荘も楽しもう

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!

