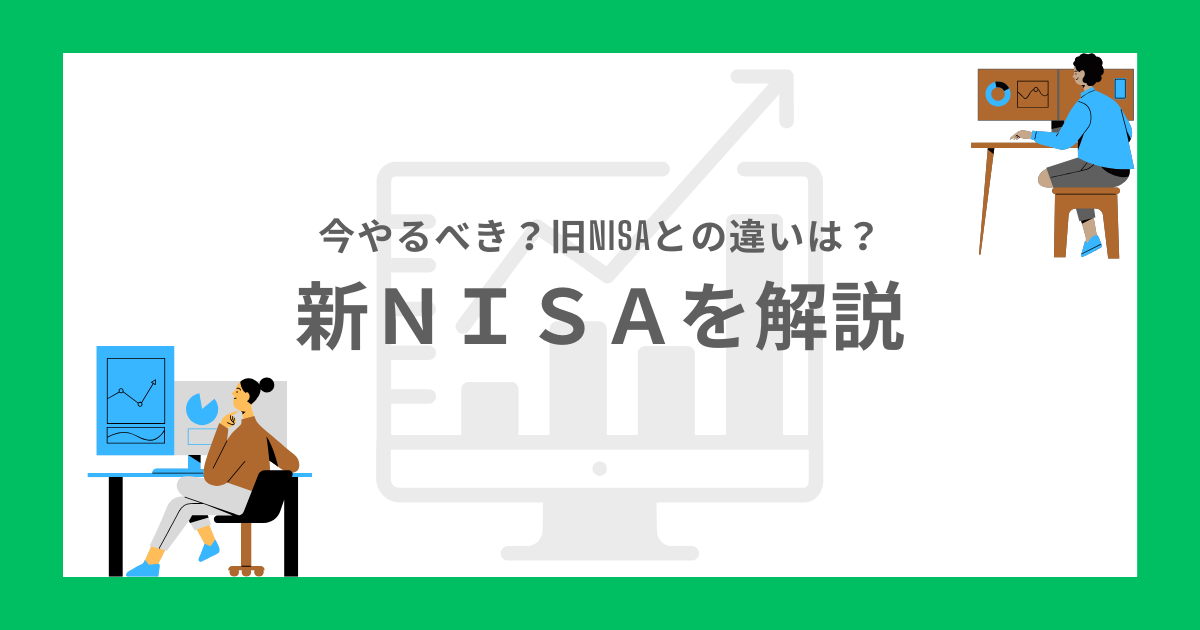2024年から新NISAが始まり、これまでのNISAよりも非課税枠が拡充、さらに非課税で投資できる期間も恒久化されるなど、メリットが大きいと投資家の間でも話題になりました。
またメディア等でも大きくとりあげられているため、これをきっかけに運用投資を始める人も増えています。
「NISAは知っているけど、あまりお得感がない」
「投資商品に手を出すのはちょっと・・・」
という方に向けて、今回はNISAとはどういった制度なのか、旧NISAと新NISAの違いやメリット、始める際に注意しておきたい点を解説します。
NISAとは

NISA(ニーサ)は、少額からの投資を行う方のために2014年1月にスタートした「少額投資非課税制度」です。
イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)をモデルにした日本版ISAとして、NISA(ニーサ・Nippon Individual Savings Account)という愛称がつけられました。
金融庁-NISAとは
個人で証券口座を開設し、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、売却益や配当に対して約20%の税金を払わなければなりません。
一方で、NISA口座で投資した金融商品から得られる利益は非課税になります。
ただしNISA口座で投資できる上限金額は決まっています。
NISAは投資初心者や、幅広い年代の方の資産形成をサポートする制度として、始める人が増えています。
NISAを始めるには
まず、NISA(新NISA)を始めるにはNISA口座の開設をする必要があります。
また、1人が持てるNISA口座は全ての金融機関を通して1つと決まっています。
そして、NISA口座には2つの投資枠があり、選べる商品が多い「成長投資枠」と、投資信託を毎月積み立てる「つみたて投資枠」で構成されています。
それぞれの投資枠には上限額が設けられており、NISAで年間に投資できる額は、つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円、合わせて360万円が上限額です。
また、どちらの枠も合わせて総額の非課税保有限度額は1,800万円となっています。
しかし、投資して消費した非課税保有限度額は、売却することで復活し、翌年以降に再利用することが可能です。
新NISAと旧NISAの違い

新NISA制度は2024年1月から始まりました。
旧NISAとの違いは、旧制度が「一般NISA」と「つみたてNISA」に分かれていて、どちらか一方にしか投資が出来なかったのに対し、新NISAでは「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つを併用して投資をすることが可能です。
◆旧NISA
| 旧NISA | ||
| 一般NISA | つみたてNISA | |
| 併用の可否 | 併用不可 | |
| 非課税保有期間 | 5年間 | 20年間 |
| 口座開設期間 | 2023年まで | |
| 年間投資枠 | 120万円 | 40万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 | 800万円 |
◆新NISA(2024年1月~)
| 新NISA | ||
| 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
| 併用の可否 | 併用可 | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 口座開設期間 | 恒久化 | |
| 年間投資枠 | 240万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 | 1800万円 (内、成長投資枠は1200万円まで) | |
また、旧NISAでは、非課税期間が「つみたてNISA」で20年間、「一般NISA」で5年間となっていましたが、新NISAでは、非課税で運用できる期間が無期限になりました。
他にも、旧NISAと比べ新NISAでは年間の投資枠や非課税保有限度額が大幅に広がったため、長期的な資産運用により活用しやすくなったと言えます。
新NISAのメリット

続いて、新NISAを始めるメリットは何かを解説していきます。
メリット1 非課税で運用できる
まず一つ目のメリットは、1800万円までの投資で得られた運用益が非課税であることが挙げられます。
これは、投資した1800万円が長期運用により5000万円となり、それを売却するとなった場合に3200万円の運用益が出ても税金がかからないということになります。
ちなみに、一般的な株式や投資信託であった場合約640万円の税金がかかってきます。
また、投資の運用益には値上がり益だけでなく配当金や分配金もあります。
新NISAを利用した投資であれば、そうした配当金や分配金にも税金はかかりません。
メリット2 つみたて投資枠の商品は厳選されている
つみたて投資枠の商品は、金融庁の定める基準を満たし、届け出が行われた投資信託・ETFのみとなっています。
2024年1月時点で、購入可能な投資信託の商品数は約6000本ありますが、新NISAつみたて投資枠の商品は、いずれも「長期・積立・分散投資」を軸とした商品約280本に厳選されています。
これから投資を始める人にとって多くの投資信託から銘柄を選ぶのは非常に難しいことです。
そのため、リスクの高い商品を選んでしまう心配がない点が、つみたて投資枠のメリットと言えます。
メリット3 成長投資枠では自由度の高い投資が可能
新NISAの成長投資枠では、上場株式、ETF、REIT、投資信託と幅広い商品の中から選んで投資することが可能です。
投資信託についても、つみたて投資枠にはない商品に投資することも可能です。
新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠を併用することができるため、例えば、「長期的に老後資金を貯めたい分はつみたて投資枠、短期的に利益を狙いたい分は成長投資枠を使う」という使い分けも可能です。
ただし、二つを併用した場合でも、非課税保有限度額は総額で1800万円となっているため、気をつけましょう。
メリット4 非課税枠は売却後、翌年に枠が復活
新NISAでは、口座内の資産を売却すると、買付価額分の非課税枠が翌年以降に復活します。
例えば、非課税保有限度額である1,800万円を使い切った状況だと、非課税で追加投資することができません。
しかし、買付価額ベースで500万円分を売却すると、翌年以降、500万円分の非課税枠が復活します。
また、新NISAは、いつでも口座内の資産引き出すことができるため、住宅購入、教育資金、余暇資金など、さまざまな用途でお金を貯めることに適しています。
非課税枠が復活することもあり、必要な時に資金を引き出し、翌年以降に非課税枠内で再投資することによって、流動的な資産運用が可能とも言えます。
新NISAの注意点
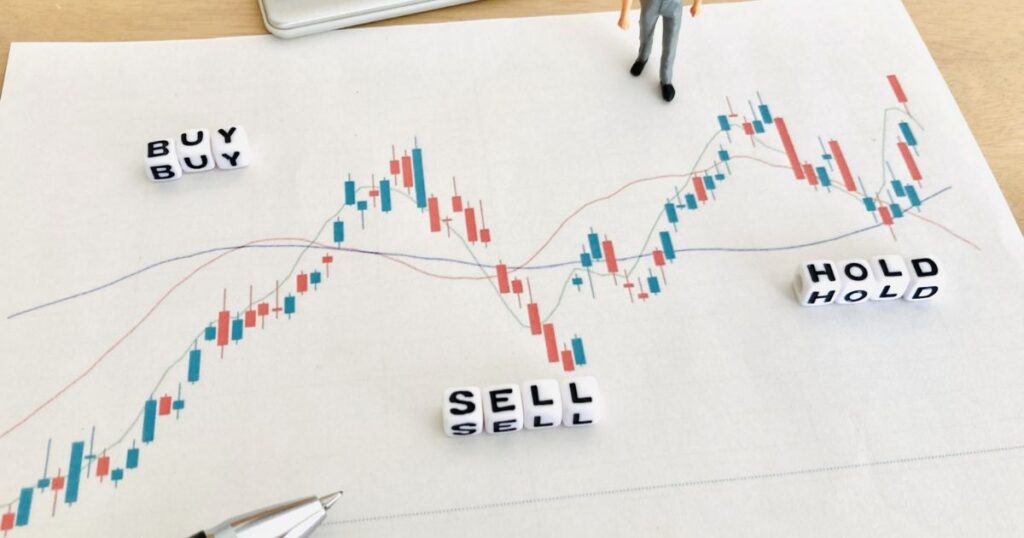
新NISAはメリットの多い制度ではありますが、デメリットがないわけではありません。主なデメリットを紹介します。
注意1 元本割れのリスクがある
メリットが多く、さまざまなメディアでも「やるべき投資」として取り上げられることの多い新NISAですが、銀行預金とは違い、株式や投資信託などの商品に投資するため元本割れのリスクがあります。
また、新NISAの投資信託商品の中で、現在は米国株価指数「S&P500」が人気ですが、運用成績はその年によって大きく変動するため、短期投資の場合は必ずしも利益が出るとは限りません。
しかし、長期間投資することで下落リスクが少なくなるため、10年・15年と長期的な投資に向いていると言えるでしょう。
注意2 損益通算・繰越控除ができない
一般的な株式投資等の場合、複数の口座で生まれた利益と損失を合算する「損益通算」という仕組みがあります。
また、損益通算しても損失があるときに最大3年間その損失を繰り越して、翌年の利益から差し引くことができる「繰越控除」があります。
どちらも、投資の利益にかかる税金の負担を減らす仕組みですが、新NISAは損益通算や繰越控除の対象外となっている点に注意が必要です
注意3 旧NISAからのロールオーバーはできない
旧NISAの一般NISAではロールオーバーができましたが、新NISAではロールオーバーができません。
ロールオーバーとは、5年間の非課税期間が満了した後に、翌年のNISA非課税投資枠に移管させることでさらに5年間、非課税で運用できる制度のことです。
ロールオーバーすれば、最長10年間にわたって非課税で運用できるメリットがあります。
新NISAではそもそも非課税期間が無期限となることから、ロールオーバーができない点については問題とならないでしょう。
しかし、旧NISAと新NISAは別制度という考えのため、すでに一般NISAを利用している場合、一般NISA枠の投資はそのまま旧NISAとして運用され、新NISAへそのまま移行できないという点には注意が必要です。
もし、旧NISAで運用中の商品を新NISAで運用したい場合は、一旦、売却して新たに新NISAで購入する必要があります。
注意4 売却後の非課税枠復活には注意が必要
新NISAのメリットで、資産を売却すると、買付価額分の非課税枠が翌年以降に復活するとお伝えしました。
しかし、どれだけ資産を売却しても、年間の非課税枠は「成長投資枠」の240万円と「つみたて投資枠」120万円と決まっているため、それ以上の資産を売却しても、翌年度の年間の非課税枠は最高360万円のため、注意が必要です。
新NISAの運用ポイント

新NISAを活用して資産を運用するには、運用する際の心構えも大切です。
ここでは、新NISAの運用ポイントについて解説します。
目標や目的を設定する
新NISAの活用にあたり、資産運用の目標額や行う目的をきちんと設定することが大切です。
例えば「セカンドハウスの購入資金を貯めたい」「老後資金を準備したい」など、目的と運用期間によって、リスク許容度が異なってくるためです。
新NISAは、これまでのNISAよりも資産運用の自由度が高くなります。
さまざまな目的に対応できることから、「自分は何のためにいくら必要なのか」「いつまでに、いくら用意したいのか」といったゴールを決めることで、運用商品や運用方法が変わってくるでしょう。
長期運用、分散投資を
投資は、長期的な運用と、投資する対象や時期を分散させることが大事です。
長期的に資産運用をすると、運用成績が平準化されて安定的な利益が期待できます。
また、一つの金融商品に絞らず、さまざまな金融商品に分散投資することもリスクを軽減する上で重要です。
まとめ
今回はNISAとはどういった制度なのか、旧NISAと新NISAの違いやメリット、始める際に注意しておきたい点を解説しました。
- NISAとは「少額投資非課税制度」のこと
- 旧NISAに比べ、新NISAは投資額や非課税保有限度額が増額された
- 新NISAはこれから投資を始める人、長期運用にオススメ