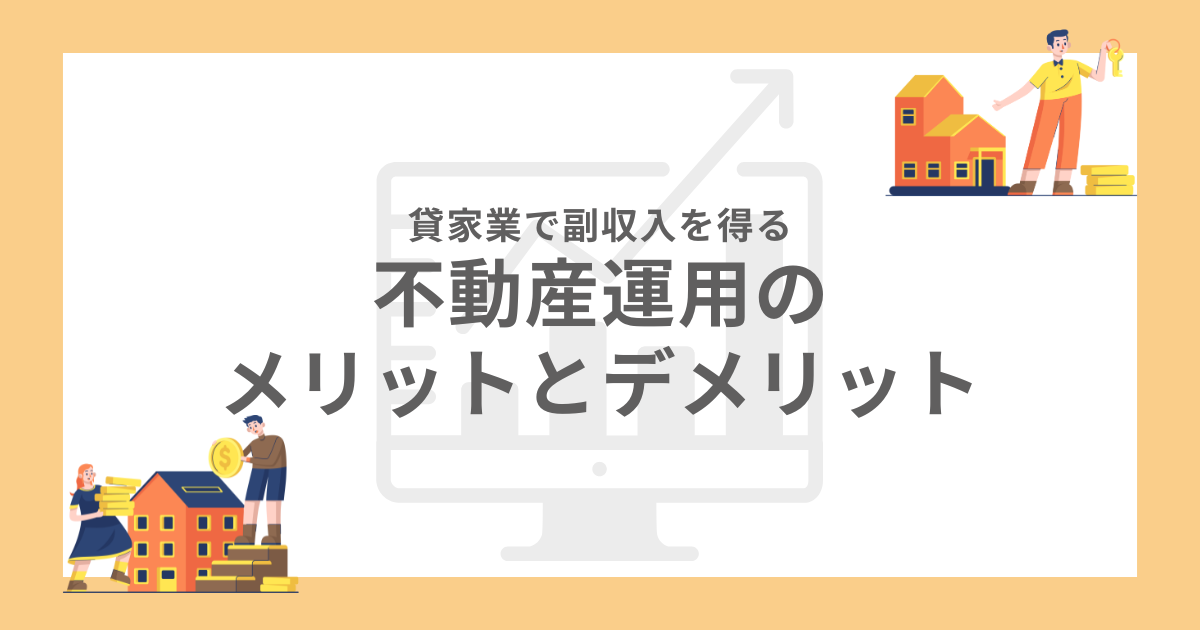昨今、会社員でも堅実に運用ができると「不動産運用」が注目を集めています。
二拠点生活を始めるための資産形成にも有効な手段といえます。
一方で、不動産の資産運用と聞くと「ハードルが高い」、「騙されそう」と思われる方も多いでしょう。
不動産運用には利益が出る以外のメリットもありますし、もちろんリスクもあります。
今回は不動産運用のメリットやデメリット、安定して運用するためのポイントをご紹介します。
不動産運用とは

不動産投資とは、不動産を購入しそれを他人に貸すことで家賃収入を得ることが主目的の投資です。
主に老後の年金対策として注目を集めていますが、二拠点生活をしている人の中には貸家業で拠点先の費用を賄う方法として運用している人もいます。
運用と聞くと預貯金や株式、債券、投資信託といった金融商品が一番思い浮かべやすいでしょう。
不動産はややハードルが高いと感じることもありますが、これらを活用して金銭的なメリットを得ることが資産運用の主な役割です。
不動産運用といえば、「大家」として不動産を誰かに貸し、継続的に利益を得ることですが、実は不動産運用の目的はそれだけではなく相続税対策の場合もあります。
また、広くいえば「売って利益を得ること」も不動産運用のひとつです。
更には不動産を売ったお金を不動産以外の株、証券などで運用するということ1つの運用方法と言えるでしょう。
不動産運用で利益が出る3つの仕組み

不動産運用で利益を出す方法は主に3つあります。
①賃貸として家賃収入を得る
戸建てやマンション・アパートを賃貸して、家賃として現金収入を得る方法です。
いわゆる「家賃収入(インカムゲイン)」と言い、コツコツと稼ぐモデルです。
家賃は毎月大幅に変わるものではないため、入居者がずっと入居し続けてくれた場合はほかの金融商品に比べて景気変動の影響を受けることが少ないと言われています。
家賃収入に対して、どれだけの経費(管理費や修繕費など)とローンの返済額があるかで、月々の収支が赤字か黒字かが決まります。
一方、デメリットとしては、不動産の場合は長期定着してくれる借り手を見つけることがなかなか難しく、時間もかかるという点です。
人口減少により今後はますます空家・空室率が高い時代がやってきます。
大家として家賃収入を得ている人達も必死になるでしょうから、家賃は下がり、競争も激化していくと考えられます。
②不動産を売り、売買益を得る
「売買益(キャピタルゲイン)」とは、不動産を購入した価格よりも、高い価格で売却する投資です。
今後地価が上がりそうな戸建てやマンションを購入して、値上がりしたら売却し現金収入を得る方法です。
実際、バブル期には、不動産投資はこのキャピタルゲインを主目的としたものが多く、家賃収入は二の次というスタイルが一般的でした。
不動産価格が上り調子の時代・エリアであれば、売買収益を期待して取り組みます。
しかし、現在はキャピタルゲインを主目的とするよりも、長期での月々の家賃収入を狙った投資が主流です。
ただし不動産市況を捉えて、キャピタルゲインを得る方も一定数はいます。
③不動産を売ったお金を運用して、運用益を得る
不動産を売ったお金を、株・債権・投資信託・外貨などに変えて、配当金や分配金などの継続的な収入を得る方法です。
この方法のメリットは、不動産を持ち続けるリスクを減らせることです。
投資する資産を分散すれば、さらにリスクを小さくすることができます。
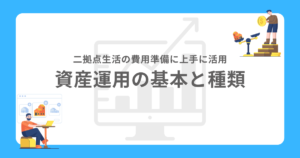
不動産運用のメリット

ここでは不動産運用のメリットを見ていきましょう。
収入を得られる
家賃収入は、自分の労働力に関係なく得られる「不労所得」です。
物件の管理には手間がかかりますが、管理会社へ委託できるため忙しい方でも続けられます。
入居者がいる限り毎月安定して収入を得られるため、老後の備えとしても人気です。
将来受け取る年金の金額と実際必要となる生活費には開きがあり、老後に2,000万円ほど不足する費用を、準備する必要があるといわれています。
老後に公的年金のみとなった場合でも家賃収入を得続けることができますので、生活を補うことができるでしょう。
価格変動リスクが低い
不動産は実際に存在する物に価値がある「実物資産」です。
実物資産に対して、株式や債券といった有価証券は「金融資産」と呼ばれます。
市場で取引される金融資産は、発行する企業の業績や市場参加者の心理状態などによって資産価値が変動します。
例えば、投資先の企業にとって悪いニュースが流れると「早く売却して損失を抑えよう」と考える投資家が増えるでしょう。
株価などの下落によって売りが売りを呼び、さらに資産価値が下がります。
不動産の資産価値も、経済や需給の関係などさまざまな要因で変動しますが、金融資産のように、急激に大きく変動するケースは多くありません。
また、実物資産はインフレに強い資産です。
インフレの局面において、資産を現金のみで保有するよりも資産価値の下落リスクを抑えられます。
レバレッジ効果
レバレッジとは直訳すると「てこの原理」で、意味としては小さな力で大きなものを動かすことができる“仕組み”を指します。
投資の世界でも同じことを実現することが可能です。
不動産運用におけるレバレッジとは、金融機関から借入れをして不動産を取得することです。
自己資金のみで投資を行うよりも大きな額の不動産を手にすることができるため、「レバレッジ効果」が期待できます。
節税対策
不動産運用をする場合、相続対策にも有効で、預金や株式などは時価で相続税が決まるのですが、不動産の資産運用の場合には、70~80%で評価されることが多いので、その分相続税が少なくなります。
例えば、現金は時価で評価するため、100万円の現金を相続した場合の相続財産は100万円です。
一方、土地は路線価や固定資産税評価額を基準に計算します。
一般的に、路線価は時価の80%、固定資産税評価額は70%を目安に設定されているため、時価よりも評価が低くなる傾向です。
また、土地の相続時は「小規模宅地の特例」が設けられており、特例が適用されると、さらに評価額が下がります。
不動産運用のデメリット
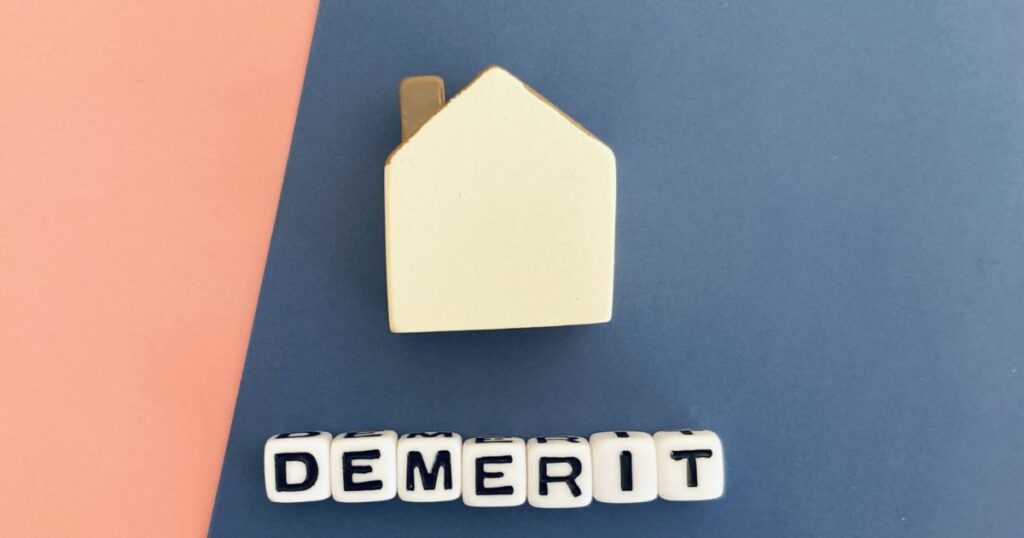
不動産の運用はメリットだけでなく、デメリットも存在します。
どのようなリスクがあるのか見ていきましょう。
空室時の収入源
借り手がすぐに見つかり、長期定着してくれるとよいのですが、実際にはそう簡単ではなく、空室の対策をとる必要があります。
空室対策として考えられることは、古くなった建物のメンテナンスです。
そのような外壁塗装や内装工事をするとなると、当然修繕費がかかります。
しかし、空家のリスクを少なくするためには、修繕の計画を立てて、できるだけ次の入居者が長くいてくれるようにすることが、一番の対策といえます。
また、サブリースを利用することで、空室対策ができます。
サブリースとは、空室のあるなしに関係なく、不動産会社から一定の金額が支払われます。
しかしサブリースの場合は、不動産会社の取り分だけ収入が減ってしまうというデメリットがあります。
初期費用・運用費用がかかる
不動産投資ローンを使って不動産を購入する場合でも、購入時には初期費がかかります。
不動産価格よりも少額ですが、ある程度の自己資金が必要です。
初期にかかる費用は、「所有権の移転」を明らかにするための登記にかかる費用、売買契約書に貼る印紙代(税金)などがあります。
また、管理に関する運用費用が必要になります。
不動産の管理には2つあり、建物管理と賃貸管理があります。
建物管理は分譲マンションの場合、建物管理費や修繕積立金などの費用がかかります。
例えば建物管理費は、共用部分の清掃、エレベーターの定期点検など、入居者の快適な暮らしを維持する費用です。
修繕積立金には、約15年に1度の建物の大規模な工事のほか、給水ポンプの交換費などが含まれます。
対して賃貸管理は、入居者とのやりとりや退去時の原状回復など、部屋の内部で起きることに対する業務です。
実際には不動産管理会社に委託することが多いため、入居者とのやり取りを行うことは稀ですが、原状回復については負担する必要がでてくる場合もあります。
不動産価格下落の可能性
不動産は年月がたつごとに、一般的には価格が下がるものといわれています。
それは経年により建物や設備は劣化するからです。
築年数とともに家賃がゆるやかに下がっていけば、得られる収入も減っていくでしょう。
ただし、立地が優れていたり、管理の行き届いた建物であれば価値を維持できる可能性は高まり、そのためにも建物の管理は重要といわれています。
なお市場の影響を受け、需要の高まりによって不動産価格が上昇する時期もあります。
天災の可能性
台風や地震など、年々被害が甚大化傾向にある自然災害によって不動産がダメージを受ける可能性もあります。
例えば大雨による浸水被害にあった場合にはその復旧費用がかかります。
地震による最悪のケースでは、建物に入ることができなくなり家賃収入がなくなる可能性が考えられます。
不動産運用で起こりやすい失敗
ここまで不動産運用の性質上のメリットとデメリットを見てきましたが、不動産運用をする際に私たちが起こしやすい失敗についても見ていきましょう。
情報収集を怠る
不動産投資では、購入した物件を長期的に保有し、適切な運営を行うことで利益を増やしていきます。
投資が成功するかどうかは物件選びで決まるといっても過言ではなく、物件に関する情報収集を怠ると失敗するリスクが高まります。
例えば、投資額に対する収入・利益の割合のことを「利回り」といいますが、高利回りの物件を選んだからといって必ずしも利益が安定するとは限りません。
空室がなかなか埋まらず、期待していたほどの収益が得られないこともあるでしょう。
そのため確実に収益を得るには、入居者を確保する必要があります。
そして入居者を確保するには、周辺の環境や建物の状態などから賃貸物件としてのニーズを見極める必要があり、そのために欠かせないのが情報収集です。
不動産運用を成功させるために、物件に関する情報はもちろん、不動産会社や管理会社に関する情報もしっかり集めるようにしましょう。
相場価格よりも高い物件を購入
物件選びのポイントはいくつかありますが、そのひとつが「価格」です。
例えば、相場よりも価格が高い物件を購入した場合、毎月のローン返済額が家賃収入を上回る可能性があり、結果的に損をする恐れがあります。
また、購入時の価格が高いほど売却した際に得られる利益が少なくなるのに加え、不動産の価値が下落したタイミングに売却してしまうと「キャピタルロス」となることもあります。
キャピタルロスとは、売却額が購入額を下回ることで被る損失をいいます
購入額が高いとその差も大きくなるため、損失も増えることになります。
このような失敗を防ぐためには、不動産投資に関する知識を深めると同時に、相場観や情報を分析する能力を鍛えておくことが大切です。
相場よりも高い家賃設定にする
不動産投資において家賃収入は利益の大半を占める重要なものです。
この点から「利益を増やすため家賃を高く設定しよう」と考える方もいるかもしれませんが、かえって入居希望者が寄り付かなくなる可能性があるため注意しましょう。
住居用の賃貸物件探しにおいて、家賃は多くの方が重視するポイントです。
たとえ好条件の物件でも、相場より家賃が高いと候補から除外されやすいため、家賃設定の際はエリアの相場を事前にチェックしておきましょう。
家賃滞納等で収支が悪化してしまう
家賃滞納が起きると一時的に収入が減少するため、場合によっては利益が支出の金額を下回ってしまうことがあります。
不動産を購入・保有すると、不動産取得税や固定資産税、所得税などのさまざまな税金が発生します。
また、購入時にローンを組んだ場合はその分も支払わなくてはならないため、入居者の家賃滞納が続くと赤字となり、自身の支払いまでもが滞ってしまう可能性があるのです。
さらに、不動産の修繕などに用いられる管理費が値上がりすることで、収入と支出のバランスが崩れてしまう可能性もあります。
管理費の一部である修繕積立金は修繕積立計画をもとに設定されており、徐々に値上がりするケースも少なくありません。
不動産運用を成功させるには事前に総額を確認しておき、無理のない資金計画を立てておくことが重要です。
安定した不動産運用をするためのポイント
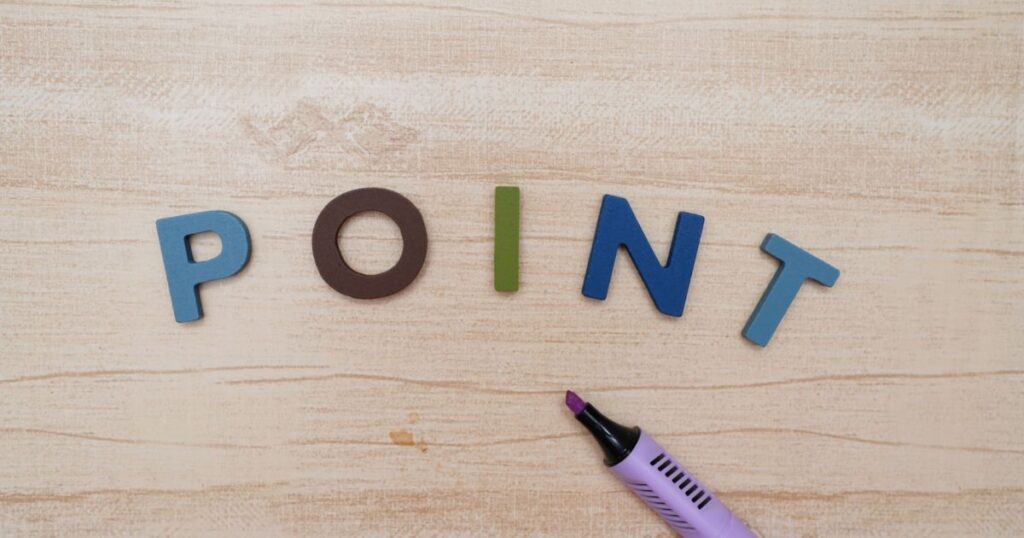
安定した不動産運用をするのには、いくつかのポイントがあります。
徹底的に情報収集をする
不動産投資では情報が必要不可欠です。
その際、参考にする材料は必ず一次情報にしましょう。
また、一か所で情報を集めるよりも複数から集めたほうがより正確性が増し、成功率を高められます。
情報収集を怠ることは不動産投資の失敗につながります。
そのため、物件や相場に関する情報、不動産会社・管理会社に関する情報などを徹底的に収集することが大切です。
きちんと自分の目で確かめ、正しい情報を取得しましょう。
なお、不動産投資に関する情報は常に同じとは限らず、情勢の変化などによって変わることがあります。
そのため、一度収集した情報でも常にその内容をアップデートしていくことが大切です。
そうすれば、古い情報のもと不動産投資を進めるリスクが減るほか、対応力・判断力が磨かれることで投資を成功させやすくなります。
不動産投資に適した物件を選ぶ
不動産投資に適した物件を選ぶことも、失敗を防ぐ上で重要なポイントです。
なぜなら、事故物件や入居者離れが予想される物件を選んでしまうと利益を充分に得られず、不動産投資が失敗する可能性があるからです。
不動産投資に適した物件にはいくつか条件があり、例えば「都心から近い、または駅から近い立地であること」が挙げられます。
交通の便がよい物件は、家賃収入と売買益のどちらを狙うとしても成功率が高いといわれています。
そのため、物件を選ぶ際は優れた立地かどうかを必ず確認することが大切です。
この他、「物件の築年数が浅いこと」も不動産投資に適した物件の条件のひとつです。
築年数が浅いほど修繕費がかかりづらいため、その分支出を押さえることができ、利益を得やすくなります。
中古物件を選ぶ際は修繕の可能性を考慮する
もし、不動産投資用に中古物件を選ぶなら、修繕の必要性を理解しておかなければなりません。
上記のとおり、築年数が浅い物件なら設備もまだ新しいため修繕の必要はほとんどないでしょう。
その一方で、中古物件の場合は築年数が古い可能性が高く、設備が経年変化していることが考えられます。
これにより、物件の購入費に加えて修繕費が発生する可能性もあるため、あらかじめ理解しておくことが大切です。
信頼できる不動産会社を選ぶ
不動産運用を行うときには不動産会社選びも大切です。
なぜなら、不動産会社はパートナーとなる存在だからです。
不動産会社によって得意としている物件に特徴がある場合が多く、新築物件を主に扱っている会社、中古物件に強みのある会社に分かれています。
まずは不動産会社に行き、自分の考えに合った提案をしてくれるのかを確認するだけでも信頼のおける会社かの判断材料になりますし、そういった会社であれば失敗のないよう親身にになってアドバイスしてくれます。
分散投資をする
分散投資をして、リスクをできるだけ少なくしましょう。
分散投資とは、資産運用をいくつかの資産に分配して、リスクを最大限に少なくすることです。
不動産資産の運用の場合には、アパートやマンションを複数購入して、投資することをいいます。
分散投資をすることで、ひとつの物件が赤字になっての、他の物件でカバーして、できるだけリスクを減らすことができます。
ひとつだけの資産運用はリスクがともないます。
分散投資でリスクのカバーをしながら、全ての物件が黒字で安定した収入を得ることが可能です。
物事を長期的に捉える
不動産投資を始めたからといって、すぐに満足できるほどの利益を得られるとは限りません。
例えば、売買益を狙っている場合は、物件の価値が高騰しているタイミングで売却するのが理想です。
しかし、そのタイミングがすぐに訪れるという保証はなく、もしかすると数十年先かもしれません。
つまり、不動産投資を確実に成功させるには年単位で物事を考え、自らが掲げたゴールの達成に向けて計画的に行動する必要があるのです。
そのため、物事を長期的に捉え、地道に努力することが、不動産投資を成功させるポイントと言えます。
まとめ
今回は不動産運用のメリットやデメリット、安定して運用するためのポイントをご紹介しました。
- 不動産運用の主目的は家賃収入や売買益により現金収入
- 不動産運用のメリットは価格変動リスクが低く、インフレに強い
- 不動産運用は取得物件に大きく左右されるため徹底的に情報収集をする