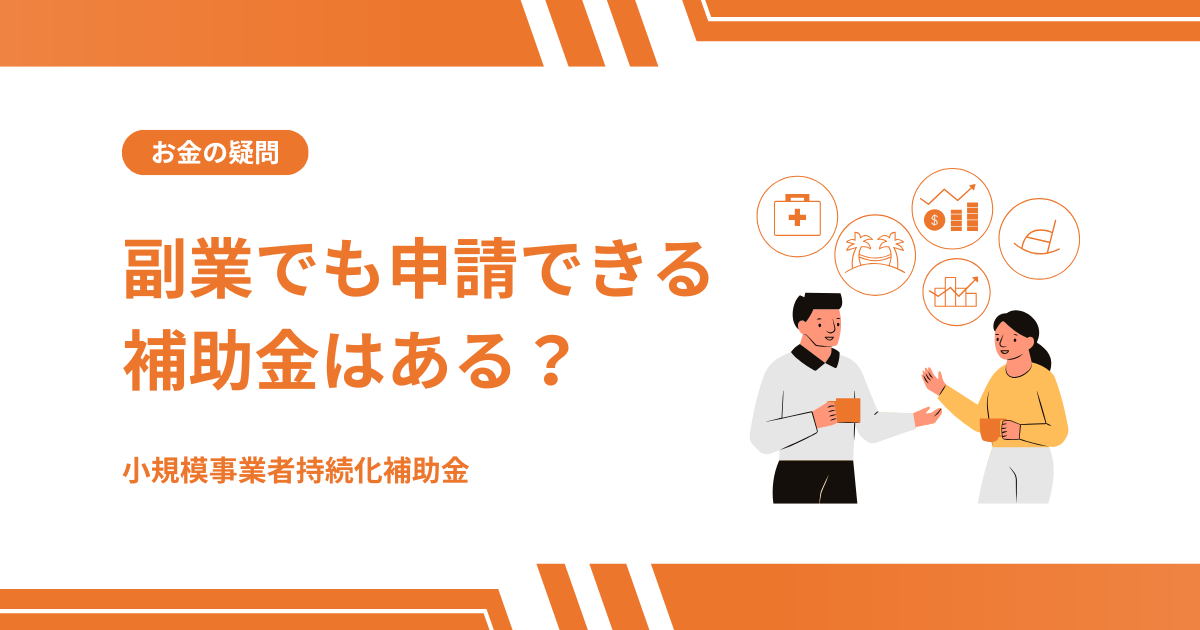副業解禁に伴い、副業を始める人が増えています。
しかし、副業をしている人のほとんどが資金調達の課題に直面すると言われています。
融資やクラウドファンディングなど、資金調達の方法には様々ありますが、国が支援している補助金も活用してみてはいかがでしょうか。
今回は副業でも申請できる補助金について、対象要件から申請までの流れをご紹介します。
他にも自治体が独自で行っている支援制度もご紹介しますので、最後までご覧ください。
副業でも申請できる補助金は?

普段は会社員として働きながら就業後や休日に副業を行っているという人も増えてきました。
その中には、新規開拓のための資金調達に、補助金等の利用を検討する人もいるでしょう。
中小企業や個人事業主にとって代表的な補助金と言えば、「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」です。
しかし、本業は別に持っていて副業をしている場合でも申請は可能なのでしょうか。
開業届を出していれば申請が可能
開業届を出して副業を行っている人は、「小規模事業者持続化補助金」や「IT導入補助金」に申請可能です。
たとえば、会社員の傍らでフリーランスとして副業している場合でも、開業届を出して個人事業主として収入を得ていれば小規模事業者持続化補助金の対象になります。
会社員でも開業届は出せるため、補助金の申請を検討する際には、まず開業届を出して申請要件を満たしておきましょう。
小規模事業者持続化補助金とは
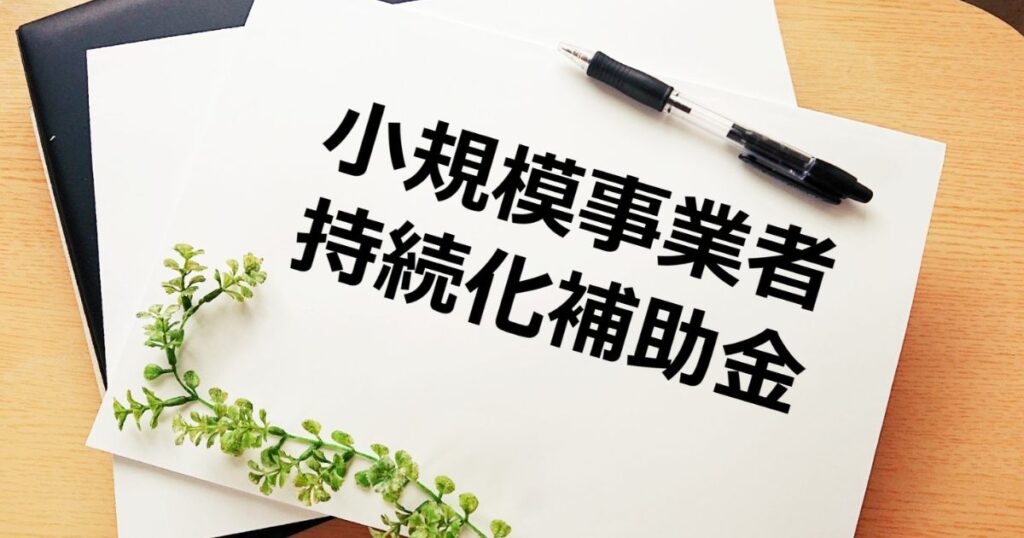
副業でも申請できる補助金として2つ挙げましたが、本記事ではその1つである「小規模事業者持続化補助金」について説明していきます。
小規模事業者持続化補助金とは、小規模事業者が持続的な経営を図るため、政府や地方自治体により実施される支援策です。
この補助金制度は、小規模事業者が自ら作成した経営計画に基づき、販路開拓や商品改良・開発などに取り組む際に支援を行います。
「販路開拓のための」という要件はありますが、副業を含む個人事業主や小規模事業者にとっては、比較的使いやすく、はじめて補助金を使うという方にもおすすめです。
具体的には、新たな市場への参入を目指すために販売戦略を工夫したり、新たな顧客層を獲得するために商品の改良や開発を行ったりすることが支援の対象となります。
上記に合わせて、賃金の引き上げ、インボイスを導入した場合に上乗せされる特例もあります。
他にも、小規模事業者持続化補助金には、「創業型」という創業して間もない事業者が対象の類型も設けられているため、これから新たに事業を開始するという方にもおすすめです。
2024年12月19日、中小企業庁は2025年の小規模事業者持続化補助金の概要を公表しました。
予想では第17回は2025年3月頃より公募開始とみられているため、補助金を活用して事業を拡大したい人は必見です。
補助金の対象者と要件
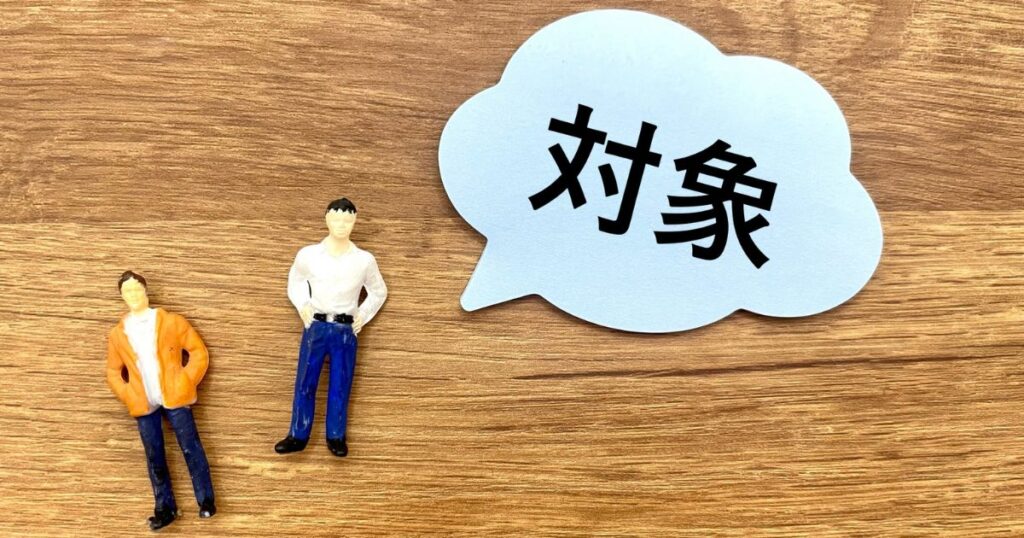
続いて、小規模事業者持続化補助金の対象者とその要件について説明していきます。
補助金対象者
小規模事業者持続化補助金の対象者は、以下の通りです。
| 業種 | 従業員規模 |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 常時仕様する従業員の数5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時仕様する従業員の数20人以下 |
| 製造業その他 | 常時仕様する従業員の数20人以下 |
補助金の要件
補助金要件は以下の通りです。
- 資本金または出資金が5億円以上の法人に100%株式保有されていないこと。
- 直近3年間の平均課税所得が15億円を超えていないこと。
- 以前に持続化補助金で採択された場合は、必要な報告書の提出を完了していること。
- 「卒業枠」で採択された事業者でないこと。
申請枠と補助金額・対象経費

次に小規模事業者持続化補助金の申請枠と補助金額について見ていきましょう。
一般型
| 申請枠 | 概要 | 補助金額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 通常枠 | 経営計画に基づく販路開拓等を支援 | 上限50万円 | 2/3 |
| インボイス特例 | 免税事業者の転換を支援 | 補助上限50万円上乗せ | 2/3 |
| 賃金引上げ特例 | 事業場内最低賃金を50円以上引き上げる事業者向け | 補助上限150万円上乗せ | 2/3 ※赤字事業者は3/4 |
| 災害支援枠 | 被災事業者が事業再建に向けた事業を支援 ※令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨の被害 | 200万円(直接被害) 100万円(間接被害) | 定額、または2/3 |
補助対象の経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費
※災害支援枠は、上記に加え車両購入費
創業型
産業競争力強化法に基づく認定市区町村による特定創業支援を受けた小規模事業者向け
補助金額:上限200万円
補助率:2/3
補助対象の経費
機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費
共同・協業型
地域に根付いた企業の販路開拓等を支援
補助金額:上限5,000万円
補助率:定額、または2/3
※地域振興等機関・参画事業者により補助率が異なる
補助対象の経費
・地域振興等機関・・・人件費、委員等謝金、旅費、会議費、消耗品・備品日、通信運搬費、印刷製本費、雑役務費、委託・外注費、水道光熱費
・参画事業者(小規模事業者限定)・・・旅費、借料、設営・設計費、展示会など出展費、保険料、広報費
ビジネスコミュニティ型
商工会・商工会議所の内部組織等(青年部、女性部等)向け
補助金額:50万円、2以上の補助対象者が共同で実施する場合は100万円
補助率:定額
補助対象の経費
専門家謝金、旅費、資料作成費、借料、雑役務費、広報費、委託費
補助金申請の流れ
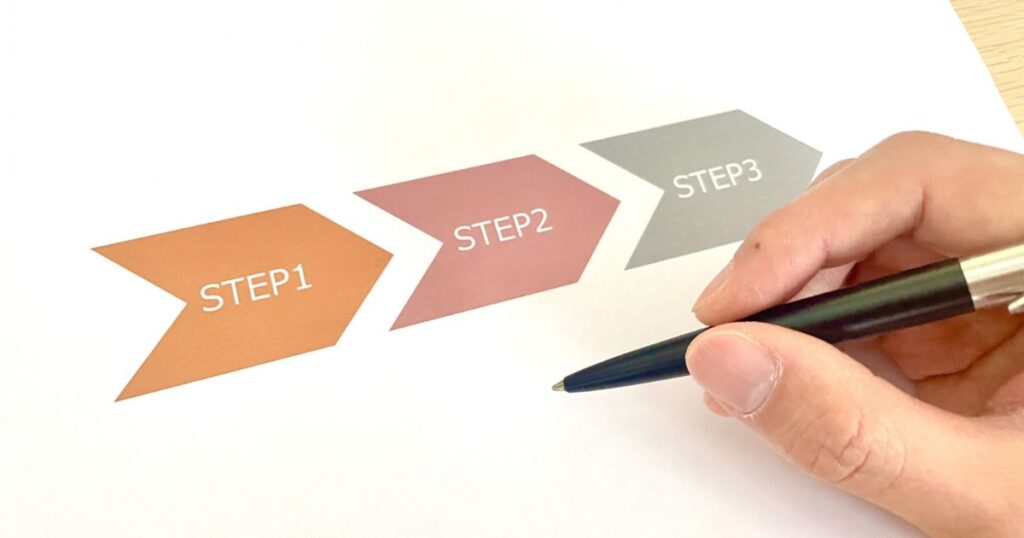
①申請準備
小規模事業者持続化補助金の申請には、複数の書類と申請手続きに利用する「GビズIDプライムアカウント」が必要です。
申請に必要となる書類は「個人事業主が申請するケース」や「賃金引上げ枠に申請するケース」、「インボイス特例を利用するケース」など、事業者の申請内容によって異なります。
そのため、過去の公募を参考にしたり、公募が始まり次第、必要書類の詳細を確認しましょう。
また、書類には事業主が作成するものだけでなく、商工会・商工会議所が発行する書類もあります。
発行には1~2週間ほどの期間が必要となりますので、補助金の申請期日に間に合うようスケジュールには余裕を持っておきましょう。
②申請手続き
小規模事業者持続化補助金は、電子または郵送での申請が可能です。
ただし、郵送での申請は減点調整の対象となります。
可能な限り電子申請をおこないましょう。
電子申請は、専用の申請サイトを利用します。
なお、商工会と商工会議所、所属を問わず申請用サイトは同一です。
郵送申請の場合、地区に応じて書類の提出先が異なります。
商工会議所地区の場合は事務局への送付で一貫化されていますが、商工会地区の場合は公募要領に記載されている各地方事務局へ送付しなければなりません。
商工会地区で郵送申請をおこなう際には注意が必要です。
③審査
事業計画をはじめとした申請内容は、外部有識者による審査がおこなわれます。
審査によって提出された事業計画に評価がつけられ、評価が高いものから順に採択となります。
なお、審査の評価は「審査におけるポイントを満たしているか」、「加点項目が取り入れられているか」などによって決まります。
④採択・交付決定
採択決定者には、「交付決定通知書」が通知されます。
なお、採択された事業は所在する都道府県・事業者名(屋号)・法人番号・共同申請の有無・補助事業名が補助金事務局公式ウェブサイトにて公表されます。
⑤補助事業の実施(採択された場合)
以後、採択・交付決定がされた場合の流れをご説明します。
採択後は申請した事業計画に沿って事業を実施していきます。
ここで注意しなければならないのが「補助事業実施期限」の存在です。
小規模事業者持続化補助金には、公募ごとに「補助事業実施期限」が設定されており、事業計画はこの日までに完了させる必要があります。
また、補助対象となる経費はこの実施期限日までに発注~支払いを完了した費用のみとなります。
なお、事業の実施中に当初の計画から事業内容を変更する場合、または経費配分を変更する場合には「計画変更の申請」が必要です。
各種変更にあたってはあらかじめ決まった様式の「変更承認申請書」を提出しなければなりません。
作成・提出については補助金公式ウェブサイト・各回の公募要領を確認しましょう。
⑥実績報告書の提出
補助事業の完了後には、「実績報告書」を事務局へ提出します。
申請時と同様に送付先が商工会議所地区と商工会地区で異なりますので、送付先を確認しましょう。
商工会議所地区で電子申請をした場合は郵送不可となります。
実績報告書は「事業完了日を起算日として30日が経過した日」または「最終提出期限日」のどちらか早い日までに提出しなければなりません。
実績報告書の提出に関しては、事務局公式ウェブサイト内「補助事業の手引き」にも案内が掲載されています。
提出前に必ず確認しておきましょう。
※事務局公式ウェブサイトは公募開始時にリリースされます。
⑦確定検査および補助金額の確定
実績報告書を受領次第、事務局が事業実績および費用内訳などを審査・確認し補助金額を確定します。
審査・確認作業では実績報告書のほかに見積書や発注書などの証拠書類も参照されます。
すべての申請経費を補助対象経費として承認してもらうには、事務局が必要と判断した書類を不備なく提出しなければなりません。
追加提出に備え、事業期間中の請求関連書類は忘れずに保管しておきましょう。
また、確定検査の一環として事務局による現地調査がおこなわれる場合があります。
⑧補助金の請求・入金
補助金額の確定後、「補助金確定通知書」が事務局より送付されます。
金額を確認し、「精算払請求」を事務局に対しおこないます。
その後、数週間の手続き後、補助金の入金がおこなわれます。
⑨事業効果報告
補助金の交付対象者は、申請事業がどのような影響を与えているかの「事業効果報告」をおこなう義務があります。
また「賃金引上げ枠」、「卒業枠」の申請事業者は、あわせてこれらの成果報告も必要です。
事業効果報告は「事業効果および賃金引上げ等状況報告」の文書および必要な証拠書類(賃金台帳・労働者名簿等の写し等)を提出します。
自治体独自の補助金まとめ

自治体によっては、「小規模事業者持続化補助金」へ上乗せや独自の支援を行っています。
ここでは、2024年度に実績のあった自治体をご紹介します。
※最新情報については各自治体・商工会ページでご確認ください。
小規模事業者持続化促進補助金(千葉県流山市)
国の 「小規模事業者持続化補助金<一般型>」 を活用して、販路開拓等に取り組む事業者に上乗せ補助を実施します。
交付対象者
次の①~③の全てに該当する小規模事業者が 対象となります。
- 国の「小規模事業者持続化補助金<一般型>」に申し込み、令和4年4月1日以降に国から補助事業に対する補助金の交付額の確定通知を受けた市内の小規模事業者
- 市内に主たる事業所を有している事業者
- 市税を完納している事業者
補助金額
国の交付決定を受け、令和4年4月1日以降に補助金の額の確定を受けた額「国の補助金交付確定額」の1/4(千円未満切り捨て)を補助します。
小規模事業者等創業支援事業補助金(千葉県いすみ市)
新規事業者の事業活動の活性化及び雇用の創出を図るため、「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」の交付対象者に対し、市が独自に上乗せ補助を実施します。
補助対象者
次の要件を全て満たす小規模事業者等が交付対象となります。
- 小規模事業者持続化補助金(創業枠)/第11回以降の交付を受けていること
- 申請時において市内に主たる事務所又は住所を有し、かつ、市内で事業を営んでいること
- 市税等の未納が無いこと
補助金額
次に掲げる計算式により算出した額を補助金額とします。
(持続化補助金補助対象経費-持続化補助金額)×1/2(上限50万円)

中小事業者持続化及びSDGs推進補助金(群馬県東吾妻町)
地域経済を支える東吾妻町内の中小事業者が、持続的な開発目標(SDGs)を意識しながら継続的な経営に向け、創意工夫を凝らした地道な販路開拓や新しい生活様式に対応することを目的に実施する事業に対して支援をし、本町の商工業の振興を図ることを目的とします。
補助対者
- 東吾妻町内に事業所や店舗を持つ中小企業の事業者(個人事業者含む)。
- 申請時点で事業開始している事業者で、今後1年以上継続して事業を行う予定であること。
- 期限の到来した町税等を完納していること(個人事業主の場合、町税の納税義務者が町税等を完納していること)。
補助対象事業
- SDGs17の開発目標のうち、ターゲットに該当とする事業
- 販路拡大のための事業、または新製品開発のための事業
- 対象となる店舗・事業所等は、東吾妻町に住所を有するものに限る
補助金額
- 町内事業者が施工又は町内事業者から購入の場合、かかる経費の100分の50
- 町外事業者が施工又は町外事業者から購入の場合、かかる経費の100分の30
※補助の上限額は30万円とします。
※対象経費は、総額10万円(税込)以上の事業が対象です。
※補助対象品の単価5万円(税込)以上とします。
補助対象経費や詳細については、ページ内の資料をご確認ください。
中小企業者経営改善・創業等支援補助金(茨城県大子町)
町内における地域経済の活性化及び雇用の創出を図るため、社会情勢等の変化に応じた持続的な経営に向けた取組や創業等(創業、事業承継及び新規出店)を行う事業者を支援します。
補助対象事業者
- 経営改善…新商品開発、人材確保、環境配慮行動、自然災害等
- 創業等…創業等事業
- 国補助金…国が実施する中小企業等事業再構築促進事業に関する補助金の交付決定を受けている
補助金額・補助率
1/2(上乗せ要件で2/3)
※上限25万円(上乗せ要件で50万円)
補助対象経費
機械装置等導入費、広告宣伝費、出展費、旅費、開発費、備品購入、賃借料等
詳細については、公式ページをご確認ください。
まとめ
今回は副業でも申請できる補助金について、小規模事業者持続化補助金の対象要件から申請までの流れをご紹介しました。
- 副業であっても開業届を出していれば補助金申請は可能
- 初めての申請におすすめの小規模事業者持続化補助金は一般型・通常枠と創業型
- 申請には書類準備に時間がかかるため、前もって確認をしておこう