リモートワークが普及していく中で、地方移住に力を入れる自治体も増えています。
また、国としても都心の一極集中を緩和するため「移住」に関する支援を強化してきました。
しかしながら、都会への人口流入は続いており、政策としての地方移住が順調は進んでいるとは言えません。
そこで、2018年頃から移住に代わって、地方を活性化することが期待できる「関係人口を増やす」という取組みが注目されるようになってきました。
今回は、地域創生や二拠点生活に関連が深い「関係人口」についてご紹介します。
関係人口とは

関係人口とは、移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域と多様に関わる人々のことを指します。
過去に滞在をしていて思い入れがある
二拠点生活などで何度も訪れている
いずれ戻りたいと思っている故郷など
地域にルーツや愛着があり、関わっている人などが該当します。
関係人口の具体例
- 決まった地域へのふるさと納税
- 都会と地方での二拠点生活
- 出身地や父母の故郷等
など
定住人口
定住人口とは、その地域に居住する人やその土地へ移住する人たちのことを指します。
定住人口と同じ意味で「居住人口」と呼ばれることもあり、関係の深さで考えれば関係人口よりも深い関係だと言えるでしょう。
しかし、移住は心理的ハードルが高く、多くの地方自治体が定住人口の創出に苦戦を強いられているのが現状です。
そこで近年は、ワーケーションや多拠点居住の受け入れなどによって、地域へ移住するハードルを下げる取り組みが行われています。
交流人口
交流人口とは、なにかしらの目的を持ってその地域を訪れる人たちのことを指します。
具体的な目的としては、観光を筆頭に通勤・通学、習い事、スポーツ、レジャーなどが挙げられます。
交流人口はあくまで目的を果たすために訪れることが多く、関係人口と比べて地域との関わりは浅いと言えるでしょう。
関係人口が生み出された背景

地方に新しい風をもたらす存在である関係人口が、なぜ近年注目されているのでしょうか。
ここでは、その背景をご紹介します。
関係人口は、地方創生に関連する言葉として位置づけられています。
そもそも地方創生の目的は、首都圏への一極集中型を是正し、地方の地域づくりの担い手不足という課題に歯止めをかけるとともに、将来にわたって活力ある日本社会を維持していくことを目指すことを指します。
しかし未だに首都圏への人口流入は続いています。
そこで国は「移住促進」だけでは難しいと考え、「関係人口」という新たな概念を使い、若者を中心に地域外の人材を呼び込み、地域づくりの担い手となってくれるような取り組みを始めています。
また、インターネットをはじめとしたデジタルの発展により、リモートワークで都心と地方を行き来しながら働いたり、経済的な成功よりも健康的な生活を志向する人が増えたりなど、新しい生活様式が後押ししています。
関係人口の実数

国土交通省は関係人口の「実数」を把握するため、「地域との関わりについてのアンケート調査」(2020年)を実施しました。
その結果、移住や観光でもなく、単なる帰省でもない、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ「関係人口」について、全国の18歳以上の居住者の約1,827万人が特定の地域を訪問している関係人口であることが判明しました。
この調査によると、直接寄与型と言われる産業の創出、ボランティア活動、まちおこしの企画等に参画している人が、三大都市圏居住者の6.4%(約301万人)、その他地域居住者の5.5%(約327万人)存在しており、様々な関わり方をしています。
また、農山漁村部に関わる直接寄与型は、関わり先の自然環境に魅力を感じており、移住希望が強いことが同調査から判明しています。
今後さらに社会全体のデジタル化が進むことが予想されており、近年のライフスタイルの多様化なども後押しとなって、関係人口の創出・拡大が期待されています。
・地域との関わりについてのアンケート調査(国土交通省):https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001391572.pdf
関係人口のメリット

関係人口を増やすことが地方活性のための国による取組みということがわかりました。
ここでは、関係人口を増やすメリットを見てみましょう。
①労働力不足や後継者不足を解決
多くの地域では人口減少による労働力不足といった課題があります。
地場産業の担い手は高齢化し、後継者について頭を悩ませているケースも少なくありません。
帝国データバンクの調査では、2021年の社長の平均年齢は60.3歳と過去最高年齢となっています。
また、約27万社の57.2%で後継者不在であることが明らかになっています。
関係人口が増えることで、地場産業を支える人材の確保ができたり、伝統的工芸品産業の後継さ不足を解決できたりと、地域経済を活性化できるメリットがあります。
そのため、関係人口は、地域づくり支援の担い手として活かせることから、慢性的な人手不足に陥る分野の問題を解決できます。
また、地域に新しい人や考えが入ることにより、さらに住みやすい街、住みたいと思われる街へと地域活性化が期待されています。
②首都機能の分散
2つめのメリットは、人口や労働力の東京一極集中を是正し、地方の活力を生み出すことで日本の全体を高められるからです。
首都機能を地方に分散することは、停滞感の強い日本を打開するきっかけになり、様々な波及効果が期待されています。
移住は現実的には難しくても、地域と関わりたい人は一定数いるため、関係人口を増やす施策は長期的な地域活性化に繋がる可能性が高いのです。
③自分らしいライフスタイルの確立
関係人口となる都市住民にとってもメリットはあります。
平日に本業の仕事をする傍らで、休日の空いた時間に愛着のある地域や地域の人々と交流を深めて地域課題を解決する担い手として参加することで、新しいスキルや知見を得ることができるでしょう。
また、自身が住みたいと思っている地域で二拠点生活することで、都会と自然豊かな地方のいいとこどりができます。


関係人口のデメリット
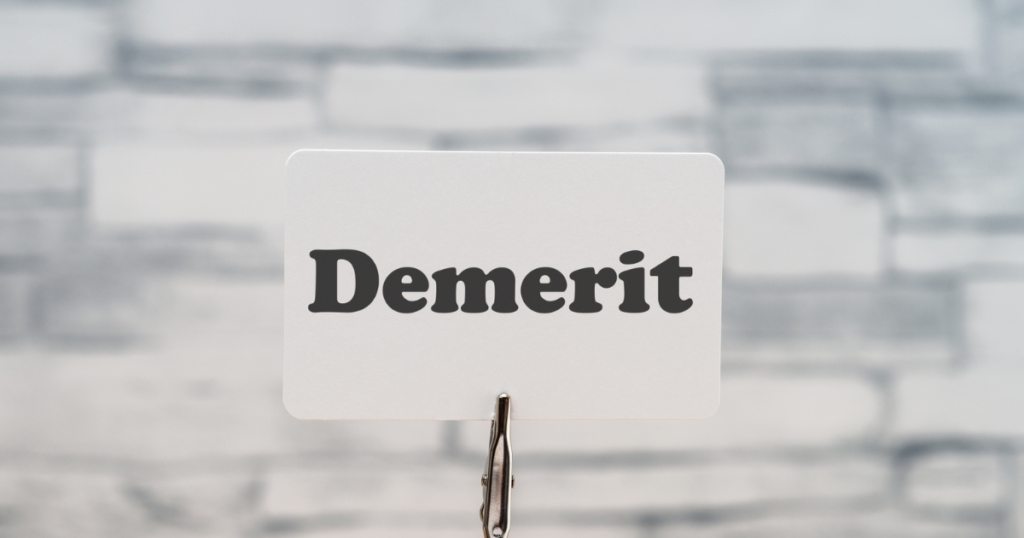
次に、関係人口を増やすデメリットを見ていきます。
目的外のイベント
関係人口増加への取り組みは、全国の半数近くの自治体で取り組みを行っていると言われています。
そのためレッドオーシャン化してしまい、地域課題への取り組みよりも関係人口を増やすだけのイベントやワークショップ開催となってしまっている自治体もあります。
参加する側としては、その地域へ愛着を持って地方創生に貢献したいという思いがあるはずですので、地域活性化するプロジェクトなのかを確認する必要があります。
地域の環境悪化
関係人口が増えたとしても、それによって地域環境が悪化するということも考えられます。
受け入れ態勢が整っていなかったり、地域住民と意思疎通ができていないと、本来は活性化につながる取組みも、地域の治安やゴミ問題等の生活環境の悪化というデメリットになりかねません。
関係人口として関わる側の私たちも、その地域の環境悪化につながらないよう配慮をする必要があると言えます。
関係人口の取組みプログラム4選

ここでは、関係人口を増やす取り組みを行っているプロジェクトやサイトを4つご紹介します。
「ふるさとプロボノ」全国
地域活性化に取り組む地域内のコミュニティや団体と、地域外のビジネスパーソンをつなぐプログラムです。
主には農山漁村の暮らしを体験し、かつ本業で得たスキルや知見を使って、経験の提供(プロボノ)により地域コミュニティの活動基盤強化や、地域活性を応援する 「課題解決型地域交流プログラム」です。
現在、北海道から九州までおよそ70以上の地域でプログラムが開催されています。
「マイ田んぼ」千葉県匝瑳市
千葉県匝瑳(そうさ)市では「SOSA Project」という取り組みを行っており、「ローカル化」をキーワードに米作りやDIYを経験できます。
「マイ田んぼ」は1区画が約50平米ほどで、草取りや田植え、収穫を行います。
分からないことや困ったことは「SOSA Project」に相談できるので、米作りが初めての人でも安心です。
関係人口の効果として、米作りや空き家リノベーションを通して、都心から匝瑳市に100組以上が通い、匝瑳市を含め近隣市町村への移住者も40名近くに上っています。
「アキヤアソビ」静岡県沼津市・裾野市
公共と連携し移住定住・創業支援・空き家対策を行っている「アキヤアソビ」
空き家を改修し、沼津市ではフリーランス×空き家、裾野市では大学生×空き家として、関係人口創出に役立つシェアスペースとして提供しています。
更に関係人口の創出のため、創業支援・アーティスト支援に取り組んでいます。
「関係人口マッチング・ナビ」全国
総務省が運営している「関係人口ポータルサイト」内にあり、関係人口に関する自治体の募集案件を探すことができるナビサイトです。
農業体験の他、移住体験や、イベントの交流体験など幅広い募集の掲載があります。
まとめ
今回は、地域創生や二拠点生活に関連が深い「関係人口」についてご紹介しました。
- 関係人口とは、定住していないが地域と多様に関わる人々のことを指す
- 関係人口の推計は1800万人と増加傾向
- 自治体や団体が開催する関係人口に関するプログラムがある



