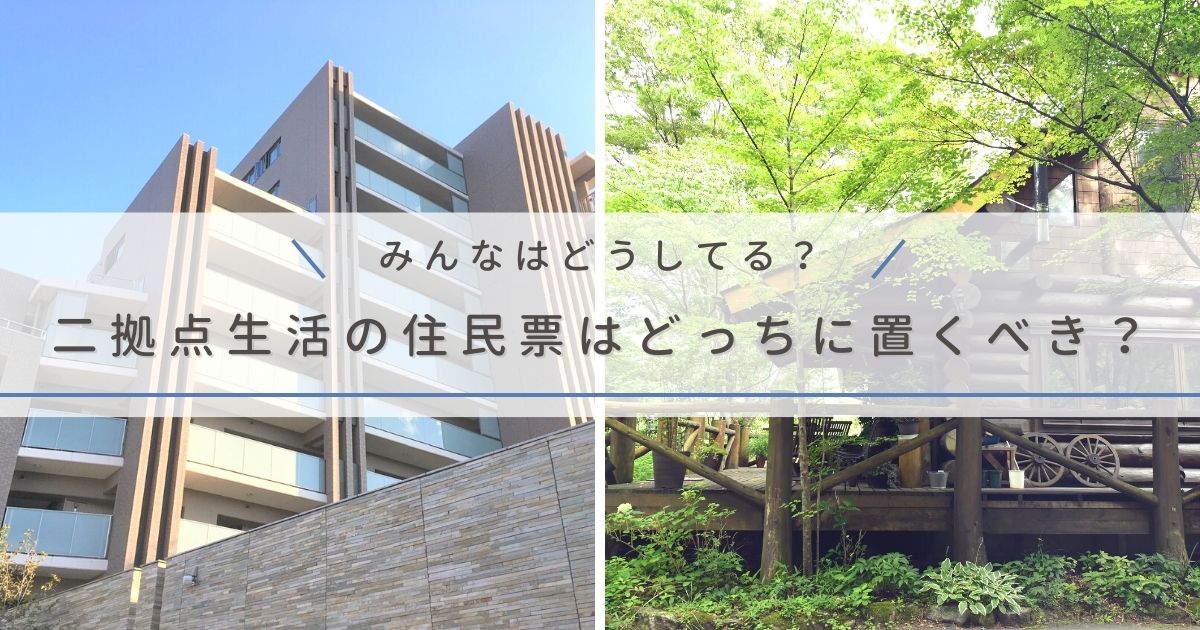平日は都市部で仕事中心の生活をし、週末はゆったりと田舎暮らしをする「二拠点生活(デュアルライフ)」を始める人が増えています。
また、テレワーク・リモートワークという働き方が浸透してきて、それに伴い平日も含めて長期滞在をしているという方もいらっしゃいます。
今までの別荘と明らかに異なるのはリゾート感覚ではなく、「もう一つの家・生活の場」として二拠点生活を考えているということです。
そんな二拠点生活を行う上で、気になってくるのが「住民票をどこに置くか」です。
今回は、二拠点生活をする時に住民票をどちらにおけばいいのか、移した場合に活用できる制度などをご紹介します。
二拠点生活(デュアルライフ)とは?

二拠点生活とは、2つの地域に生活拠点を持ちながら暮らすことを指します。
主に、都会と田舎といった拠点を持つことが多く、メリハリのある充実した日々を過ごす方がここ数年増えています。
二拠点生活のライフスタイルは人によってさまざまで、平日は都会、休日は地方で過ごす「週末田舎暮らし」をしている人もいれば、スキーやサーフィンなど趣味のために2~3ヶ月を地方で過ごす人もいます。
子どもがいる場合は学校の長期休暇に合わせて拠点を変えるケースもあり、仕事や家庭の事情に合わせた柔軟なライフスタイルを選択可能です。
移住とは異なり、仕事や住まいを変える必要がないところが二拠点生活のメリットです。
都会と田舎を行き来しながら、自分らしい暮らしを楽しむことができる二拠点生活は、新しいライフスタイルとして定着しつつあります。
二拠点生活の実態

ひと昔前まで、都会から地方へ移住する人や二拠点生活をする人の多くは、仕事をリタイアした人というイメージでした。
しかし、最近では都心部で働きながら、田舎暮らしを満喫するという若い世代も増えています。
二拠点生活の理由は「ゆとりのある暮らしをしたい」
国土交通省の「社会情勢の変化に応じた二地域居住推進施策に関する検討調査(2012年)」によると、二拠点生活を始めた理由のトップが「ゆとりのある暮らしをしたい」で、全体の約4割を占める結果となりました。
かつてのライフスタイルは、子育てのために都心ではなく、自然豊かな郊外のニュータウンや住宅地を選ぶ家族が多くを占めており、平日は都心部まで長時間通勤、週末は緑の多い住宅地でのんびり過ごすというものでした。
しかし今は、都心部での共働き世帯は年々増えており、夫婦の通勤利便性等を優先して、都市部に住まいを選ぶ傾向が高まっています。
都市部は仕事面や買い物などの生活に関する利便性がよい反面、自然を感じられる機会が少なく、目まぐるしい変化に晒されて疲れたり、孤独を感じやすいという面もあり、心のゆとりがもてる環境が欲しいということで、二拠点生活を考え始めるきっかけとなるようです。
二拠点生活者は子育て世代が中心
リクルート住まいカンパニーが2018年に行ったアンケート調査の結果によると、二地域居住を開始する人は近年増加傾向にあり、2018年は年間17万人以上と推計されています。
また、「将来したい」「興味がある」など、二地域居住を前向きに考えている「意向者」の割合は全国の20〜60代で14%に達し、人口にすれば約1100万人という計算になります。
実際に二拠点生活をしている人の属性を見てみると、年代は30代(29.1%)がもっとも多く、以下20代(27.9%)、40代(16.5%)と続いています。
そして家族構成は、「既婚、子どもあり」が4割を超えており、若い子育て世代を中心に二拠点生活をしていることがわかります。
二拠点生活を始める人は年々増加
前述の心理的背景と、昨今の「パソコン1台あれば、仕事ができる」ということで、テレワークを導入した企業が増加したことにより、場所や時間に縛られることなく、働ける時代になったことで二拠点生活を始める人は年々増えています。
また、自治体によるお試し移住体験などの支援施策や、拠点の取得方法が多様化しコストを抑えて始められる等、二拠点生活をする上で、様々な選択肢がとれるようになったことも増加の後押しとなっています。

住民票はどっちに置くべき?住民票の役割について

二拠点生活を行う上で気になってくるのが「住民票をどうするのか」です。
今の拠点に住民票を置いたままにするべきか、気に入った2拠点目に住民票を移すか選択しなければいけません。
なぜなら、住民票を2つの地域に置くことはできないからです。
結論から言いますと、生活拠点が2つある場合、住民票は滞在期間が長い拠点に置くことをおすすめします。
理由としては、住民票は公的サービスを受けるために必要なものだからです。
たとえば、ワクチンの接種は住民票のある市区町村で受けますし、選挙の際には住民票のあるところで投票します。
その他、福祉や図書館などの施設利用といった公的サービスを受ける際にも、住民票が必要になることがあります。
公的サービスを受ける頻度が多い拠点や、さまざまな手続きをしやすいのはどちらの拠点かを考えて、滞在期間が長い拠点の方を選ぶとよいでしょう。
住民票と運転免許証
住民票の異動と運転免許証の住所変更はそれぞれ手続きをする必要があります。
運転免許証の住所変更をするには、住民票の写しや郵便物など、新住所を示すものが必要です。
そのため、仮に住民票を新しい拠点に移す際、手順としては住民票を変更したのち、運転免許証の住所を変更するという流れになります。
住所変更をしないまま運転できないことはありませんが、免許更新の案内は旧住所に届きますし、更新手続きも基本的には旧住所で行います。
そのため、主に生活している拠点に住民票を置くほうがよいでしょう。
2拠点目に住民票を移すメリット

まずは2拠点目に住民票を移した場合のメリットについてご紹介します。
①自治体の支援制度が受けられる
自治体が移住者に対し、最初の生活基盤を整えるための支援や、リフォーム・住宅に関する助成金制度を設けている所が多くあります。
また2019年から政府が、東京圏外に移住する場合に移住支援金を支給する取組を支援しています。
地方移住先の自治体が地方創生移住支援事業を実施しているなど条件がありますが、世帯での移住で最大100万円、単身での移住で最大60万円の受給が可能です。
このような支援制度を受ける場合には住民票を移すことが条件となっている場合が多いです。
②住宅ローンの利用
住宅を購入する場合において住宅ローンを利用できるのは、原則として「自分が居住する住宅」となります。
そのため、ローンの必須条件として住民票の提示を求められることがほとんどです。
住宅ローンを利用して購入した住宅に「住んでいない」場合は、ローンの一括返済を求められることもあるので注意が必要です。
こういったメリットを享受できるか、2拠点目の自治体や銀行等に問い合わせしてみることをおすすめします。
また、住民票を移さない場合でも、2拠点目に月1回以上通うのであればセカンドハウスローンの利用が可能な場合もあります。
2拠点目に住民票を移すデメリット
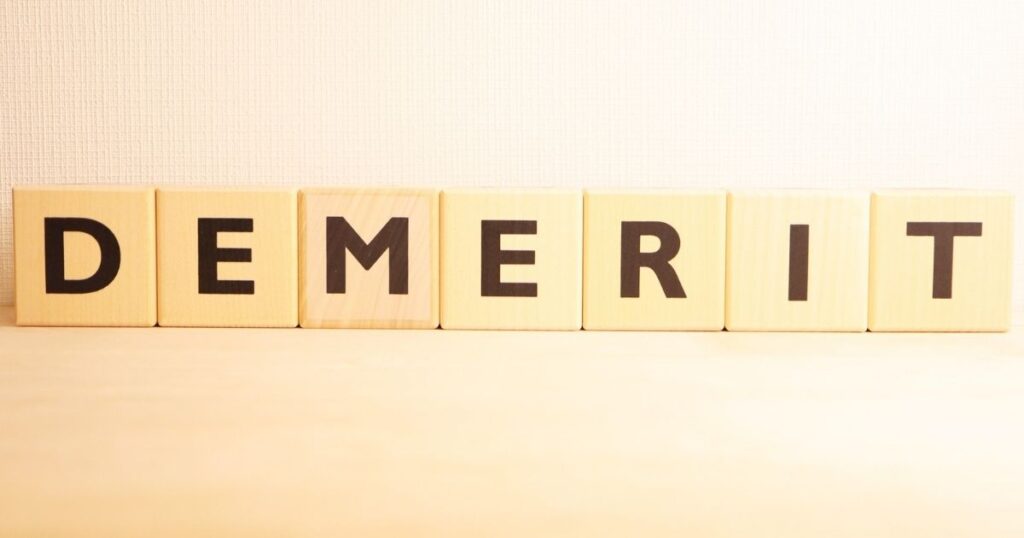
続いて、2拠点目に住民票を移した場合のデメリットについてご紹介します。
①これまでの公共サービスが制限される
当然の話ではありますが2拠点目で公共サービスが受けられるものの、これまでの拠点で受けられる公共サービスが制限される可能性があります。
そのため、これまでの住まいで受けられていた公共サービスと2拠点目で受けられるサービスを比較検討する必要があります。
②お子さんの就学条件や制度に注意
小中学生のお子さんがいる場合、公立校は住民票のある学校へ就学が原則となります。
住民票を移さずとも2拠点目の学校に一時的に就学できる「区域外就学制度」というものもありますが、現在の学校と受け入れ先とで協議が必要となります。
また、全ての公立校が対応しているとも限りませんので、注意が必要です。
他にも就学に関する自治体の支援制度を受けている場合は考慮する必要があります。
二拠点生活時の住民票と住民税の関係
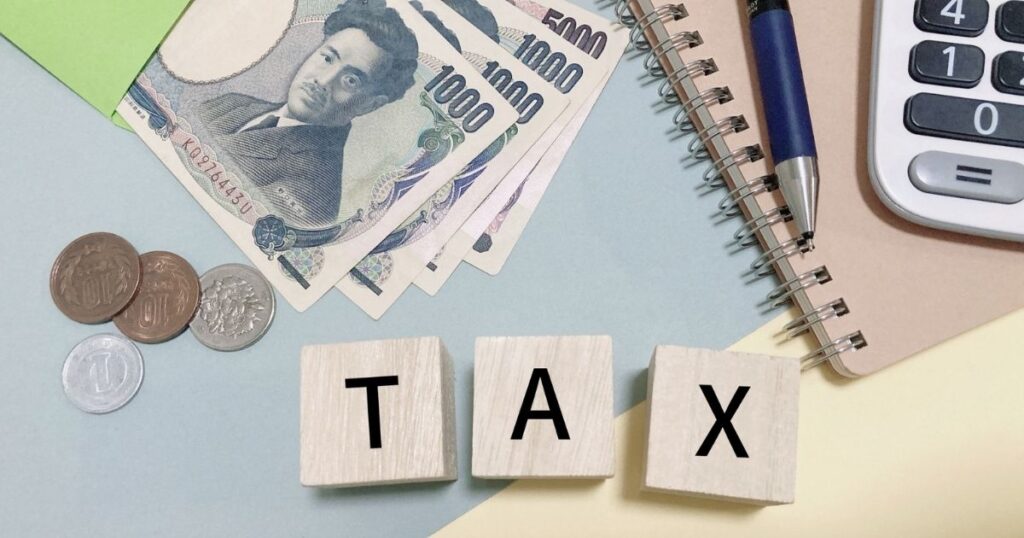
住民票を2拠点目に移す場合、住民税についても考慮する必要があります。
ここでは住民税についてお話します。
住民税の考え方
住民税は、住民票のある地方自治体に納めます。
地方税法によって標準税率が決められているため、住民税に地域差はないのが原則ですが、実際には自治体の裁量で変更できるため、住民税の額に地域差が発生することもあります。
たとえば、北海道夕張市では、財政を立て直すために税率を0.5%上乗せしていたというケースや、神奈川県や岩手県などでは、環境負荷を抑制するために「地方環境税」を徴収しています。
つまり、住民票をどこに置くかによって、住民税に差が生まれる場合があるのです。
気になる人は、事前に2拠点目の地方自治体のサイトで確認しておきましょう。
住宅を所有する場合は住民税にも注意
2つの拠点のうち、少なくともどちらかに住宅を所有している場合は注意が必要です。
というのも、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
しかし、税制上、住まいと認められるのは1ヶ所だけです。
二拠点生活では住宅を所有するか賃貸とするか、そして住民票をどちらに置くかを、十分に考えておきましょう。

二拠点生活に活用したい支援制度

いざ始めるとなると、何かとお金がかかる二拠点生活。
できるだけ費用負担を減らすためにも、国や自治体の移住支援制度・補助金を上手に活用したいものです。
ここでは二拠点生活に活用したい支援制度をご紹介します。
地方創生移住支援事業
国が地方創生の一環として行っているのが、地方創生移住支援事業です。
移住者に支援金を支給する地方自治体に対して、国がその取り組みをサポートする制度で、単身移住の場合は最大60万円、世帯で移住する場合は最大100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大100万円を加算)が支給されます。
対象者は東京23区内に在住または通勤している人で、地方へ移住してテレワークを行うなどの就業要件を満たすと支援金が交付されます。
ただし、支援金を受け取るには地方自治体へ住民票の移動が必須となる場合が多いので注意してください。
また、自治体によっては事業を実施していない場合もあるので、要件の詳細も含めて国のホームページで確認しておきましょう。
自治体による支援制度
都道府県や市町村でも、移住や二拠点生活のためのさまざまな支援制度を用意しています。
空き家バンク
空き家バンクとは、自治体が運営している空き家を売りたい(貸したい)人と、空き家を買いたい(借りたい)人を仲介するサービスです。
格安で住める空き家を探せるのメリットがあり、地方なら庭付きの広い一軒家を月数万円で借りられることもあるでしょう。
さらに、自治体によっては空き家バンクで購入した物件の改修費用を一部補助してくれる場合もあるため、初期費用を抑えたい人は確認してみましょう。
住宅購入支援
住民票を移すことが条件となりますが、自治体によって住宅購入やリフォームの支援制度があります。
自治体や条件によりますが最大100万円の支援が受けれるなど、初期費用の負担を大きく軽減できるでしょう。
具体的な支援内容などは自治体によって異なるため、移住を希望する自治体のホームページをチェックしてみよう。
移住体験施設
地域でのリアルな暮らしを体験できる移住体験施設を、自治体や民間で用意している地域もあります。
施設によりますが、体験期間も数日~数か月と幅広いため、納得いくまで体験することが可能です。
体験施設の大半はお得な料金でお試し移住できる上に、施設によっては移住コンシェルジュによるガイドツアーなどの特典がついている場合もあります。
実際の生活を通して、その地域の風土や魅力、暮らしやすさなどを肌で感じられるので、二拠点生活をしてみたいけど場所は決まっていないという方は活用してみるのも良いでしょう。
まとめ
今回は、二拠点生活をする時に住民票をどちらにおけばいいのか、移した場合に活用できる制度などをご紹介しました。
- 住民票を置く場所は「滞在期間が長い拠点」
- 住宅に関する支援制度は住民票がある場所で利用できる
- 住宅や家族のライフプランに合わせて検討を

都心から1時間の小屋暮らし
ずっと探していた自分だけの秘密基地
やまのいえ-ちちぶ遊び小屋販売