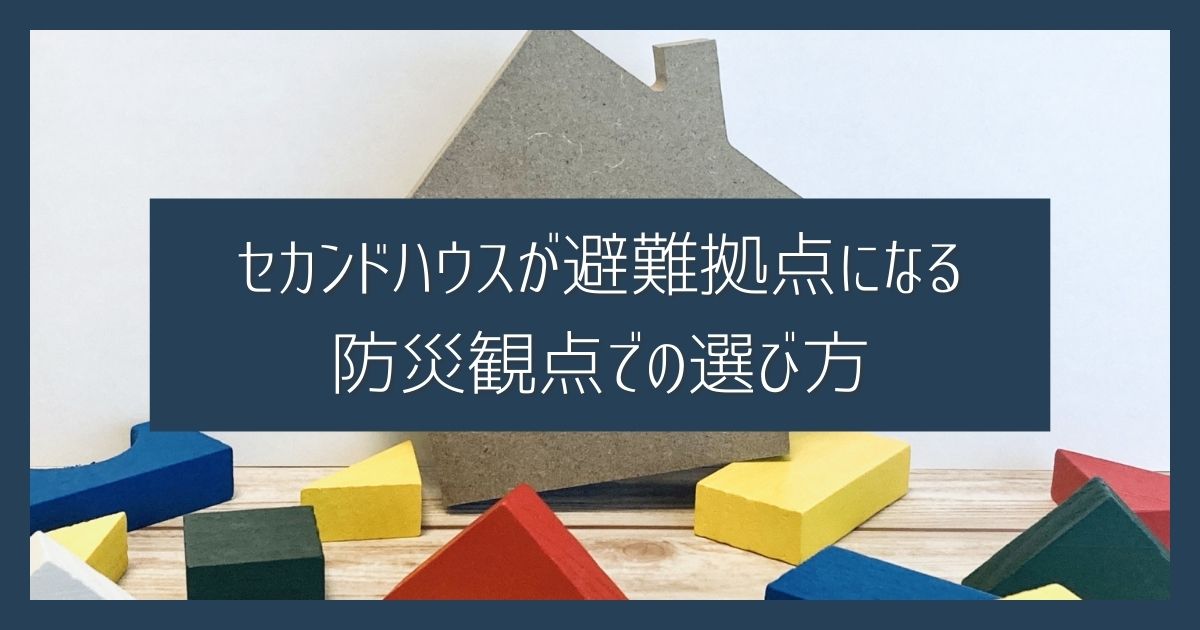日本は海外に比べて台風や大雨、洪水、土砂災害、地震、津波などの自然災害が発生しやすい国です。
全世界で起こったマグニチュード6以上の地震の18.5%が日本で起こり、全世界の活火山の7.1%が日本にあると言われています。
現在ではテレワークの普及によって、複数の生活拠点を持つ人も増えてきました。
その中で、セカンドハウスが避難拠点としての役割も担うと注目を集めています。
今回はセカンドハウスに関する税制優遇や、災害時の避難拠点としての選ぶポイントをご紹介します。
セカンドハウスと別荘の違い

セカンドハウスというと別荘を連想する方もいらっしゃると思いますが、厳密にはセカンドハウスと別荘は異なります。
ここではセカンドハウスと別荘の違いについてご説明します。
セカンドハウスは「第二の生活の拠点」
セカンドハウスは、「週末に住むため」や「平日の通勤のため」の家のことを指します。
普段の生活に欠かすことのできない、「第二の生活の拠点」であるため、生活必需品とみなされます。
そのため、セカンドハウスには税制優遇があります。
税制優遇があることにより、別荘よりも気軽にセカンドハウスを考えることができると言えます。
平日は、通勤や生活に便利な都会で過ごし、週末はセカンドハウスで田舎暮らしをする、
セカンドハウスなら都会と田舎暮らしのいいとこどり生活ができるのではないでしょうか。
別荘は「非日常的な贅沢品」
一方で別荘は、避暑などの目的で短期的に過ごす「非日常的な贅沢品」とされています。
夏休みなどの長期休みの時に、過ごしたりするイメージの人が多いのではないでしょうか?
余暇を過ごすイメージの強い別荘では、保養のための贅沢品のため、税制優遇等の措置もありません。
セカンドハウスは税制優遇がある

複数の生活する場所があるという点では別荘とセカンドハウスは同じように感じられますが、実生活の延長線上なのか(住居)、それとも贅沢品(住居以外)なのかで、様々な税制が異なってきます。
セカンドハウスは、「週末に居住するため郊外などに取得、また遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くに取得するもので、かつ毎月1日以上居住の用に供するもの」としており、セカンドハウスは居住用なので、税制の優遇が受ける事が可能です。
固定資産税
固定資産税は土地・家屋や償却資産にかかる地方税で、毎年1月1日時点の所有者に課税されます。
固定資産税の計算方法は以下のとおりです。
固定資産税=課税標準 × 1.4%(標準税率)
土地の課税標準額は売買実例価格などを基に算出されますが、宅地については地価公示価格などの7割が目安です。
「住宅用地に係る特例」が適用されると、次のとおり課税標準額がさらに減額されます。
- 小規模住宅用地(200m2以下の部分):課税標準額 × 1/6
- 一般住宅用地(200m2超の部分):課税標準額 × 1/3
※その他、一定条件を満たした新築住宅や認定長期優良住宅の建物の場合にも別途軽減措置が受けられる場合があります。
なお、地方税のため、自治体によっては異なる税率が適用されることがあります。
そのため、セカンドハウスを建設した場所の自治体に確認してみてください。
都市計画税
市街化区域内の土地・家屋には、固定資産税にあわせて以下のような都市計画税が課税されます。
都市計画税:課税標準 × 最高0.3%(制限税率)
特例適用後の課税標準額の減額割合は次のとおりです。
- 小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):課税標準額 × 1/3
- 一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):課税標準額 × 2/3
固定資産税と同じく課税主体は自治体で、市町村によって税率が異なります。
ただし、制限税率のため上限の0.3%を超えることはありません。
不動産取得税
不動産取得税は、売買や贈与、新築や増築などで発生します。
固定資産税や土地計画税のように毎年課税されるものではなく、取得後半年から1年半の間に都道府県から課税される地方税です。
不動産取得税:固定資産の評価額(課税標準税額)×4%(標準税率)
「住宅・住宅用地の特例」が適用されると、土地・建物それぞれに次のとおり減額されます。
<土地>
下記のいずれか大きい額に税率を乗じて得た額を減額・150万円・床面積の2倍の面積(200平方メートルまで)に相当する土地の価格
<建物>
- 新築:固定資産税評価額から1,200万円を控除
- 中古:住宅の新築時期により固定資産税評価額から最高1,200万円を控除
なお、2024(令和6)年3月31日までに取得した不動産に関しては、さらに次のような軽減措置が適用される可能性があります。
- 不動産取得税の税率の特例:4%→3%に軽減・住宅用地
- 商業地等の特例:固定資産税評価額(課税標準税額)を1/2に圧縮
要件などはセカンドハウスがある都道府県に確認してください。
生活拠点を複数持つことのメリット

複数の生活拠点を持つ最大のメリットは、都会と田舎の両方のいいとこどりができるということですが、他にも自然災害で被災した時の避難所の確保というメリットもあります。
複数の拠点があれば、平日は都会で仕事や学校に行きながら利便性の良い暮らし、週末には田舎で自然に触れながらゆっくりと家族と過ごしたり趣味を楽しむという暮らしを送ることができます。
そして自然災害で被災した場合、2つ目の拠点が被災していなければ避難する場所として利用することもできるでしょう。
避難場所が確保できているという安心感も心理的価値が高いと言えます。
昨今の自然災害、ウィルス対策など含め一か所に定住するというリスクがあることもわかってきました。
一昨年の千葉県の暴風、台風災害、茨城県の河川の氾濫災害、そして先日の能登半島地震等、日本ではいつどこで災害が起きてもおかしくない状況です。
そのような点でも複数の生活拠点を持つメリットがあると言えるでしょう。
▼にきょらぼメンバーがリフォームした小屋を販売中

避難拠点というセカンドハウスの役割

自宅が自然災害等で被災した場合、自宅は無事でも、同一エリアの電気・水道・ガス等のインフラで、何らかの障害が発生し、電気・ガス・水道の供給が断絶することも考えられます。
その場合は避難が必要になりますが、避難の方法は
① 自分で避難先を確保する
②地方自治体が用意する避難所等に避難する
のいずれかになると思います。
例えば①自分で避難所を確保するという場合には、遠方の知人や親戚を頼るというのも一つの手段でしょう。
しかし、避難期間が短期間であれば受け入れてもらいやすいかもしれませんが、長期間となってくると難しい場合もあるかと思います。
その時に自宅からある程度、距離の離れたセカンドハウスがあることで、一時避難場所として自宅同様とまではいかなくてもプライバシーを確保した上で避難生活ができるでしょう。
セカンドハウスを防災観点で選ぶ時のポイント

災害時の避難拠点としての選択肢にもなるセカンドハウスですが、出来れば災害に強い建物を選びたいですよね。
ここでは災害観点でセカンドハウスを選ぶ際のポイントをご紹介します。
まずはハザードマップを確認
日本のほぼ全域は、地震や台風などの災害のリスクが多い場所といえます。
しかし、その中でも比較的災害が少ない場所というのもありますので、その点に注目して土地を探しましょう。
そういった時にまず確認したいのがハザードマップです。
ハザードマップを見ると、土砂災害や洪水が起きた場合の被害範囲が予測できます。
ハザードマップを見ながら実際にその土地を歩いてみると、洪水発生時に水が流れ込む方向、土砂崩れの危険が高そうな場所などがイメージできるはずです。
道を一本挟んだだけでも、災害時の被害が大きく変わることがあります。
「このあたりに住みたい」との希望があれば、土地の高低差や道の勾配などをチェックしながら、なるべく災害リスクが低い物件を探すと良いでしょう。
新耐震基準で建築されている建物か
建物は「建築基準法」という法律に基づき建築されますが、災害の経験を経て改正され、現在は1981年6月から施行された新耐震基準が用いられています。
新耐震基準で建築される建物は、震度6~7程度の地震が発生した場合にも倒壊や崩壊がないレベルという想定です。
しかし、法改正以前の基準(旧耐震基準)で建築された建物の構造には十分な耐震性がない恐れがあります。
具体的には震度5程度に耐え得る建物としており、近年に発生した大きな地震に対応できるものではありません。
古い建物や中古物件については、新耐震基準による建物の検査、および改築などが必要です。
住んでいる地域から離れすぎない
災害時の避難拠点としてだけでなく、普段から利用することも考えた場合には自宅から移動のしやすい距離が良いでしょう。
二拠点生活をしている人の大半が自宅のある都・県内や隣接の県に拠点を所有しており、移動時間も車や公共交通機関で1時間~1時間半圏内が多くを占めます。
また、災害時は家族全員が一緒にいるとも限らないため、そういった点でも合流しやすい場所として自宅からあまり離れすぎていないエリアはおすすめと言えます。

日頃からの防災対策も忘れずに

ここまで災害時の避難拠点としてのセカンドハウスについてご説明してきましたが、災害に重要なのは日頃からの防災対策です。
3~7日分を目安に備蓄
大規模災害の際、電気や水道が復旧するのに、約7日程度かかると言われています。
一般的には、3日分の備蓄をすることが望ましいとされていますが、近年は、高層マンションでの電気システムの水没で復旧までに時間がかかったことから、7日程度の備蓄を呼びかけるようになりました。
家族の人数✕7日分の水分・食料の確保や、乾電池やバッテリーなどの電源の確保など、日ごろから防災グッズの準備をしておきましょう。
自宅・セカンドハウスがある地域の危険度を知る
同じ災害に遭っても、被害の程度は地域により異なります。
災害の内容や自宅がある場所の危険度により、被災時に自宅にとどまるか避難するかを適切に決める必要があるわけです。
自宅の危険度は、自治体が公表しているハザードマップで確認できます。
洪水や土砂災害、地震などが代表的です。
海が近い場所では、津波や高潮のハザードマップも用意されています。
浸水の危険度や土砂災害警戒区域内かどうかなど事前に確認しておきましょう。
もし自宅やセカンドハウスが危険な地域にある場合は、避難場所の確認をしておくことも忘れずに。
家族同士の連絡方法を決めておく
災害時は電話がつながりにくく、通信障害が発生するケースが予想されます。
そのため、いつも活用している携帯電話やSMS、LINEでは、なかなか連絡が取れないかもしれません。
公衆電話からの発信は優先的につながるものの、街中に設置されている公衆電話の台数が大きく減っているため、待ち時間が長くなりがちです。
被災した際に備えて家族の連絡方法を決めておくことも、防災対策の一つです。
以下は災害時に有効な連絡手段となります。
- 災害直後は通話よりショートメール
- 遠くの親戚や知人に連絡役を頼む
- 災害用伝言ダイヤル「171」や災害用伝言板を利用する
- SNSプロフィール欄やグループメッセージを活用する
災害用ダイヤルや伝言板は体験できる日が決まっているので、事前に試してみると良いでしょう。
その他、国土交通省では防災に役立つ情報から、災害時に必要となる情報や交通機関の情報を見ることができる『防災ポータル』を設けています。
日本のどこにいても災害は避けられないと言われていますが、日ごろの備えによって減災することは可能です。
定期的に防災グッズや連絡方法を確認し、災害に備えましょう。
まとめ
今回はセカンドハウスに関する税制優遇や、災害時の避難拠点としての選ぶポイントをご紹介しました。
- セカンドハウスは別荘と違い税制優遇がある
- 災害時にはセカンドハウスが避難拠点をして機能することも
- 日頃の災害対策も忘れずに

都心から1時間の小屋暮らし
ずっと探していた自分だけの秘密基地
やまのいえ-ちちぶ遊び小屋販売