2025年に建築基準法の改正が施行されます。
この法改正では、省エネ性能の向上や耐震性の強化、さらには木材利用の促進など、建築分野全体にわたる改正となっています。
二拠点生活の住宅(セカンドハウス)を中古で購入検討している人の中には、合わせてリフォームを考えているという人も多いでしょう。
リフォームを考えている場合、法改正によってどのような影響があるのでしょうか。
今回は2025年改正の建築基準法について、法改正のポイントとリフォームへの影響、どんなメリットがあるのかを解説します。
そもそも建築基準法とは

建築基準法とは、日本で建築物を建設、改修、または解体する際に遵守しなければならない基準や規制を定めた法律です。
建築基準法は1950年に制定され、それ以降も、社会情勢を反映して改正を繰り返しています。
私たちが暮らすためには、家や会社、学校など、さまざまな建築物が欠かせません。
建築基準法は、それら建築物についてルールを定め、安全で安心な生活を送れることを目的としています。
具体的には、地震や火災、風災などの災害時においても建物が崩壊したり、人命に危険を及ぼさないようにするための構造や材料の規定を定めています。
また、都市景観の保全や環境負荷の軽減、生活環境の向上を目指すための基準も含まれています。
建築基準法の対象範囲
建築基準法は、住宅やビル、工場、商業施設、公共施設など、あらゆる建築物を対象としています。
新たに建築物を建てる場合はもちろん、増築や改修、さらには解体する際にもこの法律に従う必要があります。
また、建築物が建つ場所によっても適用される基準が異なります。
都市部では防火地域や準防火地域といった指定がされており、これに従った建築基準が設定されています。
逆に、農村部や山間部では、景観保護の観点から建物の高さやデザインが制限されることもあります。
2025年建築基準法改正の背景

2025年の建築基準法改正は、環境への配慮や建物の安全性に配慮しています。
ここでは、法改正の背景を解説します。
住宅は量より質へ
4号特例ができたのは、1983年と今からおよそ40年前です。
当時は高度経済成長期で、住宅については質より量が求められ、新設住宅の件数は高い水準となっていました。
このようなニーズに応えるために、建築行政の迅速化と小規模事業者の負担軽減を目的として、4号特例が導入されました。
この制度により、対象の住宅は建築確認を省略できるようになったのです。
しかし現在は自然災害が激甚化しており、住宅にはより高度な性能が求められています。
そこで、すべての住宅をより厳格な基準にのっとって建築するために、4号特例が縮小されることになりました。
省エネ対策の必要性
2025年の建築基準法改正の背景には、省エネ対策の義務化への対応があります。
たとえば、2030年の温室効果ガス46%削減や、2050年のカーボンニュートラルなどです。
それぞれの目標を達成するために、建築分野での省エネ対策が求められており、今後すべての新築住宅において、省エネ基準への適合が義務付けられます。
建物構造の耐力向上が必要
近年、高断熱化や太陽光発電システムの普及などにより、住宅重量の増加が進んでいます。
その結果、建物構造の耐力や安全性を高める必要性が出てきました。
構造の耐力や安全性は、人命に関わります。
建築確認や完了検査を通じて、確実にチェックできる環境を整えなければなりません。
そこで今回の法改正により、4号特例が適用されていた木造建築物についても、建築確認・完了検査の省略制度を見直すことになりました。
何が変わる?2025年建築基準法改正のポイント
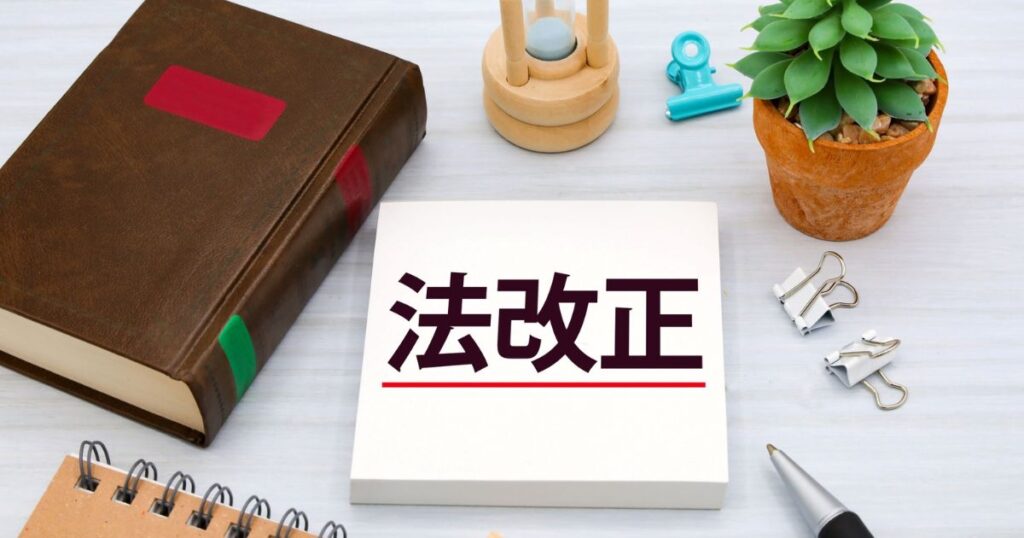
2025年の建築基準法改正は、特例や審査が変更になります。
4号特例の見直し
現行の建築基準法では、4号特例の条件を満たす建物(4号建物)の建築確認申請が簡略化されています。
建築確認申請とは、建物が合法的かどうかを着工前に図面で判断することです。
この特例により、小規模な住宅の新築やリフォームがスムーズに進められる一方で、耐震性や安全性が十分に確認されないまま建築されるケースもありました。
4号特例とは
4号特例とは、以下の基準を満たす建物の審査を簡略化するものです。
- 2階建て以下の木造住宅
- 延床面積:500平方メートル以下
- 建物の高さ13m以下
- 軒高9m以下
2025年4月以降の法改正後は、一般の木造住宅の多くが4号建物から「新2号建築物」、または「新3号建築物」に区分されることとなります。
建築確認の対象見直し
今回の改正で、現在4号建物の住宅で大規模なリフォームを行う際に、これまで不要だった確認申請が必要になる可能性が出てきます。
前述のとおり、2025年4月以降、一般の木造住宅の多くは「新2号建築物」「新3号建築物」に区分されるためです。
「新2号建築物」と「新3号建築物」の条件
- 新2号建築物:木造二階建て・木造平屋建て(延床面積200平方メートル超)
- 新3号建築物:木造平屋建て(延床面積200平方メートル以下)
新2号建築物に該当する建物は、建築確認時の構造耐力関係規定をはじめとする、構造計算審査が必須です。
構造計算審査とは、建築基準法で定められた基準を満たすかどうかを確認する審査を指します。
なお、新3号建築物に該当する建物は、審査を省略できます。
つまり、確認申請を省略できるのは、3号の平屋かつ延べ面積200平方メートル以下の建築物に限られることになります。
その結果、リフォーム全体にかかる費用や工事スケジュールにも影響が出てくる可能性があります。
構造・省エネ図書の提出の変更
2025年の建築基準法改正では、構造・省エネ基準への適合が求められます。
- 新2号建築物:原則として構造関係規定等の図書の提出および審査が必要になる
- 新3号建築物:これまでと同様に必要書類の提出および審査を一部省略できる
同時に、壁と柱の構造基準も見直されます。
今後は、柱の断面寸法と耐力壁(地震や積雪、強風などに対抗する壁)の量が新基準以上であることを、以下のいずれかの方法で確認する必要があります。
- 算定式で算定する方法
- 早見表で確認する方法
- 構造計算で確認する方法
なお、延床面積が300m²を超える木造平屋・2階建て住宅は、構造計算(許容応力度計算)が必須になります。
参考:2025年4月(予定)から4号特例が変わります|国土交通省
既存不適格建築物に対する現行基準の一部免除
既存不適格建築物とは、過去の基準では合法だったものの、現在の建築基準法には適合しない建物を指します。
このような建物の中には、接道義務や道路内建築制限に違反しているものが多く残っていました。
そのため、これまで省エネ改修や耐震改修を行う際に現行法に適合させることが難しく、リノベーションを断念するケースが頻発していました。
しかし、今回の改正では、空き家問題や既存ストック住宅の再利用を促進するため、特定の条件下において現行基準を適用しない免除規定が導入されました。
これにより、接道義務に違反する土地でも大規模リノベーションを行うことが可能となり、古い建物の再利用が進むことが期待されています。
法改正でリフォームにおけるメリットは?

リフォームをする側から見ると、特例の適用が縮小となったり、構造・省エネ図書の提出が義務化となることで、費用の増加や工期の延長など負担が増えるように感じられる改正法。
では、改正によるメリットはどんなものがあるでしょうか?
① 省エネ性能の向上によるコスト削減
2025年の建築基準法改正では、省エネ基準がより厳しくなることで、リフォーム後の建物が高い断熱性能を持つことが義務化されます。
これにより、冷暖房効率が大幅に向上し、年間を通じてエネルギー消費量を抑えることが可能です。
特に、断熱性能が強化されることで、室内温度を快適に保ちやすくなり、夏場や冬場のエアコンの使用頻度が減ることから、光熱費が大幅に削減されるメリットがあります。
これは、エネルギーコストの上昇が続く中で家計にとって大きなメリットと言えるでしょう。
さらに、省エネ性能の高い住宅に対しては、国や地方自治体から補助金が支給される制度もあり、これを活用することで、リフォームの初期費用を抑えることができます。
②耐震性の向上による安心感
今回の改正では、4号特例が縮小され、すべての新築住宅や商業建築に対して、耐震性や省エネ性能を含む建築基準が適用されるようになります。
これまで、木造住宅の構造審査においては、建築設計事務所の判断に任されていた部分が多く、設計者によって品質にばらつきが生じることもありました。
しかし、改正後は行政が直接確認を行うため、一定の基準を満たしていればどの建築会社を選んでも耐震性能が保証されるようになります。
これにより、地震大国である日本において、より安全な住まいを手に入れることができ、安心して暮らすことができるようになります。
③長期的な資産価値の向上
省エネ性能や耐震性の向上は、単に快適で安全な住まいを提供するだけでなく、将来的な資産価値の向上にも寄与します。
特に、日本の不動産市場では、エコ住宅や耐震住宅の需要が高まっており、環境に優しく耐震性の高い建物は、売却時に有利な条件で取引されることが期待されます。
さらに、2025年の建築基準法改正後、建築確認申請が必要なリフォームを行わずに違法状態で増築や改修を行った建物は、売却時に買い手がつきにくくなる可能性があります。
セカンドハウスの購入でリフォームを考えている人だけでなく、自己資産として売却する時も含め考えておくと良いでしょう。
リフォームに関する補助金制度

ここではリフォーム・リノベーションに利用できる支援制度をご紹介します。
①子育てエコホーム支援事業
子育て支援および2050年カーボンニュートラルの実現の観点から、子育て世帯や若者夫婦世帯の省エネ改修などに対する補助制度。
対象工事
【いずれか必須】
- 開口部の断熱改修
- 外壁・屋根・天井または床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置
【1〜3と同時に行う場合のみ対象】
- 子育て対応改修(ビルトイン食洗機・宅配ボックスなど)
- 防災性向上改修(防犯安全ガラスへの交換)
- バリアフリー改修(手すり設置、段差解消など)
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
補助額と上限
原則1戸あたり20万円(工事の内容や属性に応じて最大60万円)
▼制度の詳細、申請条件などは以下で確認
子育てエコホーム支援事業
②先進的窓リノベ事業
先進的窓リノベ事業は、断熱性能の高い窓に交換するリフォームに対する補助制度。
対象工事
- ガラス交換
- 内窓設置
- 外窓交換
- ドア交換(※窓の改修と同時に行った場合のみ対象)
補助額と上限
200万円/戸(上限)
※補助額5万円未満の場合は、補助申請はできません。
▼制度の詳細、申請条件などは以下で確認
先進的窓リノベ事業
③長期優良住宅化リフォーム推進事業
良質な住宅ストックの形成や、子育てしやすい生活環境の整備等を図るため、 既存住宅の長寿命化や省エネ化等に資する性能向上リフォームや子育て世帯向け改修に対する支援制度。
対象工事
【性能向上リフォーム工事費】
- 劣化対策や耐震性、省エネ対策など特定の性能項目を一定の基準まで向上させる工事
- 1.以外の性能向上工事(バリアフリー改修工事・インスペクションで指摘を受けた箇所の補修工事・テレワーク環境設備改修工事・高齢期に備えた住まいへの改修工事など)
【三世代同居対応改修工事費】
- キッチン・浴室・トイレ・玄関の増設工事
【子育て世帯向け改修工事費】
- 若者・子育て世帯が実施する子育てしやすい環境を整備するための工事
【防災性の向上・レジリエンス性の向上改修工事】
- 自然災害に対応する改修工事
補助額と上限
補助対象リフォーム工事費用などの合計の3分の1
リフォーム後の住宅性能によって以下のように異なる
①長期優良住宅(増改築)認定を取得しないものの、一定の性能向上が認められる場合
100万円/戸
② 長期優良住宅(増改築)認定を取得した場合
200万円/戸
更に増額となる条件もあるため、詳細は要確認。
※申請はリフォーム業者が行うため、事前に業者へ申請対応が可能かを確認する必要があります。
▼制度の詳細、申請条件などは以下で確認
長期優良住宅化リフォーム推進事業
まとめ
今回は2025年改正の建築基準法について、法改正のポイントとリフォームへの影響、どんなメリットがあるのかを解説しました。
- 2025年改正の建築基準法は、住宅安全面の向上と省エネがポイント
- 建築確認対象が広がったため、より安全性の高い建築・リフォームが期待される
- 省エネ適用は補助金の対象にもなるため、自治体をチェック

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!

