二拠点生活や多拠点生活が注目を浴びている一方で、日本の空き家は増え続けています。
2018年住宅・土地統計調査(総務省統計局)によると、全国の住宅の13.6%が現状、空き家となっているという結果が出ました。
また空き家は、まちの景観や衛生に悪影響を及ぼしたり、防災・防犯上のリスクも高まったりと、今や大きな社会問題となっています。
こうしたことから2015年に空き家法が制定され、今年2023年に更に強化された法改正がなされることとなりました。
今回は、セカンドハウスでも無視できない、空き家法改正による影響やどう対策すればよいかご紹介します。
空き家法とは

空き家法とは、正式には「空家等対策の推進に関する特別措置法」といい、2015年から施行された増え続ける空き家に対する適切な対応を定めた法律です。
具体的には、以下のようなことを定めています。
- 空き家の実態調査
- 空き家の所有者へ適切な管理の指導
- 空き家の跡地についての活用促進
- 適切に管理されていない空き家を「特定空家」に指定することができる
- 特定空家に対して、助言・指導・勧告・命令ができる
- 特定空家に対して罰金や行政代執行を行うことができる
法律制定の背景には、空き家が増え続ける一方で責任の所在や行政の対応方法が確立されていなかったことがありました。
これらを明確にすることで、それまで個人の管理領域だった空き家に対し、行政が関与できるようになりました。
空家等対策特別措置法の目的は、適切な管理が行われていない空き家やそれに附属する土地・工作物などに対し、適切な管理・活用を促進することです。
適切な管理が行われていない空き家は、防災・衛生・景観などの観点から、住民の生活環境に悪影響が及ぶ可能性があります。
そのため、空き家を放置しないような対策や、放置されている空き家に対して措置を講じることができるように定められているのが空き家法となります。
空き家を放置してしまうと、最終的には特定空家へ指定され、命令違反による罰金や行政執行が行われてしまいます。
そうならないためにも、所有する家はきちんと管理することが大切です。
2023年の法改正でセカンドハウスも危ない?

空き家法というと、例えば「誰も住んでいない遠方の実家」というイメージが強いかと思いますが、場合によっては長期間使っていないセカンドハウスも対象になってしまう可能性があります。
特に2023年の改正法で空き家管理が厳密となったため、他人事ではなくなったのです。
ここでは、2023年の改正法で具体的にどう変わったのかご説明します。
①管理不全空き家の新設
改正で最も大きなポイントが、「管理不全空き家」の新設です。
法改正で初めてできた管理不全空き家は、管理が適切でなく今後放置されることで特定空き家になる可能性のある空き家、いわゆる「特定空き家予備軍」です。
そもそも「空き家」の定義とは、「状態は悪くないが1年程度住んで(使われて)いない」状態を指します。
状態が悪く周囲に悪影響を及ぼすような空き家を「特定空き家」としており、「空き家」と「特定空き家」の間に位置するのが「管理不全空き家」となります。
管理不全空き家に指定された空き家は、特定空き家と同様に固定資産税の優遇から外れるなど、これまで以上に空き家の不適切管理への姿勢が厳しくなります。
つまり、今までよりも対象となる空き家の範囲が拡大したため、セカンドハウスもしばらく使用していない場合、管理不全空き家となる可能性があるということになります。
②特定空き家の除却などの円滑化
市区町村長に「特定空き家」に関する報告徴収権が与えられます。
これにより資料の提出などを求めることができ、勧告等が円滑に行われるようになります。
また、除却などの代執行が円滑に進むように、命令等の事前手続を経る時間がない緊急時の代執行制度が創設され、所有者不明時の代執行、緊急代執行の費用は、確定判決なしで徴収できるようになります。
③空き家の活用を拡大
市区町村が、中心市街地や地域の再生拠点、観光振興地区などの「空き家等活用促進地域」の指定権限を持つことになります。
また、同地域の指定や空き家等活用促進指針を定め、用途変更や建て替えなどを促進できるように、接道規制や用途規制の合理化を図ることができるようになります。
加えて、市区町村長は、区域内の空き家等所有者らに対して、指針に沿った活用を要請することができるようになります。
さらに、空き家等の管理・活用に取り組むNPOや社団法人などの団体を、市区町村長は「空き家等管理活用支援法人」に指定できるようになります。
空き家対策は地域促進につながることから、地方自治体への権限移譲が図られます。
なぜ固定資産税が6倍になる?

土地に対する固定資産税や都市計画税が課税される年の1月1日において、住宅やアパート等の敷地として利用されている住宅用地には特例措置があり、敷地面積によって固定資産税が1/3~1/6に軽減されています。
これは、「住宅用地の特例措置」と呼ばれているものです。
管理不全空家指定されるとこの特例を受けられなくなるため、最大固定資産税評価が1/6とされていた優遇がなくなり、実質的に固定資産税が増額となります。
例えば、評価額1,000万円、200㎡以下の土地に建っている家の場合、税率1.4%で住宅用地特例が適用されると約2.3万円が固定資産税額です。
しかし管理不全空家に指定されて住宅用地特例が解除されると固定資産税額は14万円となり、毎年10万円以上税金が上がってしまうことになります。
固定資産税は毎年ですから、10年間の差額で考えると100万円以上の負担増になってしまいます。
セカンドハウスの草木を放置したら・・・

今回、法改正がされた空き家法。
適切に管理をしていないと、固定資産税が最大6倍になる可能性があるということがわかりました。
セカンドハウスとして利用している方には無関係と思われがちですが、子供の進学や仕事の都合で2~3年に行かなかった、というのはそんなに珍しいことではないと思います。
しかし、セカンドハウスを持っている人のほどんどが、日常は都会に住んでいるため、地方の自然豊かな場所を選ぶ場合が多く、そういった環境は庭木や雑草の成長の速さを考える必要があります。
決しては空き家ではないセカンドハウスも、訪れる頻度が低くなり庭木や雑草の手入れを怠ると、一見すると管理されていない空き家に見えてしまうだけでなく、越境して道路や隣接した敷地へ草木が伸びて被害を与えることもあります。
またセカンドハウスの場合ではあまりありませんが、「特定空き家」に指定された場合、最悪のケースでは行政代執行で強制的に解体されてしまうことも。
行政代執行でかかった費用は所有者が支払わなければならない為、所有している方は特定空き家に指定されないよう対処する必要があります。
庭木が切られて費用請求がきた!?
空き家法改正とは別ですが、民法「竹木の枝の切除及び根の切取り」の改正により、2023年4月1日から一定の条件を満たす場合には、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることができるようになりました。
改正前は、「庭木の所有者に枝を切ってもらうようお願いをして切ってもらう」しか方法はなく、越境された土地の所有者が自ら枝を切ることはできませんでした。
改正によって「所有者に枝を切除させる」という原則を維持しつつ、
- 催告しても、相当の期間(2週間程度が基本)内に切除されない
- 所有者の所在がわからない
- 急迫の事情がある(台風によって折れた枝が建物を破損する恐れがある等)
といった場合には、切り落とすことができるようになりました。
そのため、セカンドハウスの庭木が境界を越えて近隣の敷地や道路にせり出している等で催告が来た場合、なかなか対応ができずにいるうちに、庭木が伐採されその費用を請求されるというケースもあります。
自然豊かな環境では庭木や雑草の成長も早いため、管理を怠ると近隣への被害だけでなく、多額に費用請求が来てしまうこともあるということです。
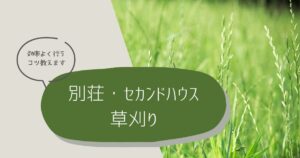
セカンドハウスはどう対策する?

セカンドハウスの維持にはコストがかかるため、長期間放置するのは望ましくありません。
「管理不全空き家」に指定されるリスクの他にも、管理がされていない家は老朽化が急速に進んでしまうため、資産価値としても下がってしまいます。
そこで長期間使っていないセカンドハウスの対策方法をご紹介します。
定期的に訪れて管理をする
なかなか家族との都合がつかずに足が遠のいていた場合でも、通える範囲であれば管理の為に訪れるのが一番良い方法でしょう。
もし、仕事がテレワーク可能な場合は、会社に出勤する代わりにセカンドハウスへ行って仕事をするというのも、いつもと違った環境で気分転換になるかもしれません。
管理代行サービスを利用する
それでも、実際に訪れるのはなかなか難しい、出張・転勤でしばらくは遠方にいるという場合は、別荘管理の会社等に依頼をするのも1つの方法です。
屋外点検だけのサービスや、庭木・草刈りのなど必要に応じたサービスを実施してくれる会社もありますので、ご自身のニーズと予算にあったサービスを探すと良いでしょう。
貸別荘にする
あまり使用する予定がない場合は、貸別荘として貸し出すことも方法の1つです。
利用する人がいることで建物の老朽化を防ぎ、収益も得られるため今注目されている活用方法です。
中でも1日から別荘を貸し出す「日貸し」は、短期間から活用を始められるため、多くの人が取り組みやすい方法です。
しかし、別荘を日貸しで貸し出す場合は、法律上「民泊」という取り扱いになり、「旅館業法」の制限が課せられます。
貸別荘の場合は、旅館業法の「簡易宿所営業」許可をとると良いでしょう。
また、清掃等に関しては、民泊サービスを運営している会社に外注することもできるため、収益の範囲内で依頼できるサービスがあるか確認すると良いでしょう。
売却する
以前はセカンドハウスとして月1回以上訪れていたとしても、家族のライフステージの変化で訪れることがなくなってしまうこともあるかと思います。
それでも思い出の詰まった家だからと、訪れることなくそのままにしておく人も多くいます。
しかし、放置している期間が長ければ長いほど建物の老朽化も進み、「管理不全空き家」の指定リスクや、資産価値が下がっていきます。
そうなる前に、家族と話し合った上で売却するというのも方法の一つです。
まずは、地場やセカンドハウスに強い不動産屋に相談して、現在の物件価値を確認してみるのも良いでしょう。
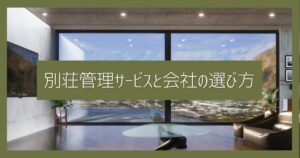
まとめ
今回は、セカンドハウスでも無視できない、空き家法改正による影響やどう対策すればよいかご紹介しました。
- 空き家法の改正によって税優遇の対象外となる空き家が増える
- 2~3年使用していないだけでも固定資産税が6倍になる可能性
- 利用頻度が下がったセカンドハウスは貸す・売る等の検討も

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!

