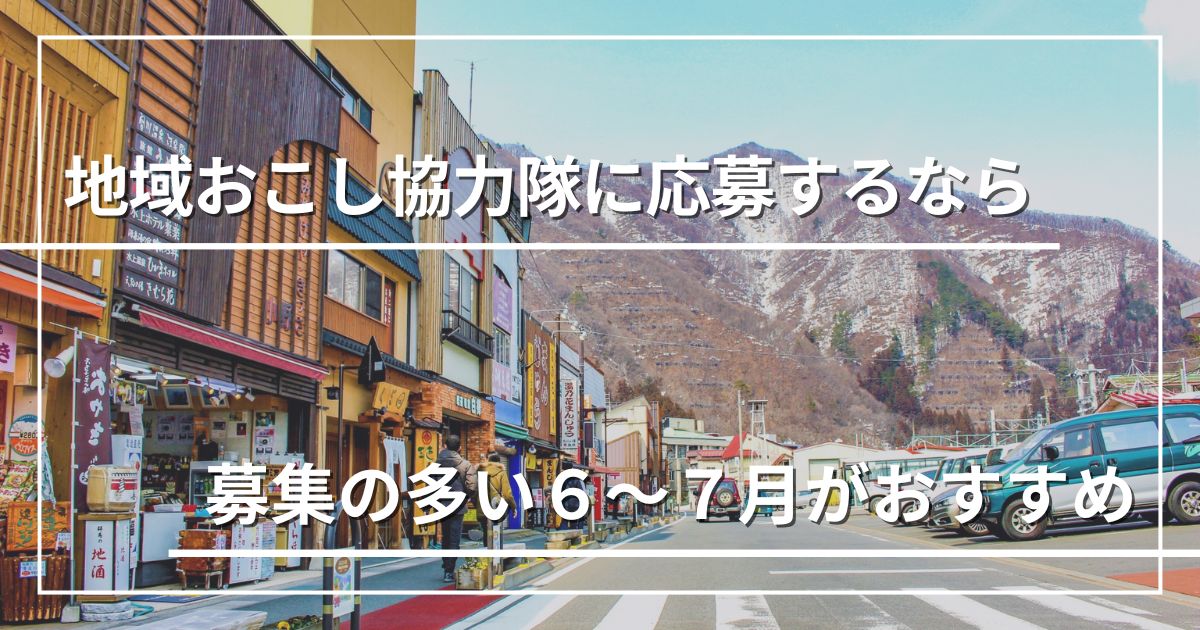年々、隊員募集や希望者が増えている「地域おこし協力隊」
総務省の発表によると、令和5年度に全国で活躍している人は前年から753人増の7,200人となっています。
また、取り扱い自治体数も増加傾向にあり、地域創生や地域活性化を考えている自治体が多くなっていることが伺えます。
今回は地域おこし協力隊とはどのようなものかと、地域おこし協力隊に興味ある方に向けて2024年5月末現在の募集情報をご紹介します。
地域おこし協力隊とは

地域おこし協力隊とは、地方自治体の課題に取り組むために、全国からの応募者が派遣され、その地域への定住・定着を目指す制度です。
地域おこし協力隊員は、地域の特性や魅力を活かした活動を通じて、地域の活性化や定住促進、観光振興などを目指します。
具体的には、地域の特性や魅力を活かした観光資源の開発やPR、農業や漁業の振興、地域の文化や歴史の保護や活用、地域の子育て支援や高齢者支援など、様々な分野で活動を行います。
地域おこし協力隊は国の制度
地域おこし協力隊は、国が定め、地方自治体が実施している制度です。
この制度は2009年に開始され、2023年度の取組団体数(受入自治体数)は1,164団体で、7,200名の隊員が活躍しています。
政府はこの隊員数を2026年度までに10,000人に増やすという目標を掲げており、地域おこし協力隊等の強化を行うこととしています。
地域おこし協力隊の実情
隊員の男女比は6:4で、幅広い世代の隊員が活躍していますが、約7割は20~30代の若い世代となっています。
地域おこし協力隊の活動期間は、概ね1年から3年間となっており、活動期間中は各自治体で定められた給料が支払われます。
また、地域おこし協力隊の活動終了した人の6割が、活動地に定住しているというデータもあり、地方移住への足掛かりとなっています。
地域おこし協力隊はどんなことをするの?

地域おこし協力隊は、地方自治体が実施する制度であり、地域の活性化や地域社会の課題解決に貢献することを目的としています。
具体的には、以下のような活動が行われます。
①地域振興のための企画・実行
地域おこし協力隊は、地域の課題や問題点を把握し、その解決に向けてプロジェクトを立ち上げ、実行することが求められます。
例えば、地域の特産品を活かしたイベントの開催や、地域の観光資源の活用などが挙げられます
②地域の魅力の発信・PR
地域おこし協力隊は、地域の魅力を発信することで、地域に人を呼び込むことにも貢献します。
ブログやSNSなどを活用した情報発信や、地域PR用のパンフレットや動画制作などを行います。
③地域住民との交流・コミュニケーション
地域おこし協力隊は、地域住民との交流を大切にし、地域に根ざした活動を行います。
地域住民の声を聞き、意見を交換することで、地域の課題解決につながるアイデアを出し合ったり、地域の人間関係の構築に貢献したりします。
④地域の組織・団体の支援
地域おこし協力隊は、地域の組織・団体の活動支援も行います。
例えば、地域の農業団体や商工会のイベントの協力や、地域の子育て支援グループの運営支援などがあります。
地域おこし協力隊の雇用形態や給料

地域おこし協力隊員として活動する場合、どのような働き方・収入になるのか気になりますよね。
ここでは地域おこし協力隊の雇用形態や給料、二拠点生活をしながら兼業・副業はOKかなどをご紹介します。
期間
地域おこし協力隊は移住を促進するための制度であるため、活動できる期間が最長3年と決まっています。
給料
地域おこし協力隊には国から活動費として、年480万円(令和4年度※年によって変動あり)が支給されます。
活動費とは、活動する中で必要な費用を賄うお金となります。
その活動費の内訳は200万円が活動経費等、280万円が報酬の上限とそれぞれ決まっています。
そのため、協力隊の給料は最大280万円となります。
しかし、実際の給料額の平均は14万円~16万円というところが多いようです。
その他、住宅費用として5万円の補助や、移動費などの手当もあります。
ただし、自治体によって支給額や手当は異なるため確認が必要です。
雇用形態
地域おこし協力隊の働き方は大きく分けて「一般職」と「雇用関係なし」の二つに分けられます。
◎一般職
自治体に会計年度任用職員として任用されます。
そのため、扱いとしては一般の公務員と同じ扱いとなり、社会保険も公務員と同等となります。
その代わり、自治体によっては副業ができないところもあり、その場合は地域おこし協力隊の任期後に生計を立てる手段を任期中に確保するのが難しいケースもあります。
◎雇用関係なし
雇用契約がなく、地域おこしに関する業務を委託されるという形です。
個人事業主であるため、業務や働く時間の采配も自分で決めることができ、もちろん副業が可能です。
しかし、個人の裁量が大きい分責任も大きくなります。
また、自分で国民年金・国民健康保険・NPOなどで社会保険に入り、費用も自己負担で支払わなければなりません。
応募資格や募集方法は?

応募資格の条件
自治体よってスキルや経験などの条件がある場合もありますが、一般的には以下のような条件、応募資格を設けていることが多いです。
応募条件
- 満18歳以上(自治体によっては45歳未満の制限もあり)
- 健康で、継続して活動できる見込みがあること
- その地域に関心や縁があること
- 過去に犯罪歴がないこと
- 任期満了後に定住や起業の意思がある方
- 応募する隊の活動計画や仕事内容に合わせて、応募書類に必要事項を記入し提出すること
- 普通自動車免許
ただし、各地方自治体よって異なるので応募前には、必ず地域おこし協力隊の公式サイトや担当窓口で確認しましょう。
募集期間
地域おこし協力隊の募集期間は、自治体や県によって異なります。
募集開始時期は、年度によって異なりますが、多くの自治体では6月から7月にかけて募集を開始し、9月から10月にかけて締め切りとなります。
応募から選考まで
地域おこし協力隊員の募集方法や選考の流れは、各地方自治体や地域おこし協力隊の事務局によって異なりますが、一般的には以下のような流れになります。
①募集情報の公開
地域おこし協力隊員の募集は、自治体の公式ホームページや地域おこし協力隊の公式サイト、求人情報サイト、新聞、広告などを通じて、募集情報が公開されます。
②応募書類の提出
募集に応募するためには、応募書類を提出する必要があります。
応募書類には、履歴書や職務経歴書、志望動機や意欲、活動計画の提案などが含まれます。
応募書類の提出締切は、募集期間中に設定されます。
③書類選考
提出された応募書類を基に、地域おこし協力隊の事務局や自治体が書類選考を行います。
応募者の経験やスキル、志望動機、活動計画の内容などを総合的に判断して、選考結果を発表します。
④面接
書類選考で通過した応募者には、面接の機会が与えられます。
面接では、地域おこし協力隊の事務局や自治体の担当者が応募者の人柄やコミュニケーション能力、活動計画の具体性などを評価します。
⑤選考結果の発表
面接後、合否が発表されます。
合格者は地域おこし協力隊員として採用され、研修を受けた後、任期内で地域での活動に従事します。
不合格者には、理由や改善点などのフィードバックが与えられることがあります。
ただし、地域おこし協力隊の募集方法や選考は、各自治体や地域おこし協力隊の事務局によって異なります。
応募前には、必ず公式サイトや担当窓口で確認することをおすすめします。
地域おこし協力隊情報(2024年5月末現在)

宮城県大和町|ふるさと納税の返礼品開発などを通し、「町の魅力発信と交流人口の増加」に向けた活動
大和町は宮城県のほぼ中央に位置し、町のシンボル七ツ森や船形山そして吉田川に代表される恵まれた自然と古(いにしえ)からの歴史と文化の豊かな町です。
そんな魅力のある大和町ですが、これまで地域おこし協力隊を受け入れたことがありません。そこで、ふるさと納税を通して魅力的な大和町を発掘・発信するための地域おこし協力隊を募集します。
「大和町で生まれ育ち、一度都会に出たものの、大和町に戻り何か活動をしたい。」「今は都会にいるけれど、地元大和町に何か貢献したい。」そんな方も歓迎です。大和町初の隊員として、この町に飛び込んでみませんか?
1.活動内容
「町の魅力発信と交流人口の増加」
- ふるさと納税返礼品の発掘・開発およびふるさと商品協議会活性化
- 交流人口増加に向けた町の魅力の情報発信に関する活動
- その他町のPR等に関する活動
2.募集要件
- 地域おこし協力隊推進要綱に定める三大都市圏をはじめとする都市地域および指定都市等に住民登録をしている方。
- 任用の日までに本町に生活の拠点を移し、住民登録することができる方。
- 任用の日において20歳以上40歳未満の方。
- 任用の日において普通自動車運転免許を有している方。
- 心身ともに健康で積極的に活動できる方。
- パソコン、SNS等の一般的な操作が出来る方。
- 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方。
3.募集人数
1名
4.募集期間および活動開始
令和6年5月22日(水曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
※応募があった方から面接等を行い、任用候補者が決定した場合募集を終了します。
開始予定日 候補者として決定後2ヶ月程度を想定(応相談)
茨城県北茨城市|廃校を活用した芸術活動拠点で創作活動をしながら、「芸術によるまちづくり」
北茨城市では、岡倉天心が日本美術院を置いた景勝地「五浦」、三大童謡詩人の一人である野口雨情、江戸時代から続く伝統的な陶器を継承する「五浦天心焼」など、本市が有する芸術的な風土・資源を活かして、「芸術によるまちづくり」を推進しています。
その担い手として、廃校を活用して整備したアトリエで創作活動をしながら、芸術によるまちづくりをプロデュースしてくれる芸術家を「地域おこし協力隊」として募集します。
山々に囲まれ、のどかに広がる田園風景。市の北西部に位置する関本町富士ケ丘。
そこに、ひっそりとたたずむ旧 北茨城市立富士ケ丘小学校。平成28年3月に廃校となったこの学校を、芸術活動拠点「期待場」として整備しました。
校舎の1階は、陶芸設備やシェアオフィスが設置され、2・3階は各教室をアトリエとして整備しました。
体育館は、ギャラリーとして整備。北茨城市出身のアーティスト石井竜也さんの作品が展示されている他、貸しギャラリーとしても利用可能です。
「期待場」という名称は、石井さんが市名にかけて、また、これからが期待される子どもたちの希望の場所として存在してほしいという願いを込めて名づけてくださいました。
1.活動内容
北茨城市の地域資源を生かし創作活動を行い、その作品を市内で開催されるイベント等に出展、または自ら北茨城市でアートイベント等を主催し、企画立案・運営・コーディネートを行う活動
- 芸術によるまちづくりの推進に寄与する活動
- 芸術によるまちづくりの情報発信を行う 活動
「芸術による里山づくり(※)」事業への協力を行う活動
※関本町富士ケ丘揚枝方地区において、地域が中心となって実施している、地区の環境全体がアートと呼べるような里山づくりを目指した活動
- 北茨城市が行う学校教育事業及び生涯学習事業等への協力を行う活動
- 北茨城市が行う移住関連施策への協力
2.募集要件
- 3大都市圏をはじめとする都市地域等(※)に現に住所を有する者であって、委嘱の後において、速やかに本市に住民票を異動できる者であること。
- 心身が健康で、かつ、協力隊の活動に意欲と情熱を持って参加できると認められる者であること。
- 土日及び祝日の行事参加など、不規則な勤務に対応できること。
- 普通自動車運転免許を有していること。
- パソコン等を用いた情報発信に必要な、一般的な操作ができること。
3.募集人数
1名
4.募集期間および活動開始
令和6年5月24日(金)から令和6年6月21日(金)まで
開始予定日 令和6年10月1日以降、別途協議の上で決定します。
長野県上田市|ゼロカーボンシティの実現に向け、脱炭素推進を担う
長野県上田市は、2050年までに二酸化炭素排出量を実質ゼロとするゼロカーボンシティの実現を目指し、具体的な削減目標の設定、脱炭素の取り組みを推進しています。
上田市では、上田電鉄別所線沿線において太陽光発電・大型蓄電池を活用した効率的なエネルギーマネジメントを推進し、民生部門電力の脱炭素化を目指しています。また、鉄道用送電設備を活用した自営線マイクログリッドを構築することで、上田電鉄のゼロカーボン運行を実現し、災害時のレジリエンス強化も図っていきます。これらの取り組みは、別所線利用促進策及び移動利便性向上策と並行して展開され、住民のマイカー依存度を低減し、将来的に環境に配慮した生活を実現沿線住民の暮らしの質の向上にもつなげていきたいと考えています。
そこで今回、ゼロカーボンシティの実現に向け、地域エネルギー会社の運営と上田電鉄別所線沿線エリアにおける脱炭素推進を担う地域おこし協力隊の募集を行います。
なお、今回募集を行う地域おこし協力隊員は「脱炭素推進コーディネーター」として活動します。
1.活動内容
地域エネルギー会社の運営に係る活動
- PPAモデル(太陽光発電の設置)の広報、営業
- 地域住民からの問合せ受付、対応
- 電力小売における需給調整 など
地域の脱炭素推進に係る活動
- 地域住民向けセミナー等の企画、運営サポート
- 上田電鉄 別所線の利用促進に向けた企画、運営サポート
- その他マイカー依存度の低減に向けた企画立案、実施 など
その他、目的達成に資する活動
- 月次報告書の提出、活動報告会への参加
- 地域行事やコミュニティ活動への参加 など
2.募集要件
- 三大都市圏(東京都,埼玉県,千葉県,神奈川県,愛知県,岐阜県,三重県,大阪府,京都府,奈良県及び兵庫県をいう)又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市に現に住所を有する方
- 採用後、生活の拠点を上田市に移すとともに上田市に住民票を異動することができる方
- 任期終了後も上田市に居住する意向のある方
- 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格事由に該当しない方
- 普通自動車運転免許を有している方、又は取得予定の方
- パソコンの一般的な操作及びSNSの活用ができる方
- 市の条例及び規則等を遵守し、職務命令等に従うこと。
- 令和6年10月1日に着任可能であること。
3.募集人数
1名
4.募集期間および活動開始
令和6年4月30日(火曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで
開始予定日 令和6年10月1日
他、全国の地域おこし協力隊の募集情報を探すなら
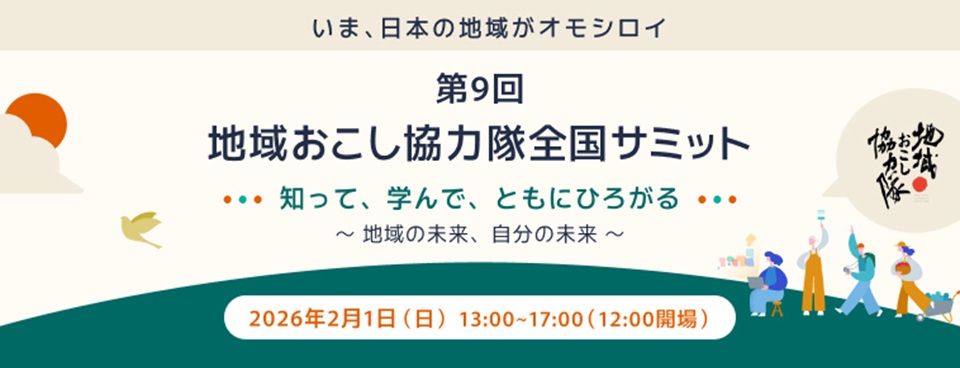
まとめ
今回は地域おこし協力隊とはどのようなものかと、地域おこし協力隊に興味ある方に向けて2024年5月末現在の募集情報をご紹介しました。
- 地域おこし協力隊とは、地方自治体の課題に取り組むために隊員となって活動する国の施策
- 募集は6~7月から開始される案件が多い
- 応募要件は各自治体が設けている地域おこし協力隊の窓口に必ず確認しよう