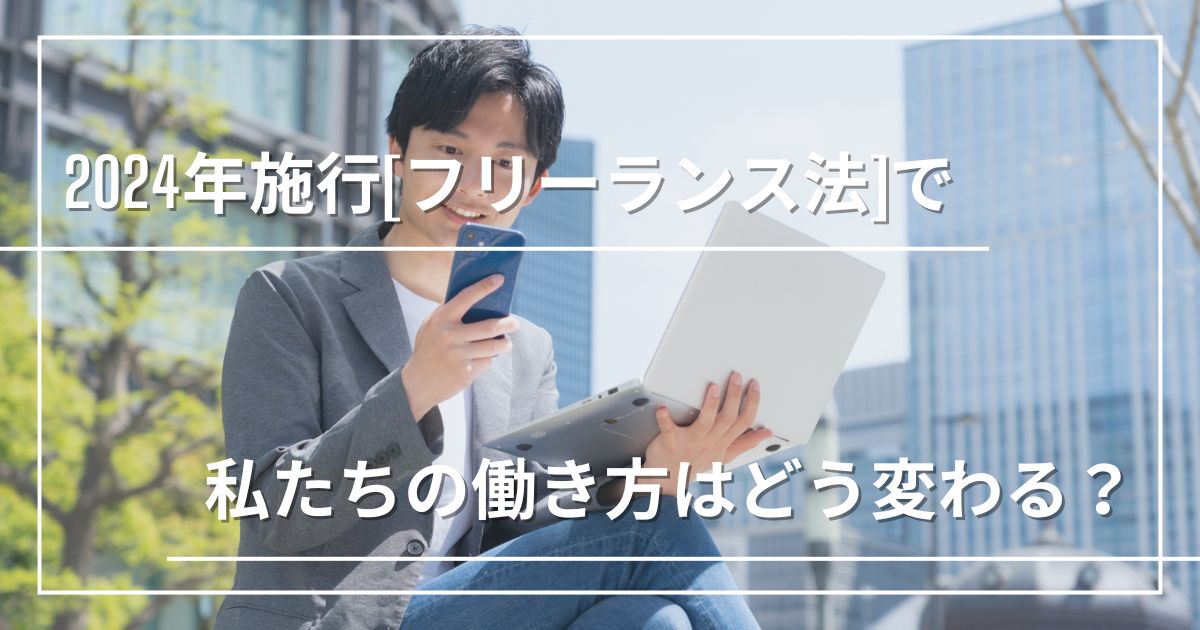働き方が多様化する現代において、2024年11月に「フリーランス・事業者間取引適正化等法(通称:フリーランス法)」が施行されます。
この法律は、フリーランスが安心して働き続けられる環境を整備するため、発注事業者(企業など)に様々な義務を課すものです。
これまで、フリーランスの仕事は、報酬の遅延や、契約内容が曖昧なまま仕事を進めるなど、不安定な側面がありました。
しかし、フリーランス法の施行によりこれらの問題が改善され、より安定した働き方が期待できるようになります。
今回は2024年11月に施行されるフリーランス法や、フリーランスが知っておくべきことを解説します。
今、フリーランスをしている人、これからフリーランスを始めたい人は必見です。
2024年11月試行のフリーランス法とは?

2024年11月に施行される「フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)」は、フリーランスの働き方をより安定させ、不当な取引慣行から保護することを目的とした法律です。
近年、働き方が多様化し、フリーランスとして働く人が増加しています。
しかし、フリーランスは、雇用契約とは異なり労働基準法の保護を受けることができません。
そのため、不当な取引慣行に遭いやすく、経済的な不安や精神的なストレスを抱える人が少なくありませんでした。
今回施工されるフリーランス法は、このような状況を改善し、フリーランスが安心して働くことができる社会を実現するためのものです。
フリーランス法は大きく2つの目的によって定められています。
- フリーランスと企業などの発注事業者の間の取引の適正化
- フリーランスの就業環境の整備を図ること
本記事で詳しく見ていきましょう。
フリーランス法の対象となる取引

フリーランス法が対象とする取引は、特定の条件を満たす「業務委託契約」です。
フリーランスが対象
この法律の対象となるのは、フリーランスとして従業員を使わず業務を行う人です。
また、消費者を相手に取引している場合はこの法律におけるフリーランスにはあたりません。
業務委託契約が対象
業務委託契約とは、ある事業者が他の事業者に特定の業務を委託し、その委託を受けた事業者がその業務を行う契約のことです。
一般的には、企業などの事業者が業務を委託し、フリーランス等が受託します。
また、フリーランス法には業種・業界の限定はなく、下請法で対象外となっている建設工事や役務提供委託も対象となります。
対象となる取引の例
- 家具メーカーが、フリーランスに家具部品の製造を依頼する(製造・加工委託)
- Webサイト制作会社が、フリーランスにWebサイトのデザインを依頼する(情報成果物の作成委託)
- イベント会社が、フリーランスに演奏会での楽器演奏を依頼する(役務提供委託)
対象とならない取引の例
一般消費者が、個人で利用するためにフリーランスに動画編集を依頼する(売買契約)
具体的にはどう変わる?

フリーランス法は、取引の適正化と就業環境の整備のために、主に発注事業者へ課される義務を定めた法律です。
フリーランスで働く人にとっても知っておくべき内容ですので、確認しておきましょう。
1.取引条件の明示が義務となる
発注事業者は、契約内容を具体的に記載した書面、または電磁的方法によりフリーランスに交付する必要があります。
電磁的方法には、電子メールの他、SNSのメッセージ、チャットツールも認められています。
ただし、メッセージを利用する場合は削除されたり閲覧できなくなる可能性もあるため、双方で事前対応を決めておくことやスクリーンショットで保存すると良いでしょう。
なお、この法律により電話など口頭で取引き条件を伝えることは認められません。
■明示すべき事項
- 発注事業者とフリーランス、それぞれの名称
- 業務を委託した日
- 業務内容
- 契約期間、納期
- 納品場所、作業場所
- 報酬額、支払期日(あれば検収日)
- 支払い方法
特に、業務の内容や範囲を具体的に定める必要があります。
追加業務が発生する可能性がある場合には、事前にその旨や報酬について協議することも盛り込むと良いでしょう。
他、解約に関する事項など、契約の重要な事項を網羅的に記載する必要があります。
②報酬の支払いに関する義務
発注事業者は、原則として業務完了後60日以内のできるだけ短い期間内に、報酬を支払う必要があります。
支払期日を定める場合は、「○月○日まで」、「○月○日以内」といった記載ではなく、「○月○日支払」と日付を特定できるよう定める必要があります。
③7つの禁止行為
フリーランスに1カ月以上の業務委託をしている発注事業者は、フリーランスに対し、以下の行為を行うことは禁止とされています。
- 受領拒否の禁止
発注事業者の都合による一方的なキャンセルや納期延期などで、物品や成果物の受け取りを拒むこと。 - 報酬減額の禁止
発注時に定めた報酬額を発注後から減らして支払うこと。予め定めのない振込手数料の差引きも減額行為となる。 - 返品の禁止
フリーランスに責がないにもかかわらず、物品や成果物を受領後に引き取らせること。 - 買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬を定めること。報酬を決定する際はしっかりと協議することが重要。 - 購入・利用強制の禁止
正当な理由がないのに、発注事業者が指定する業務に関連のない物やサービスを強制して購入・利用させること。 - 不当な経済上の利益の提供要請の禁止
委託内容に含まれていない業務について無償で行わせたり、協賛金を提供させたりすること。 - 不当な給付内容の変更・やり直しの禁止
フリーランスに責がないにもかかわらず、費用の負担なく業務内容の変更や取り消しを行うこと。
発注事業者は発注取り消し、やり直しをさせる場合には作業に要した費用を負担する必要がある。
④中途解約の事前予告・理由開示
発注事業者は、6カ月以上の業務委託について、契約の解除または更新しない場合は、例外事由に該当する場合を除いて、解除日または契約満了日から30日前までにその旨を予告しなければなりません。
また、フリーランスから解約理由を請求した場合、発注事業者は例外事由に該当する場合を除いて、開示しなければならないと定められています。
⑤その他義務
・募集情報の的確表示
求人サイトやホームページ、SNSの広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならないとしています。
例えば、実際の報酬額よりも高額な報酬額を募集情報に表示したり、職種または業種について、実際の業務内容と著しく乖離する名称を使わない、などがあります。
・ハラスメント防止対策
発注事業者は、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントなど、あらゆる形態のハラスメント防止のための対策を講じなければなりません。
また、ハラスメントに関する相談窓口を設置し、フリーランスが安心して相談できる体制を整える必要があります。
フリーランスがハラスメントに関する相談を行ったことを理由に、不利益な扱いをすることは禁止されています。
・育児・介護への配慮
フリーランスが育児や介護を行っている場合には、可能な範囲で配慮する必要があります。
具体的には、①申し出の内容の把握、②希望する配慮や対応の検討、③配慮の実施・不実施の伝達を行うこととしています。
また、申し出により契約の解除や報酬の未払い・減額(業務量減少による報酬減額はこの限りではない)、申し出をためらわせるような阻害行動は禁止されています。

契約トラブルが発生したら

フリーランスを保護する新しい法律が出来たとはいえ、実際の契約には様々なトラブルが発生する可能性があります。
もし、トラブルが発生した場合、どのように対処すればよいでしょうか。
フリーランスは、発注事業者に本法違反と思われる行為があった場合には、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省に対して、その旨を申し出ることができます。
行政機関は、その申出の内容に応じて、報告徴収・立入検査といった調査を行い、発注事業者に対して指導・助言のほか、勧告を行い、勧告に従わない場合には命令・公表をすることができます。
命令違反には50万円以下の罰金があります。
また、フリーランスとして事前の回避策は、取引開始前に契約書の内容をしっかりと確認することが重要です。
契約書には、業務内容、報酬額、支払い方法、解約に関する事項など、契約の重要な内容が記載されています。
契約書の内容と実際の取引状況に食い違いがある場合は、契約書を根拠に交渉を進めることができるため、取り交し前にきちんと確認しましょう。
フリーランスが知っておくべきこと

これまで、フリーランス・事業者間取引適正化等法について、発注事業者の義務やトラブルの解決方法などを解説してきました。
ここではフリーランスとして働く上で知っておくべき基本的な知識として、労働契約との違い、社会保険、税金について解説します。
労働契約との違い
フリーランスと労働者は、契約形態や法律の適用範囲が大きく異なります。
| 項目 | フリーランス | 労働者 |
| 契約の種類 | 業務委託契約 | 雇用契約 |
| 従属性 | 独立した事業主体として働く | 使用者に従属して働く |
| 労働時間 | 自由に決定 | 労働基準法で定められた労働時間 |
| 報酬 | 成果物や業務に対して支払われる | 時間や役務に対して支払われる |
| 社会保険 | 自分で加入 | 会社が加入手続きを行う |
また、労働基準法は労働者に対して適用されますが、フリーランスには原則として適用されません。
社会保険・年金
フリーランスは、労働者と違い、原則として自分で社会保険(国民健康保険、国民年金)に加入する必要があります。
また、企業が加入する労災保険はないため、傷病などで収入が途絶えた場合などに備えておく必要があります。
税金
フリーランスは、事業所得として確定申告を行い、所得税を納める必要があります。
確定申告は毎年1月~3月までに、前年の所得について確定申告を行います。
会社員と違い、フリーランスは業務に必要な経費は、所得から控除することができます。
また、売上が一定額を超えると、消費税の納税義務が生じます。
フリーランス向けの保険
公的保険の他、フリーランスとして働く場合に備えておくと良い保険をご紹介します。
◎フリーランスの賠償責任保険
フリーランス特有のリスクに備える保険です。
特有のリスクには、情報漏洩や納期遅延による顧客への影響、著作権侵害などがあります。
フリーランスは、トラブルに遭遇するとその責任は個人で負わなければならず、ケースによっては損害賠償を請求されてしまうこともあります。
特に情報漏えいの場合、損害賠償請求が高額になることも多いため、保険等で備えておくと安心です。
フリーランスの賠償責任保険はさまざまありますが、フリーランス協会の一般会員(年会費1万円)になると、「賠償責任保険」が自動で付帯されます。

◎労災保険の特別加入
労災保険は一般的に企業に雇用される労働者を対象としていますが、特定の事業に従事し、労働者を使用しない自営業者の場合、労災保険に特別加入することが可能となっています。
個人タクシーや個人貨物運送業者、大工等の建築業、林業などが対象となります。
仕事上で心身に支障をきたしたとき、治療が自己負担なしで受けられます。
また、労働ができない場合の休業補償給付や、障害が残った場合の障害補償給付、万が一死亡した場合には、遺族に対して遺族補償給付などを受けることができます。
まとめ
今回はフリーランス法やフリーランスが知っておくべきことを解説しました。
- フリーランス法は取引の適正化と就業環境の整備を定めたもの
- 取引きでトラブルとなった場合は公的機関へ相談を
- フリーランス特有のリスク回避のための保険もある