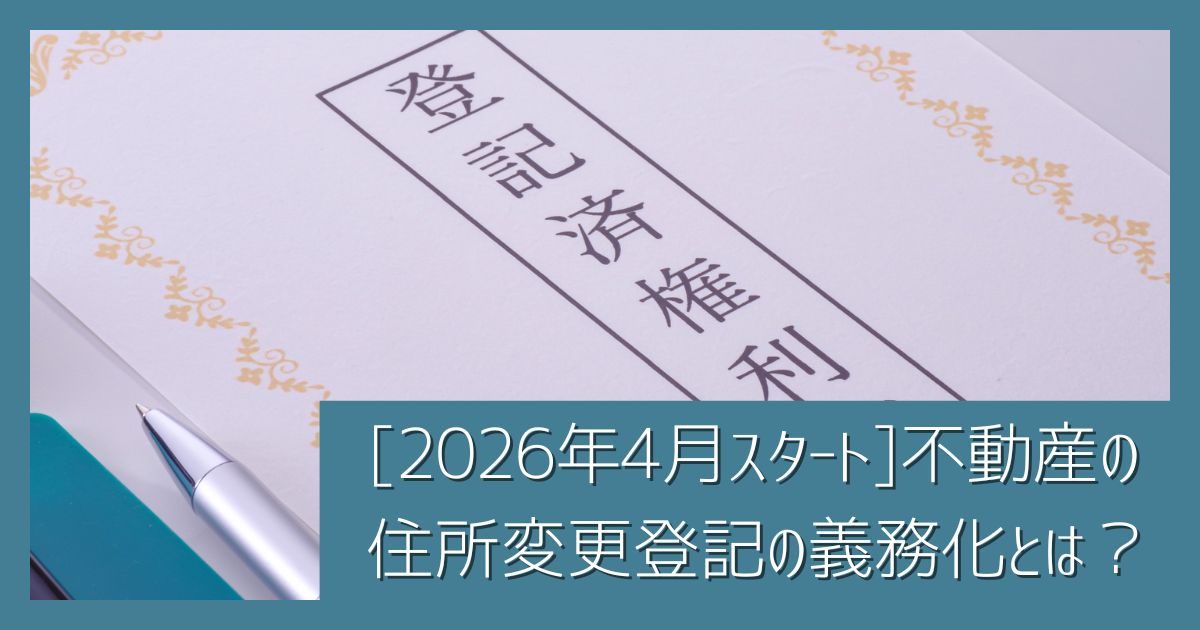2026年4月からスタートする不動産の住所変更登記の義務化。
この法改正は、都市部に住みながら地方に別荘やセカンドハウスを所有している方にとっても無関係ではありません。
特に、現代はライフスタイルの変化や転勤・転居が多く、登記の内容と実際の住所が一致していないケースも少なくないでしょう。
今回は住所変更登記義務化のポイントと別荘・セカンドハウスへの影響をわかりやすく解説します。
不動産の「住所変更登記義務化」とは?

2026年4月1日より、不動産の所有者が住所を変更した場合には、登記の変更を義務づける法律が施行されます。
これまでは任意だった住所変更の登記が、義務化される点が大きな変更です。
所有者不明土地問題への対応
この法改正の背景には、所有者の住所が分からず放置された「所有者不明土地」の増加があります。
所有者不明土地は全国で20%、約410万ヘクタールの面積を占めると推計されています。
これは367.5万ヘクタールの九州本土を大きく上回る面積で、公共事業や地域開発の妨げとなっていました。
これを解決するために、不動産の所有者情報を最新の状態に保つことが求められるようになったのです。
具体的な義務内容
改正不動産登記法の施行により、不動産の所有者が引っ越しなどで住所を変更した場合には、変更登記の申請が義務化されます。
これに違反した場合、罰則として過料(最大5万円)が科される可能性があります。
対象となる人
- 個人が住民票の住所を変更した場合(引っ越しなど)
- 法人が登記上の本店所在地を移転した場合
不動産の種類にかかわらず、自宅・別荘・セカンドハウス・投資用不動産など、所有しているすべての物件が対象となります。
義務の発生タイミング
住所変更があった日から2年以内に登記の変更申請をしなければなりません。
たとえば、2026年5月1日に引っ越しをして住所変更をした場合、2028年4月30日までに登記変更を申請する必要があります。
また、義務化される2026年4月1日以前に住所が変わっているが登記変更を行っていなかった場合も、義務の対象となります。
その場合は、猶予期間として義務化スタートから2年の間(2028年3月31日まで)に登記変更を行えば罰則の対象外となります。
別荘・セカンドハウス所有者は要注意

住所変更登記の義務化は、自宅や事業用物件に限らず、所有するすべての不動産が対象となります。
つまり、別荘やセカンドハウスを持っている方も、その物件の登記情報が最新の住所と一致しているかを確認しなければなりません。
「別荘だから関係ない」は通用しない
別荘やセカンドハウスは「たまにしか使わない」「実質的に空き家になっている」といったケースも多く、つい登記の見直しがおろそかになりがちです。
しかし、法律上は「使用の頻度」に関係なく、不動産を登記上で所有している以上、義務は発生します。
たとえば、東京都に住むAさんが、10年前に軽井沢に別荘を購入し、昨年東京都内で引っ越したとします。
この場合、軽井沢の別荘も「所有者の住所が変わった」ことになるため、登記簿上の住所も新住所に変更する必要があります。
これを怠ると、2026年4月1日以降は過料のリスクが生じます。
利用していなくても対象になる
「最近は別荘に全く行っていない」「数年放置している」といった事情があっても、登記義務の対象外になることはありません。
所有している限り、法律上の義務は継続しているという点に注意が必要です。
また、別荘は将来的に相続対象となることも多く、登記が正確でないと、相続手続きが煩雑になったり、トラブルの原因になったりする可能性もあります。
今のうちに適切に登記を整備しておくことは、自分だけでなく家族にとっても大きな安心につながります。
住所等変更登記の手続き方法
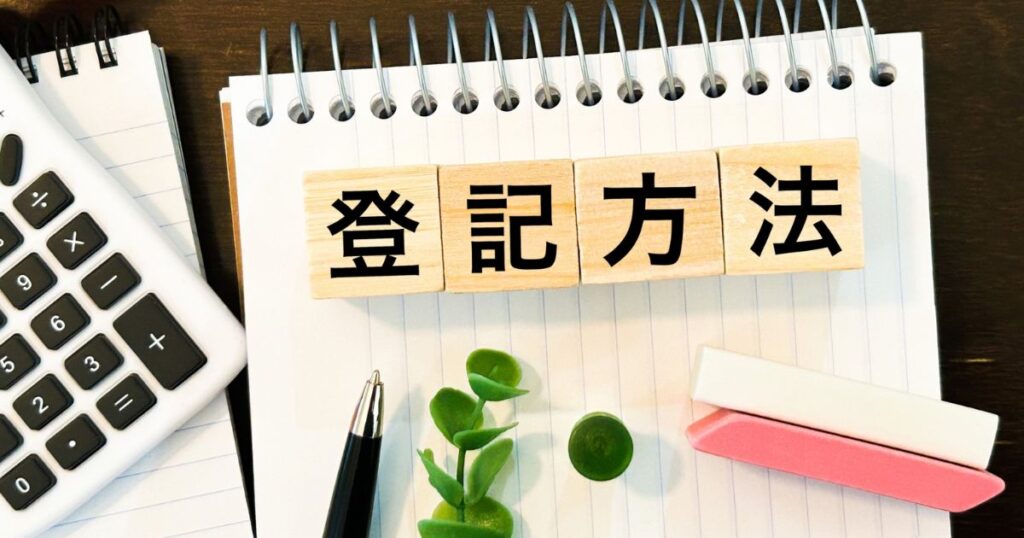
住所等変更登記は、不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)に申請します。
基本的な流れは次のとおりです。
STEP1 必要書類の準備
まずは必要書類を準備します。
①住民票など、住所変更を証明する書面
現在の住所が記載された住民票の写しを用意します。
住民票には前住所が記載されるため、登記簿上の旧住所とのつながりを証明できます。
※過去に複数回転居して登記簿上の住所と現住所が直接つながらない場合は、「戸籍の附票(現在および旧住所の履歴が記載されたもの)」や「住民票除票」などを追加で用意し、住所の変遷を証明する必要があります。
②登記申請書(住所変更登記用)の用紙
住所等変更登記用の申請書を用意します。
申請書は管轄の法務局窓口で入手または法務局ウェブサイトからダウンロードが可能です。
③委任状(必要に応じて)
司法書士など代理人に依頼する場合は委任状も必要となります。
STEP2 登記申請書の作成
申請書に物件の登記情報(登記簿の所在地番など)や旧住所・新住所、変更日など必要事項を記入します。
本人申請の場合、収入印紙で登録免許税を納付する場合は申請書に貼付します。
手続きする時間がない方や書類作成に不安がある方は、司法書士など専門家に依頼することも検討しましょう。
専門家に依頼した場合は報酬(サービス料金)が発生します。
報酬額は依頼する事務所や物件数によって様々ですが、住所変更登記1件あたり数万円前後が目安です。
費用はかかりますが、書類の不備なく確実に登記を完了できるメリットがあります。
STEP3 法務局へ提出(持参または郵送)
書類を揃えたら、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請し、登録免許税を納付します。
提出方法は、法務局窓口への持参または郵送で可能です(電子申請も可)。
STEP4 登録完了
法務局に申請書を提出すると、受付がなされ審査が行われます。
登記の処理には通常1~2週間ほどかかります。
完了すると、登記識別情報が発行され、変更が反映された後日「登記完了証」が交付されます。
※不動産を複数所有しており所在地の管轄法務局が異なる場合、それぞれの法務局に申請が必要になる点にも注意しましょう。
手続きを簡素化「スマート変更登記」

2026年4月に住所変更登記が義務化される一方で、登記手続きを簡素化し、所有者の負担を軽減することを目的とした、「スマート変更登記」も導入されます。
このサービスは簡単な申出を1回しておけば、法務局で住所等の変更を確認して登記をしてくれるというもので、個人向けには2025年4月21日から始まっています。
「検索用情報の申出」で利用可能
個人の不動産所有者を対象とする「検索用情報による申出」は、住民票の情報と登記簿の情報を連携させることで、法務局が職権で住所変更登記を行う制度です。
所有者本人が法務局に対し、検索用情報(個人を特定できる情報、マイナンバーとは別)を提供することで、市区町村が保有する住民基本台帳の内容をもとに、登記官が自動的に住所変更を行います。
登記申請をしなくても変更できる
この申出を行うことで、住所変更の度に登記申請書や住民票を準備する必要がなくなり、手続きを簡略化できるのが最大のメリットです。
たとえば、「登記のやり方がよくわからない」、「忘れてしまいそう」といった方でも、申出をしておけば自動的に登記が更新されるため、過料リスクを避けることができます。
申出の方法
法務局のスマート変更登記ページにある「かんたん登記申請」ページから、「検索用情報の申出」の手続を選択し、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力することで、WEB申出ができます。
なお、電子証明書は不要です。
書面で申出をする場合には、次の記載例・様式を参考にして申出書を作成し、不動産を管轄する法務局に提出となります。
管轄の異なる複数の不動産を所有している場合、その不動産のうちいずれかの不動産を管轄する法務局にまとめて申し出ることもできます。
放置しているとどうなる?

住所変更登記を怠った場合、2026年4月以降は過料が科される可能性があります。
これは一度限りの注意喚起ではなく、法的な「義務違反」として扱われるため、軽視できない問題です。
過料のリスク
具体的には、正当な理由なく登記を変更しなかった場合、5万円以下の過料が科されることになります。
行政から通知が来て初めて気づいたとしても、「知らなかった」ことは免責理由にはなりません。
特に複数の不動産を所有している方は、そのすべての物件が対象となるため、リスクも増大します。
また、過料が科されるか否かに関係なく、「住所が古いままの登記」は将来的に不利益を生む可能性があります。
相続・売却の際に不利益を被ることも
登記情報が最新でない状態のまま放置していると、相続や売却といった重要な局面で思わぬトラブルに直面することがあります。
- 不動産を売却しようとしたが、登記上の所有者住所が旧住所のままで契約がスムーズに進まない
- 相続発生時、住所が変わっているために「本人確認」に時間がかかり、手続きが遅延
- 金融機関の担保審査で、登記内容に整合性がなく信用性が下がる
このように、登記情報の整備は日常では気づきにくいが、重要な場面で影響するとも言えます。
登記内容を最新に保っておくことは、不動産を管理・活用するうえで欠かせない備えです。
まとめ
今回は住所変更登記義務化のポイントと別荘・セカンドハウスへの影響を解説しました。
- 住所変更登記は義務化され、変更から2年以内の変更登記が必要
- 別荘やセカンドハウスも対象になるため、住所が変わったら登記変更が必要
- 「スマート変更登記」を活用すれば、1度申出をするだけで住所変更登記を自動化