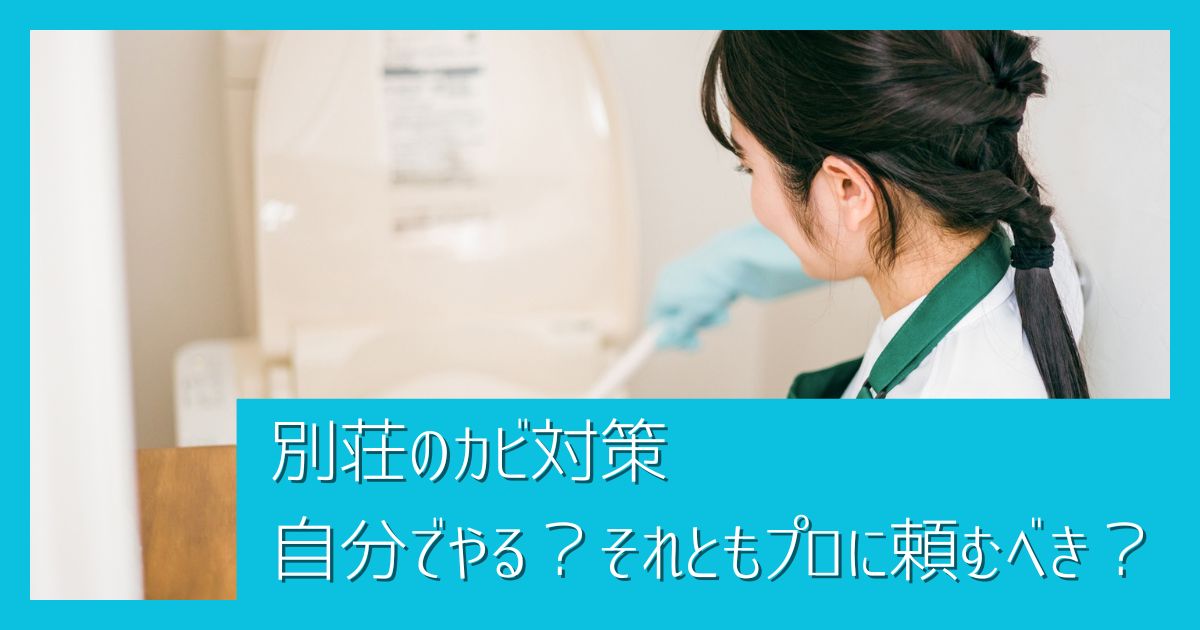梅雨から夏にかけて、別荘やセカンドハウスにとって最大の悩みのひとつが「カビの発生」です。
月に1回程度しか使わない別荘では、湿気がこもりやすく、気づかないうちにカビが広がってしまうことも少なくありません。
また、見た目だけでなく健康や建物の劣化にも影響を与えるカビは、放置すると深刻な問題につながります。
では、こうしたカビ対策は自分でできるのでしょうか? それとも管理会社や清掃業者など、プロに頼んだ方がよいのでしょうか?
今回は、別荘がカビやすい理由、自分でできる対策とプロに依頼する場合のメリット・デメリットを比較しながら、最適なカビ対策をご紹介します。
なぜ別荘はカビが発生しやすいのか

一般的に「室温が20~30度」、「湿度75%以上」の状態が続くと、カビが繁殖しやすくなります。
その中でも別荘やセカンドハウスは特にカビのお悩みを聞くことが多いです。
理由としては下記のようなことが挙げられます。
換気不足による湿気の滞留
別荘は一般住宅と違い、使用頻度が低いため、日常的な換気が行われにくい環境にあります。
とくに梅雨時期や夏場は湿度が高く、窓を閉め切ったままでは室内の湿気がこもり、カビの温床になってしまいます。
立地条件による影響
多くの別荘は山間部や森林の近く、または海辺など自然豊かな場所にあります。
これらの地域は空気中の湿度が高く、土壌や周囲の植物からの水分が建物に影響しやすいため、湿気を含みやすくなります。
使用頻度が低く変化に気づきにくい
月に1回程度の利用では、建物の異変に気づくのが遅れがちです。
カビは目立たないうちに発生し、1ヶ月もあれば広範囲に広がることもあります。
気づいたときには、壁紙や床、家具に深刻なダメージが及んでいることも少なくありません。
また、虫の死骸やホコリ、落ち葉などが溜まりやすく、これらも湿気を吸ってカビの原因になります。
屋内だけでなく屋外の清掃も怠ると、カビの温床となる可能性があります。
カビが発生しやすい場所とその理由

前述のとおり、室温・湿度の高いところはカビが発生しやすくなります。
特に発生しやすい場所は以下の通りです。
浴室・洗面所
水を頻繁に使用するため湿度が最も高くなります。
使用後の水滴や湿気が密閉された空間にとどまると、黒カビが発生しやすくなります。
特にシーリング部分や換気扇の内部など、目につきにくい箇所の確認も重要です。
押し入れ・クローゼット
閉め切った状態が続くと空気がこもり、湿気が溜まりやすくなります。
収納されている布団や衣類にもカビが移り、使えなくなるケースもあります。
スノコを敷いたり、定期的に中の入れ替えを行うことも効果的です。
窓枠・サッシ周辺
温度差による結露が発生しやすく、特にサッシ周辺は掃除が行き届きにくいため、湿ったまま放置されるとカビの温床になります。
防カビスプレーの活用や断熱フィルムの設置も予防策のひとつです。
畳・床下・壁紙の裏側
通気性の悪い床下や、湿気を吸いやすい畳、壁紙の裏側もカビが好む場所です。
見えない部分で進行しやすいため、発見が遅れやすく、リフォームが必要になるケースもあります。
特に畳の裏側は要注意ポイントで、定期的に上げてチェックするとよいでしょう。
また、家具や冷蔵庫の背面も見逃しがちなカビスポットです。
これらの場所も壁との間に隙間を空け、年に数回は動かして状態を確認することをおすすめします。
【事例】いつもの掃除だけでは防げなかった!夏の別荘での失敗談

東京都在住の40代男性・Sさんは、家族4人(妻・小学生の子ども2人)で群馬県の山間部にある別荘を月1回のペースで利用していました。
都心から2時間ほどの立地で、週末のリフレッシュに最適な静かな環境が気に入っているそうです。
6月、久々に別荘を訪れると、室内に「少しカビ臭い」空気を感じたものの、目に見えるカビはなく、簡単な掃除だけで済ませて帰宅しました。
しかし次の月、再び訪れた際には浴室の壁一面に黒カビが広がり、押し入れにしまっていた布団もカビ臭くなって使えない状態に。
清掃業者に相談したところ、壁紙の一部張り替えと徹底洗浄が必要で、予想以上の費用と時間がかかってしまいました。
鈴木さんは「軽く掃除すれば大丈夫」と思い込んでいたことが失敗の要因だったと振り返ります。
その後、インターネットで清掃業者を探したところ、別荘管理の会社で不在時の換気や清掃もしてくれるところを見つけ、月1回の定期換気と、清掃を行ってもらうようにしたそうです。
「信頼できる業者を見つけてからは安心感が全然違う」と満足そうに語ってくれました。
自分でできる?プロに頼む? カビ対策の選択肢

カビ対策は「自分でやる」か「業者に頼む」かで大きく対応が異なります。
ここではそれぞれの選択肢のメリット・デメリットを比較してみましょう。
自分で対応する場合
メリット
- 費用が抑えられる
- 自分のペースで作業できる
- 建物の状態を自分で把握できる
デメリット
- 定期的な訪問や労力が必要
- カビの根本原因まで対処しきれないことがある
- 滞在中、掃除に時間をとられる
プロ(管理会社・清掃業者)に依頼する場合
メリット
- 専門知識と経験に基づいた対策ができる
- 長期的な維持管理が期待できる
- 離れた場所に住んでいても定期的に管理してもらえる
デメリット
- ランニングコストがかかる
- 業者選定に時間がかかることがある
- 作業の質にばらつきがある可能性も
利用頻度やライフスタイルに応じて、どちらが自分に合っているか検討することが大切です。
管理会社や清掃業者を選ぶときのポイント
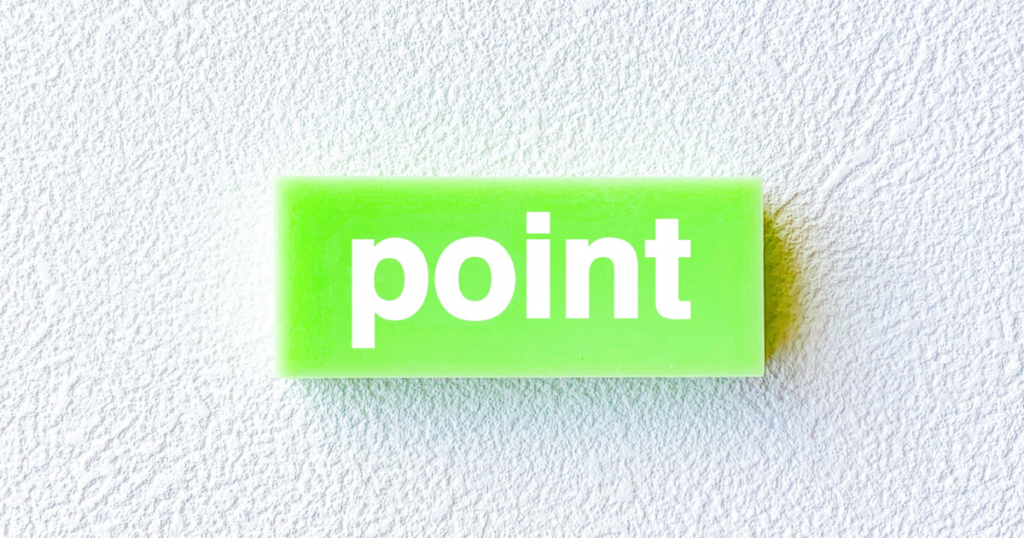
業者に依頼する場合は、以下のポイントを参考に選びましょう。
湿気・カビ対策の知見があるか
単なる掃除だけでなく、建物やカビの原因となる「湿気管理」に関する幅広い知識や経験を持つ業者を選ぶことが大切です。
除湿器の設置や効果的な換気方法までアドバイスできる業者は信頼性が高いといえます。
料金体系が明確か
定期管理やスポット清掃、オプションメニューの料金が明示されているかを確認しましょう。料金が不明瞭な業者では、後に追加費用が発生する可能性があります。
見積りが無料の場合は、一度問い合わせてみると良いでしょう。
作業報告の有無
定期管理を依頼する場合は、作業報告書や写真付きのレポートで内容を共有してくれる業者を選ぶと安心です。
遠隔地に住んでいる場合は特に重要なポイントとなるでしょう。
実績と評判
同じエリアの別荘オーナーからの紹介や、インターネット上のレビューも参考になります。
地域の気候に詳しい地元業者は、効果的な対策ノウハウを持っていることが多いです。
また、見積もり時に実際に現地を見てくれる業者かどうかもチェックしましょう。
現場を確認せずに概算だけで進める業者は、対応の丁寧さに欠ける可能性があります。
自分でできるカビ対策

業者に依頼した場合も、しない場合でも、自分でできるカビ対策はやっておくとよいでしょう。
除湿剤や除湿機の活用
押し入れや収納には除湿剤を設置することで、こもった湿気を吸収できます。
また、長期間不在になる場合は、電源を確保できる環境であれば除湿機のタイマー運転も効果的です。
最近ではWi-Fi対応で遠隔操作が可能なエアコンも登場しており、利便性が高まっています。
換気の工夫
滞在中はできるだけ窓や扉を開けて空気を循環させましょう。
家具の背面を壁から少し離すだけでも通気性が高まり、カビの発生を抑えることができます。
定期的に扇風機やサーキュレーターを使って空気を動かすのも有効です。
自然素材・カビ予防剤の使用
アルコールスプレーなど、自然由来のカビ予防剤を活用するのも一つの方法です。
定期的な拭き取り掃除によって、カビの発生を防ぎやすくなります。
市販の防カビ剤や、防カビスプレーも併用することで効果を高めることができます。
夏前・梅雨前の事前準備
春の終わりから初夏にかけて、梅雨入り前に一度別荘を訪れ、換気や掃除、除湿剤の設置などを行うのがおすすめです。
特に屋根裏や床下の点検もこの時期に済ませておくと安心です。
まとめ
今回は、別荘がカビやすい理由、自分でできる対策とプロに依頼する場合のメリット・デメリット、カビ対策をご紹介しました。
- カビ対策の基本は「湿気管理」と「定期的なチェック」
- 重点エリア(浴室・収納・窓周辺など)を中心に対策を講じることが重要
- 信頼できる管理会社と連携すれば、安心して別荘を維持できる

別荘・セカンドハウスの滞在中
掃除ばかりしていませんか?
建物のプロが掃除から点検・管理まで
トータルサポートします!