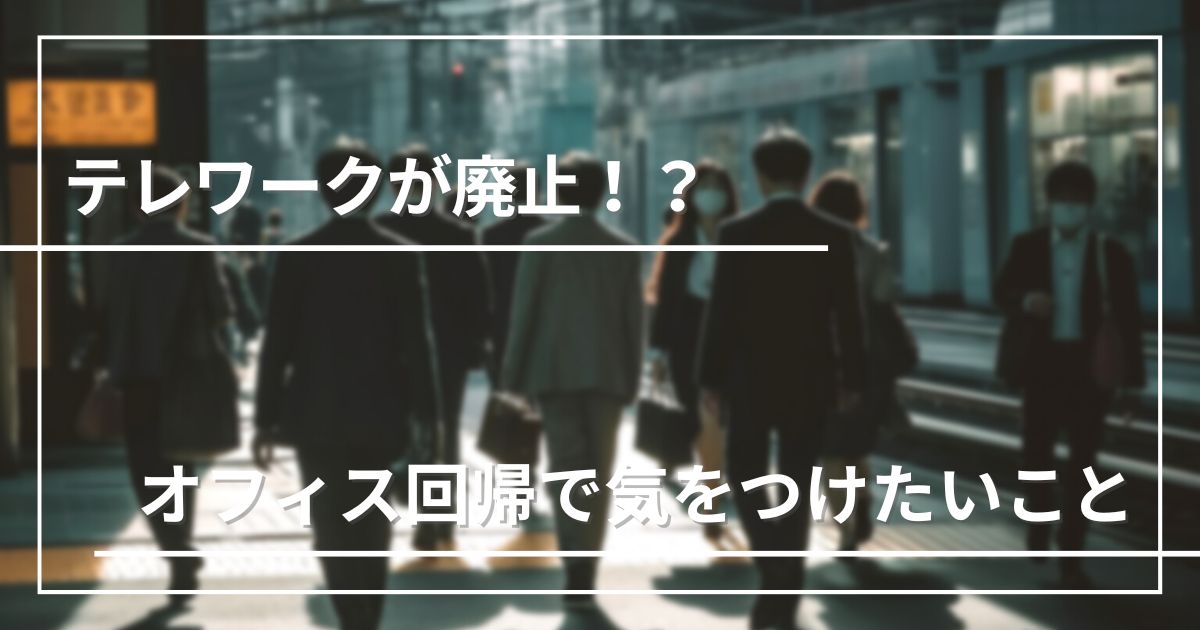新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと移行し、「オフィス回帰」という言葉を耳にする機会が増えました。
対して、オフィス出社への切り替えをきっかけに転職活動をしている人たちも出てきています。
働き方に関する価値観が大きく変わった現在で、企業や私たちにも転換期が訪れようとしています。
そんな中、会社がテレワークを廃止した場合、従業員への影響を考え、企業はどのようにしたら良いのでしょう。
そして、働く人たちはどのようなことに気をつければいいのでしょうか。
今回は、テレワークが廃止になった時にどういった影響があるのか、私たちが気をつけたいことは何かをご紹介します。
「とにかく転職!」と考える前に読んでみていただければと思います。
テレワークとは

テレワーク(Telework)とは、通信技術を活用して場所や時間に制約されずに仕事を行う働き方のことを指します。
具体的には、従業員が自宅やコワーキングスペースなどの場所で、インターネットや電話、ビデオ会議などのツールを使用して業務を遂行する形態です。
テレワークには以下のような特徴があります。
①場所にとらわれない
テレワークはオフィスから離れた場所で仕事を行います。
そのため自宅や地方の拠点、移動中の場所など、場所に制約されずに業務を遂行できます。
従来の外回り営業マンが出先のカフェで、電話やメール等の業務を行うこともテレワークの1つだったということになります。
②コミュニケーション技術の活用
テレワークでは、電子メール、ビデオ会議、チャットツール、プロジェクト管理ツールなどのテクノロジーを活用してチームや上司とコミュニケーションを行います。
以前からメールやチャットツールは普及していましたが、ビデオ会議やプロジェクト管理ツール等はコロナ禍以降に爆発的に普及しました。
③柔軟な働き方
テレワークによって、従業員の日常に柔軟性を与え、個々の生産性やワークライフバランスを向上させる特徴があります。
例えば、通勤時間の削減によって家事や家族とのコミュニケーション時間が確保できることにより、心身のバランスが保たれ、生産性のアップにも繋がります。
テレワークの現状

国土交通省の2022年度調査によると、テレワークを実施している割合は全国で26.1%となっています(前年度0.9ポイント減)
勤務地域別の実施率は
首都圏40・0%
近畿圏26・2%
中京圏21・9%
上記以外の地方都市圏17・5%
首都圏は2.3ポイント減少していますが、依然4割の水準を維持しています。
一方で、地方都市圏は0.3ポイント増加したものの首都圏との差は大きいのが現状です。
またテレワーク実施者への調査で、テレワークの継続意向があるという割合は約87%となっており、今後もテレワークを続けたいと考えている人が多いことがわかります。
継続意向の理由としては、「時間の有効活用」が約40%と最も多く、次いで「通勤の負担軽減」が約33%となっています。
国交省は「新型コロナウイルス禍でテレワークは広がったが、一部で出社への揺り戻しがみられる」と分析。
しかし経験者の約87%は継続したいと答えており、担当者は「働き方の一つとして定着しつつある」と話しています。
参照:国土交通省「テレワーク人口実態調査」(報道発表資料)
どちらが効率的?テレワーク vs オフィス勤務

新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことにより、「オフィス回帰」という言葉が頻繁に聞かれるようになってきました。
そこで、テレワークとオフィス勤務の効率はどちらが良いのでしょうか。
それぞれの働き方による効率性を挙げてみました。
テレワークの効率性
①時間の有効活用
テレワークでは出社するための通勤時間が不要となり、自宅での作業が中心となります。
そのため、通勤時間を有効活用できることや、自身の作業ペースに合わせて作業を進められることが挙げられます。
②集中力の確保
オフィスでは騒々しかったり、他の人とのコミュニケーションによる作業中断がしばしば起こりますが、自宅や外部の静かな場所で作業できるため、集中力を維持しやすい場合があります。
(家庭環境によってはこの限りではありませんが)
③ワークライフバランス
テレワークでは働く場所や時間が柔軟に調整できるため、ワークライフバランスを向上させることができます。
自分の生活スケジュールや個人のニーズに合わせた働き方が可能です。
オフィス勤務の効率性
①コミュニケーションとチームワーク
オフィスでは直接的な対面コミュニケーションが容易であり、同僚や上司とのコミュニケーションが活発に行えます。
情報共有や意思決定のプロセスが迅速に進めることができます。
②共同作業や相互サポート
オフィスでは他の従業員とリアルタイムで共同作業や相互サポートが行いやすい環境です。
そのため意見交換や問題解決がスムーズに行えます。
③効果的な会議やミーティングの実施
オフィスでは会議室や共有スペースが備わっており、効果的な会議やミーティングが実施しやすい環境であると言えます。
特にクリエイティブな意見交換やプロジェクトベースの作業では、オフィスでの直接的なコミュニケーションやアイデアの共有が重要となる場合があります。
上記のことから、テレワークとオフィス勤務にはそれぞれのメリットがあり、どちらか一方が効率的と言えないのが現状です。
オフィス回帰で気をつけたいこと【企業編】
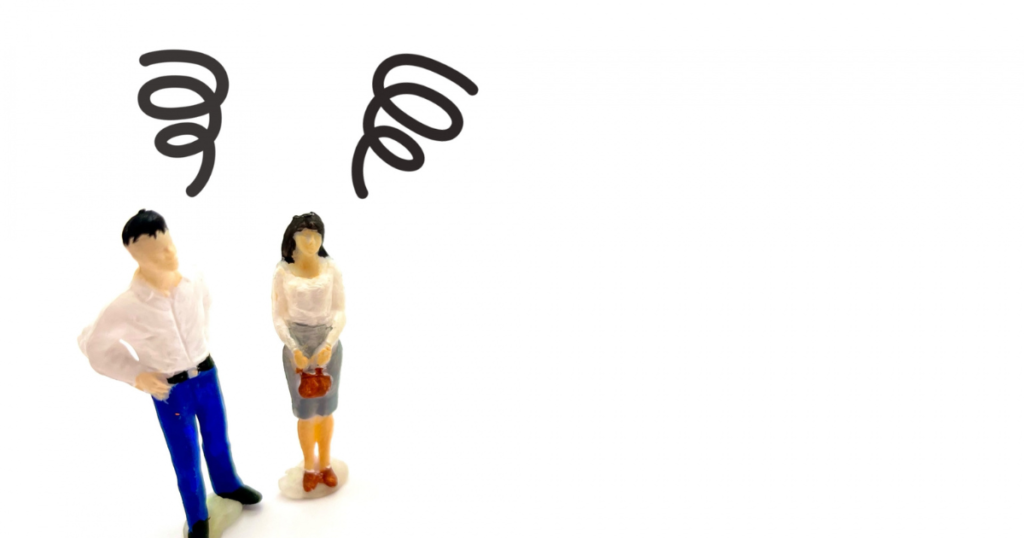
前項ではテレワーク・オフィス勤務のどちらにも効率的に良い面があるとお伝えしました。
しかし、中にはテレワークを廃止しオフィス出社を義務付ける会社も出てきています。
ここでは、テレワーク廃止を考えている会社経営者が、オフィス出社に向けて気をつけたいポイントをご紹介します。
①従業員のケア
まずは従業員の健康を最優先に考える必要があります。
感染症が落ち着いたとはいえ、対策として定期的な消毒や換気、ソーシャルディスタンスの確保などの対策を行い、従業員が安心して出社できる環境を整える必要があるでしょう。
また、テレワークを実施していた期間は、これまで通勤時間に充てていた時間を家事や育児、趣味に充てることもでき、プライベートの時間が確保しやすく、ワークライフバランスを実現しやすい環境でした。
そのため、テレワークが廃止されると通勤時間が発生し、その結果、従業員のワークライフバランスを崩してしまう可能性があります。
「コロナ禍以前は出社できていたのだから大丈夫」と考えず、このような変化を従業員がどう感じているか耳を傾ける必要があるでしょう。
②オフィス環境の整備
テレワークを機に従業員同士のミーティングや取引先との商談などをオンラインで行うようになった企業も多いでしょう。
出社を前提の働き方に変更したとしても、Web会議やオンライン商談は変わらず行っていくということであれば、オフィスにオンラインワークに適した環境を整備する必要があります。
Web会議などのオンラインワークをおこなうには、集中できるブースの設置やパーテーションを使ったワークスペースなど、周囲の視線や音を気にせず業務できる環境が大切です。
オフィスによっては新たに業務環境の整備が必要となり、その分の費用が上乗せされる可能性があります。
③柔軟な働き方の導入
テレワークの経験から得られた柔軟な働き方のメリットを活かし、出社とテレワークの組み合わせを検討することも重要です。
テレワークに働きやすさを感じていた従業員は、廃止によって離職を選択する可能性もあります。
多くの企業が労働者不足に課題を抱える現在、優秀な人材を手放すリスクに繋がりかねません。
そのため、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークの導入やフレックスタイム制度の見直しを通じて、従業員のワークライフバランスを支援し、生産性や働きやすさの向上に取り組みましょう。
経営者としては、従業員のニーズと事業の要件をバランス良く考慮し、出社に切り替わる過程をスムーズに進めることが重要です。
④テレワーク前の慣習(会議・社内イベント)
コロナ禍によって、私生活を重視する人が増え、仕事に対する価値観に大きな変化が起きました。
その中で、以前の慣習である定期的な会議や社内イベントに対し「必要性をきちんと説明してほしい」というような声が従業員から挙がっていると聞きます。
企業や管理者は「前からやっているから」や「必要だと思うから」といった、何となくやったほうがいいという観点で行ってきた会議や社内イベントはそのまま継続するのではなく、エンゲージメント向上のためにやり方を変えましょう。
エンゲージメントとは企業と従業員とが相互に影響し合い、共に必要な存在として絆を深めながら成長できるような関係を築いていくことを言います。
また、「従業員エンゲージメントが高くなると企業経営にプラスの影響をもたらす」とも言われています。
そのため、まずは従業員の価値観を把握し、本当に必要である会議やイベントなのかを再考する必要があります。
オフィス回帰で気をつけたいこと【従業員編】

続いて、勤め先がテレワークからオフィス出社へ切り替わった時、働く側はどういったことに気をつければよいでしょう。
従業員側が気をつけたいポイントをご紹介します。
①スムーズな復帰のための準備
テレワーク期間中に実施した業務やファイルを整理し、必要な書類やデータを持参するなど、出社に伴う業務のスムーズな再開に向けて準備をしましょう。
また、社内ルールの変更点を確認し、必要な情報を把握しておくことも重要です。
②コミュニケーションの再構築
テレワークでは主にオンラインでのコミュニケーションが中心でしたが、出社に切り替わることで直接的な対面コミュニケーションが再び重要となります。
チームメンバーや上司とのコミュニケーションを活発に行い、業務の連携や情報共有を円滑に行えるようにしましょう。
労働環境の変化に伴うストレスや不安を、適切にコミュニケーションで解消することも大切です。
③ワークライフバランスの維持
テレワークでは自宅や外出先で仕事をすることが多かったため、出社により通勤時間やオフィスでの業務に時間を割くことになります。
この変化によって、ワークライフバランスが崩れないように注意しましょう。
効果的な時間管理や適度な休息の取り方を心掛け、プライベートな時間や趣味、家族との時間を大切にすることで、心身の健康を維持しましょう。
④慣習見直しの提案
企業編でもテレワーク前の慣習について再考すべきことを挙げましたが、従業員にとってもテレワークによって得られた働き方について、会社に伝え、見直すべきことはしっかりと提言することが大事でしょう。
テレワークになり、ストレスが解消されたことの上位として「人間関係」がランクインしている調査もあります。
会議や社内イベントは人間関係でストレスを感じる可能性の高い機会です。
ストレスを感じる人も多いかと思いますので、自身や周囲のためにも、見直しを提案していくことは有意義となるでしょう。
今後はハイブリットワークが浸透

ハイブリッドワークとは、従来の出社型「オフィスワーク」と、自宅やシェアオフィスなどオフィスと離れた場所で働く「テレワーク」を組み合わせた働き方です。
テレワークには多くのメリットがある反面、実際に取り組んでみると課題を感じる企業や従業員も多くいます。
そこで、従業員一人ひとりの状況に応じた最適な働き方を実現するための方法として、ハイブリッドワークが必要とされるようになりました。
メリットとしては、テレワーク・オフィスワークどちらかに限定するのではなく、本当の意味で社員の自主性に任せた働き方が可能となることです。
その結果、会社側からの押し付けや決まりごとではなく、本人の意思による多様な働き方が実現します。
厚生労働省は3歳までの子どもがいる社員がオンラインで在宅勤務できる仕組みの導入を、省令で企業の努力義務とすると発表しています。
また、いまは3歳までとする残業の免除権も法改正で就学前までに延ばすとしています。
そういったことから、企業も働く側もテレワークとオフィス出社のハイブリットワークといった多様な働き方を、コロナ禍以降も取り入れていく必要があると考えられます。
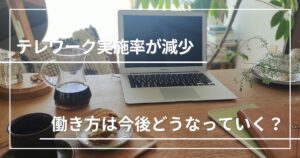
まとめ
今回は、テレワークが廃止になった時に私たちが気をつけたいことは何かをご紹介しまました
- テレワークは減少傾向にあるが、従業員の継続意向は87%と高い
- オフィス回帰では、以前の慣習にとらわれず見直しが必要
- 今後はテレワークとオフィスワークの両立がスタンダードになる