こんにちは、二拠点生活研究所のソトボンヌです。
いすみ市が毎年行っている『いすみ米オーナー制度』に、初参加。
約1年かけて、水稲体験から柿狩り、菜の花詰め放題など様々な体験イベントに参加できる制度です。
前回8月に稲刈りをして、
 ソトボンヌ
ソトボンヌ今回は収穫したお米の試食会です
▼いすみ米オーナー制度とは
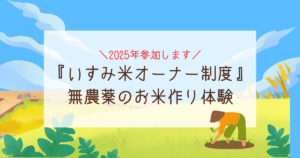
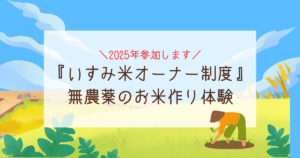
あっという間に秋の気候
9月前半はまだまだ真夏日も多かったですが、後半になり涼しい日もちらほらと。
新米試食会のこの日も天気は良かったですが、気温は30℃に届かないくらい。
風も涼しくて、外で過ごすにはちょうどいい気候でした。
主催である『みねやの里』代表の方からご挨拶と本日の流れを説明。


みんなで植えて収穫した新米を、ぬか釜で炊いて試食をします。
ぬか釜炊飯体験
ぬか釜炊飯とは、下にある専用の窯でもみ殻を使って炊く方法です。


いすみ市では、小学校の体験授業でも田植え体験と、ぬか釜炊飯体験を行っているとのこと。
さて、二重の円柱になっている窯の外側の円に、燃料となるもみ殻を入れていきます。




内側の円柱に出っ張りがあるのですが、もみ殻を入れる目安位置となっているんだそう。
そこまで入れると、ちょうど2升のお米を炊く分の燃料になるのだというからよく出来てますね。
続いて、内側の円柱には着火剤の役割となる『乾燥させた杉の葉』と、火の付きがよい『竹』を入れます。




杉の葉は油分が多いので、着火剤となるそうです。
原始的な炊飯ですが、着火は文明の利器ガスバーナーで。


火がついたら炊飯釜を置いて、約40分間放置です。




柿狩り体験へ
ご飯が炊けるまでは『柿狩り体験』です。


近くにある柿の木畑へみんなで移動。
収穫の説明を受けたら、収穫用ハサミと収穫用の袋を持って、さっそく柿狩りです。


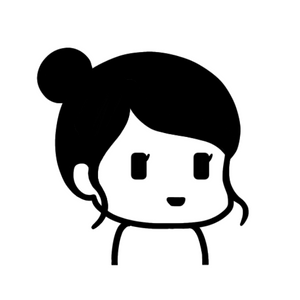
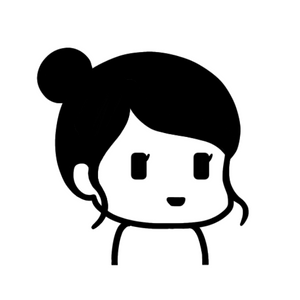
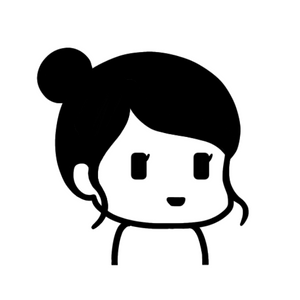
いっぱい実ってる!
ちなみに、この柿は『西村早生』という柿だそうです。
柿の特性上、一つの木に渋柿と甘い柿が混在するため、渋柿の見分け方も教えてもらいます。
柿の形に注目。お尻部分が丸いと甘い柿、くぼんでいると渋柿だそうです。


説明を聞いた時は「なるほどー」と分かった気でいたのですが、いざ柿を見比べると
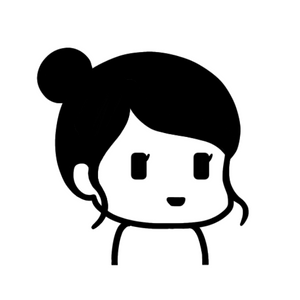
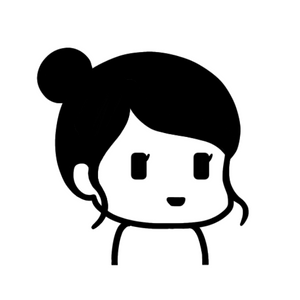
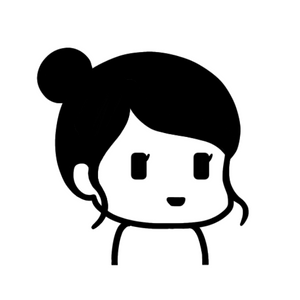
これは、渋柿・・・でいいのかな・・・?
と途端に不安になります(笑)
収穫するときは、極力、実に近い部分にハサミを充てて切ると良いそうです。





収穫!
足元は柿が落ちていて滑るところもあるので、気をつけながら収穫します。
袋がいっぱいになったら収穫終了。


柿狩りから戻ったところでちょうどお米も炊けた様子。もみ殻が綺麗に燃えて火が消えています。


秋晴れの中で新米試食会です





おー、銀シャリ!
お釜が開くと歓声が。
お米へのリスペクトは、やはり日本人だからでしょうか。
つやつやの新米は、用意いただいた具材を挟んでおにぎりにしていきます。






おにぎりの具材は、梅干し、味噌、おかかの3種。
おかずに酢の物と、柿もあります。



全部手作り
梅干しもおかかもすべて手作りなんですが、すべて美味しくて家庭料理のレベルが高すぎます。
酢の物も玉ねぎたっぷりの酸味控えめで、かなり美味しかったです。
そして、何よりも



やっぱり新米は粒立ちが違うねー
一粒一粒がしっかり、ふっくらとしています。
ほんのりおこげがあるのも、直火ならでは良さですよね。
さて、食事が終わったら、『新米30キロ』の受け取りと、柿の選別に向かいます。


希望者は事前申込みで、追加でお米を買うことも可能。
渡されるのは玄米なので、精米は各自で行います。(敷地内に精米機があるので、精米して持ち帰る人も)
収穫した柿は渋柿が混ざっている場合があるので、選別機にかけて判定します。




専用の機械に押し付けて、光の透過度(=中の密度)で見分けるんだそう。
「はい、これはOK」
「あ、これは渋だなー」



全然わからない・・・
スタッフさんが判定してくれますが、全然見分けがつきません。


切ってみると中が白くなっていて、これは渋くて食べられないんだそう。
判定結果は1つだけ渋柿でした。
渋柿分は甘い柿と交換してくれます。



お世話になりましたー
お米の受け取りと柿の選別が終わった人から、各自解散です。
いすみ米オーナー制度の次回は2月に菜の花摘み体験です。
それまではしばらくお休みですね。
最後までお付き合いありがとうございました。
▼前回は稲刈り体験をしました


この記事を書いたのは
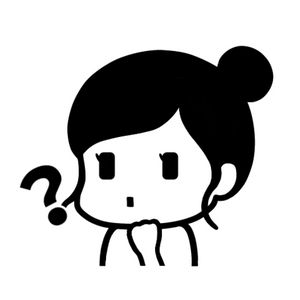
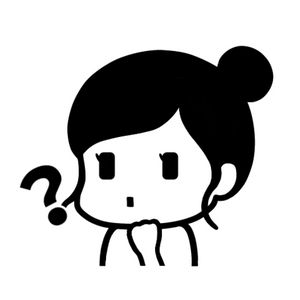
ソトボンヌ
現在、外房⇔埼玉で二拠点生活中
海沿い出身なので、泳げないけど海が好き
衰え知らずの探求心で、楽しいこと・美味しいものを探索

